書評
『噂の娘』(講談社)
観たことあるでしょう、映画の冒頭で。「さあ、今、この場所からお話は始まるんですよ」といわんばかりに、町並みを俯瞰で流し撮るシーンを。
洋品店や電器屋が並ぶ人通りもまばらな商店街の風景に、編み物教室で何台もの編み物機がたてる、じゃあーっ、じゃあーっという音や、その真向かいのパチンコ店が鳴らす軍艦マーチのやかましい旋律がかぶり――。金井美恵子の『噂の娘』は、そんな映画的な描写で幕を開ける。
一九五〇年代の晩夏、父親が入院したため知人の美容院に弟と二人預けられた少女の体験が、周囲の大人たちのお喋りを通じて再生される、これは記憶をめぐる物語だ。旦那に出奔されたおばあちゃん、寡婦のマダム、出戻りの長女、不倫の恋に悩む次女、あまり器量のよくない末娘に、住み込みで働きながら銀幕スターを夢みる娘などで構成される「女の館」モナミ美容室でやり取りされる会話が絶妙だ。男性にはわからない女同士のお喋りの愉しさを、これほど活き活きと活字で再現できる作家は、金井氏をおいて他にはいないと思う。
こうしたお喋りは時に「井戸端会議」と蔑(さげす)まれがちだけれど、この小説を読むと、教科書の歴史は男の会議によって作られたのだとしても、その行間を埋める生活の歴史は女の会話によって作られたのではないかと思えてくる。それほど彩り豊かな会話になっているのだ。かてて加えて、そうした会話の中に、今どきのそれと比べて断然ハイブロウな話題が時折混じることにもちょっと驚かされる。娯楽がそうはたくさんなかった時代だから、普通のお姉さんやおばさんたちもたくさん本を読んだり、映画を観ていたのだろうか。世代が下がるにつれて、一般人レベルにおける教養も低下しているってのは本当なんだなあ、と妙なところにも感心させられる井戸端会議ぶりなのである。
美容室にやってくる客がもたらす、駆け落ちや身投げや人殺しにまつわる虚実が判然としない噂話、ヘアスタイルやファッションの流行に関するディテール描写たっぷりのお喋り、恋の打ち明け話。語り手の少女がそうした大人たちの会話を再現する時、それは記憶の記述になる。ご存じのとおり、記憶というのはつかみ所がない。何かの拍子でリアルに立ち上ったかと思えば、追っても追っても逃げてしまったり、なかなかこちらの思い通りにはならないものだ。この小説でも、だから記憶はふいに思い出されたり、かき消えたり、細部の順序が入れ替わってしまったり、他の記憶と入り交じったりする。
にもかかわらず、読んでいて混乱させられることがないのは、絹のように美しく滑らかな文章ゆえ。その息の長い描写を多用した文章が、語り手の少女の記憶に母親の記憶や父親の子供時代の記憶を滑り込ませたり、本筋の物語にたくさんの映画や小説の物語を併走させるのだ。
とりわけ素晴らしいのがバーネットの『秘密の花園』の扱い。父母と離れてちょっとした孤児気分に浸っている語り手の少女が、そんな自分を植民地のインドで父母を失った主人公少女の境遇に重ね合わせているのだけれど、ここで作家はかの児童文学の名作を大胆に書き直しているのだ。金井氏がかつて少女時代に読んだ記憶上の『秘密の花園』を元に書いてみたという趣向なのだろうか。それがもう、「ジェイン・オースティンの作品です」と言われてうなずいてしまうほどの出来映えでっ! ここにもまた奇跡のごとく美しい記憶の改竄(かいざん)がある。
映画のようなシーンで始まったこの物語だけれど、最後は映像では決してできない、言葉だからこそ可能な試みで締められている。でも、この作品はそんな小説的企(たくら)みに満ちていながらもそうと感じさせず、読んでいる最中はひたすら読書の愉悦に浸ることができるというタイプの傑作なのだ。最後のページをめくる瞬間、読み終えるのを惜しむあまりに、あなたの「指はためらいに痙攣し、痙攣しつづける」のではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
洋品店や電器屋が並ぶ人通りもまばらな商店街の風景に、編み物教室で何台もの編み物機がたてる、じゃあーっ、じゃあーっという音や、その真向かいのパチンコ店が鳴らす軍艦マーチのやかましい旋律がかぶり――。金井美恵子の『噂の娘』は、そんな映画的な描写で幕を開ける。
一九五〇年代の晩夏、父親が入院したため知人の美容院に弟と二人預けられた少女の体験が、周囲の大人たちのお喋りを通じて再生される、これは記憶をめぐる物語だ。旦那に出奔されたおばあちゃん、寡婦のマダム、出戻りの長女、不倫の恋に悩む次女、あまり器量のよくない末娘に、住み込みで働きながら銀幕スターを夢みる娘などで構成される「女の館」モナミ美容室でやり取りされる会話が絶妙だ。男性にはわからない女同士のお喋りの愉しさを、これほど活き活きと活字で再現できる作家は、金井氏をおいて他にはいないと思う。
こうしたお喋りは時に「井戸端会議」と蔑(さげす)まれがちだけれど、この小説を読むと、教科書の歴史は男の会議によって作られたのだとしても、その行間を埋める生活の歴史は女の会話によって作られたのではないかと思えてくる。それほど彩り豊かな会話になっているのだ。かてて加えて、そうした会話の中に、今どきのそれと比べて断然ハイブロウな話題が時折混じることにもちょっと驚かされる。娯楽がそうはたくさんなかった時代だから、普通のお姉さんやおばさんたちもたくさん本を読んだり、映画を観ていたのだろうか。世代が下がるにつれて、一般人レベルにおける教養も低下しているってのは本当なんだなあ、と妙なところにも感心させられる井戸端会議ぶりなのである。
美容室にやってくる客がもたらす、駆け落ちや身投げや人殺しにまつわる虚実が判然としない噂話、ヘアスタイルやファッションの流行に関するディテール描写たっぷりのお喋り、恋の打ち明け話。語り手の少女がそうした大人たちの会話を再現する時、それは記憶の記述になる。ご存じのとおり、記憶というのはつかみ所がない。何かの拍子でリアルに立ち上ったかと思えば、追っても追っても逃げてしまったり、なかなかこちらの思い通りにはならないものだ。この小説でも、だから記憶はふいに思い出されたり、かき消えたり、細部の順序が入れ替わってしまったり、他の記憶と入り交じったりする。
にもかかわらず、読んでいて混乱させられることがないのは、絹のように美しく滑らかな文章ゆえ。その息の長い描写を多用した文章が、語り手の少女の記憶に母親の記憶や父親の子供時代の記憶を滑り込ませたり、本筋の物語にたくさんの映画や小説の物語を併走させるのだ。
とりわけ素晴らしいのがバーネットの『秘密の花園』の扱い。父母と離れてちょっとした孤児気分に浸っている語り手の少女が、そんな自分を植民地のインドで父母を失った主人公少女の境遇に重ね合わせているのだけれど、ここで作家はかの児童文学の名作を大胆に書き直しているのだ。金井氏がかつて少女時代に読んだ記憶上の『秘密の花園』を元に書いてみたという趣向なのだろうか。それがもう、「ジェイン・オースティンの作品です」と言われてうなずいてしまうほどの出来映えでっ! ここにもまた奇跡のごとく美しい記憶の改竄(かいざん)がある。
映画のようなシーンで始まったこの物語だけれど、最後は映像では決してできない、言葉だからこそ可能な試みで締められている。でも、この作品はそんな小説的企(たくら)みに満ちていながらもそうと感じさせず、読んでいる最中はひたすら読書の愉悦に浸ることができるというタイプの傑作なのだ。最後のページをめくる瞬間、読み終えるのを惜しむあまりに、あなたの「指はためらいに痙攣し、痙攣しつづける」のではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
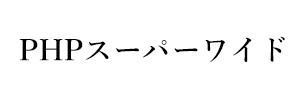
PHPスーパーワイド(終刊) 2002年5月
ALL REVIEWSをフォローする


































