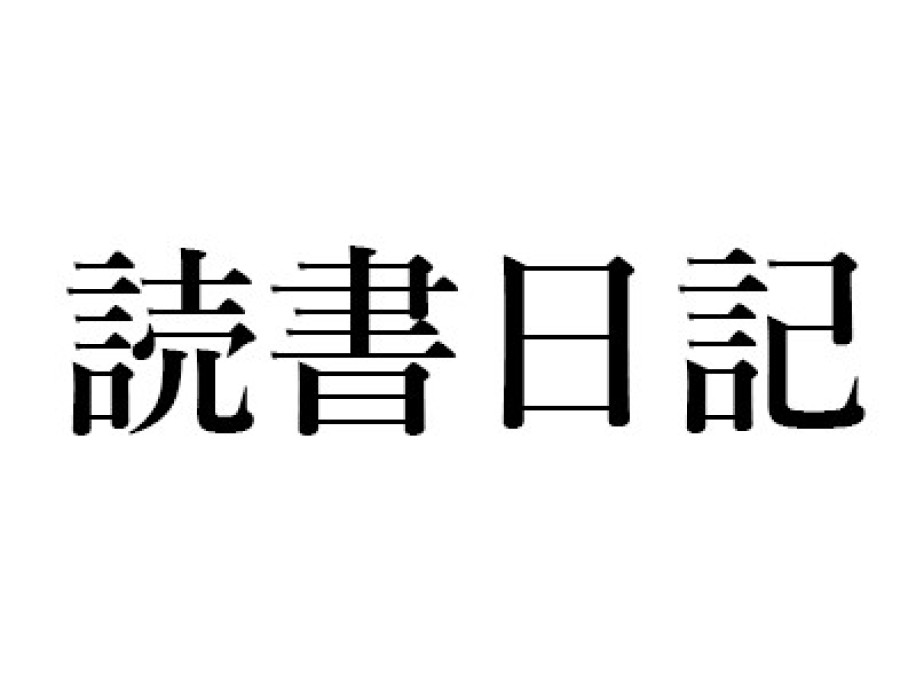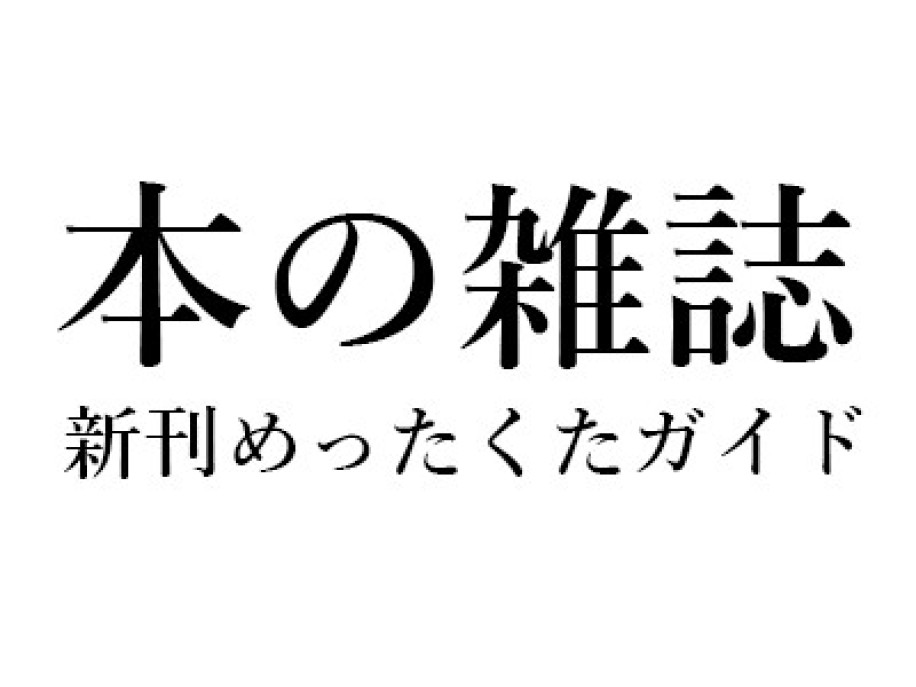書評
『20年後』(理論社)
作意が生む高踏的苦笑の快楽
本気になればなるほど臆病風が吹き、何も言い出せず行動も起こせず、さほど好きではない異性には堂々と振る舞える、これが恋愛の真理。心底恋をしてしまえば、勇気は失われ手も足も出なくなる悲しさ、情けなさ。ある男が、ふとしたはずみで公園の浮浪者に、一人で思い詰めている恋の悩みを吐露することになった。浮浪者はこの男に、自分のある体験を語ってきかせた。
自分はリングでは一度も勝ったことのない元ボクサーだが、ある夜、街のなかで喧嘩をふっかけて、一人の男を殴り倒してしまった。その男がミドル級世界チャンピオンと知って、気を失ってしまったという。
相手が誰かを知っていたなら、殴り倒すどころか、側溝を這いつくばってこそこそ通りすぎただろう。人間ってものは、自分にとって価値のあるものは特別の目でみるものなんだ……俺もあんたも同じことさ、プロに立ち向かうのは無理だってこと。あんたの場合は恋愛だが、あんたも俺と同じで負け犬なんだよ……闘う前に負けているんだよ……みたいなことを言う。
これを聞いて恋する男はがぜん奮起し、蛮勇をふるって、憧れの女性に電話をかける。
これで恋が成就したなら美談だが、待ちかまえているのは、ハッピーエンドでも悲劇でもない。もう一手どんでん返しが加えられたのち、アイロニーの幕が引かれる。(「高度な実利主義」、(1)『20年後』所収)
そのスタイルでオー・ヘンリーを紹介すれば、高度な数理主義者ということになろうか。
読者は情動の導きに従い必死で解に辿りついても、最後にその解を別の次元に導く変数や係数が用意されている。
書き始める前に机の上で、心理心情の素数を並べ替えたり組み合わせたりして、にやにや愉(たの)しんでいるショートストーリーの名手の姿が浮かんでくる。
いや、愉しんではいないだろう、物語の輪郭つまり線だけで、人間の本質と人生を描きだすためには、さぞ脂汗も流したはず。輪郭線だけで世界を切り取ったピカソの方が、輪郭を消して現実の印象を描いたターナーやモネより、ラクだったとは思えない。理に落ちた作意が正当に評価されない不満は、絵画においては抽象画としての評価でいくらかは癒されたかも知れないが、文学においては不当なまま置かれている気がする。ともかくスマートな手さばきは評価が低い。
しかしオー・ヘンリーの数理的作意は、いろんなかたちで受け継がれている。三島由紀夫の気の利いた短編にも、ジェフリー・ディーヴァーの立体的な企(たくら)みにも生かされ、その才気で読者をうならせている。作者に挑戦される読者の高揚と敗れる喜びを作り出したオー・ヘンリーのDNAは、後世の作家のなかにしたたかに生き残って、お、これはやられた、人間は外見じゃ判(わか)らんもんだ、という高踏的苦笑をもたらしてくれる。
和田誠さんは本紙の読書欄でもおなじみだが、このシリーズの表紙や挿絵を飾っておられて、いかにもこの短編集にふさわしい。
なぜか。和田さんはターナーやモネではなく、線だけで人間の姿かたちを、そして「点」だけの目でその心理を描いていて、オー・ヘンリーのトリックの、さりげない共犯者になっているからである。
小説を読む前とあとでは、登場人物の「点」の目が、まるで違う表情を持つことに気付かされる、これもまた快楽。(千葉茂樹・訳)
ALL REVIEWSをフォローする