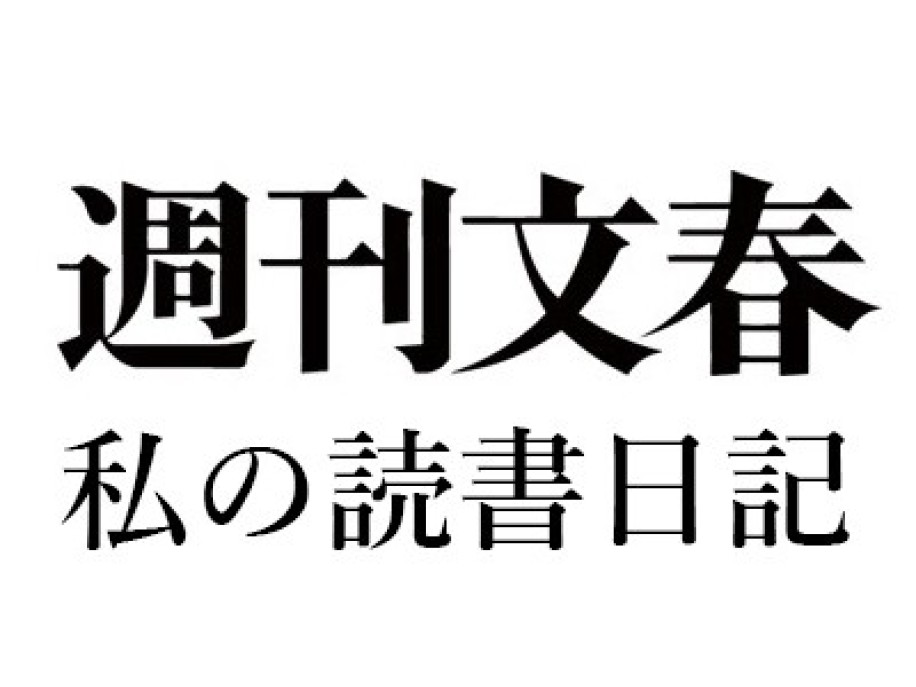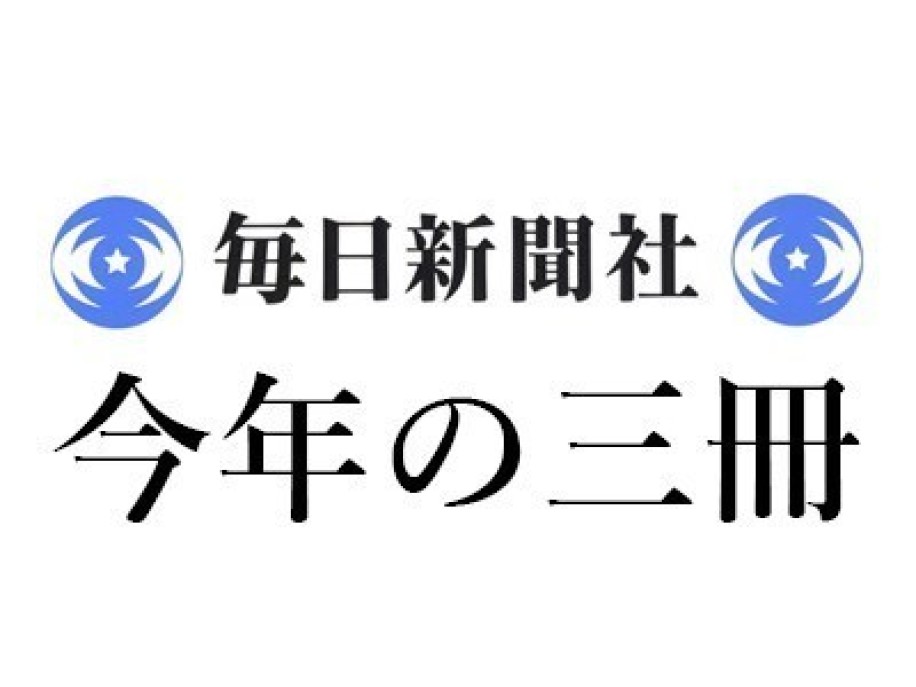書評
『赤い橋の殺人』(光文社)
忘却の淵から訳者に発掘された稀覯本
雑誌『ふらんす』(白水社)には「さえら」と題するページがあり、その月に刊行されたフランス関連書を網羅している。毎月、これを見るたびに「フランス熱は衰えたとはいえ、それでもこれだけの翻訳と研究が出ているのだ」と感心するが、そんな中でも本書が翻訳されたことは近来の快挙と呼んでいい。なぜか? 本書はたんにフランスで出た本を右から左に翻訳したというのではなく、一五〇年間忘却の淵(ふち)に沈んでいた稀覯本(きこうぼん)を訳者自身が血のにじむような努力で探し出し、ニース大学に三〇年前に提出した博士論文の添付資料というかたちで再刊したものの翻訳だからである。つまり、近年、インターネットと電子本の普及でようやく日の目を見るようになったシャルル・バルバラという作家は、訳者の発掘努力がなかったならフランス本国でも再評価の光が当たらぬまま、いまも忘れられていたかもしれないのだ。
では、シャルル・バルバラとはいかなる作家なのか? プッチーニの『ラ・ボエーム』の原作となったアンリ・ミュルジェールの小説『ラ・ボエーム生活情景』の音楽家バルブミッシュのモデルといえばわかりやすいか? つまり、バルバラは、一八二〇年前後に生まれ、飢えと引き換えにカルチエ・ラタンで自由気ままな生活を選んだボードレール、ナダール、シャンフルリー、ミュルジェールら放浪芸術家(ラ・ボエーム)に属し、その音楽的才能によりボードレールに大きな影響を与えたことが知られている。ところが実際には、その作品は誰も読んだ人はいなかったのだ。単行本未収録の作品が多かったし、単行本も一五〇年間再刊されなかったので、知りようがなかったのである。訳者はそれを論文執筆の過程で探索・読破することで、代表作の『赤い橋の殺人』は『罪と罰』のようなニヒリスト殺人を描いた探偵小説の元祖であると位置付け、同時に、バルバラが科学的知識を駆使したSF小説の元祖でもあることも明らかにしたのである。
というわけで、今回、翻訳された『赤い橋の殺人』はどのような物語か見てみよう。
ひとことでいえば、『ラ・ボエーム生活情景』とバルザックの『赤い宿屋』を足して二で割ったような内容ということになるだろうか?
小説は、ロドルフとマックスが「芸術家生活の様々な見込み違いや苦渋」について語りあっている場面から始まる。ロドルフ(モデルはミュルジェール)は芸術を第一義とする生活を棄(す)ててでも世に出たいと願う野心家だが、マックス(バルバラ自身)は「芸術作品とは、一般に困難の中から生まれ出る」と信じる禁欲的音楽家である。ロドルフはマックスが付き合っている女性が証券仲買人ティヤールの未亡人であることを知って驚く。ティヤールは義父の財産を蕩尽(とうじん)したあげく借金苦からセーヌに投身自殺したとされる話題の人物だったからだ。
マックスは次にラ・ボエーム仲間でも評判の悪いクレマンと再会し、クレマンが行いを改めてブルジョワとして落ち着いた生活をしていることを知る。クレマンは借金を踏み倒し、愛人のロザリと悲惨な生活を送っていたが、司祭に救われたのをきっかけにロザリと正式に結婚し、更生への道を歩んだのだという。 だが、 マックスはクレマンには隠された暗い部分があることに気づき、それとは知らぬうちに探偵の役割を演じていくことになるのだった。そして、ついに『赤い宿屋』的状況で秘密があらわにされるのである。
日本におけるフランス文学紹介の裾野の広がりを教えてくれる一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする