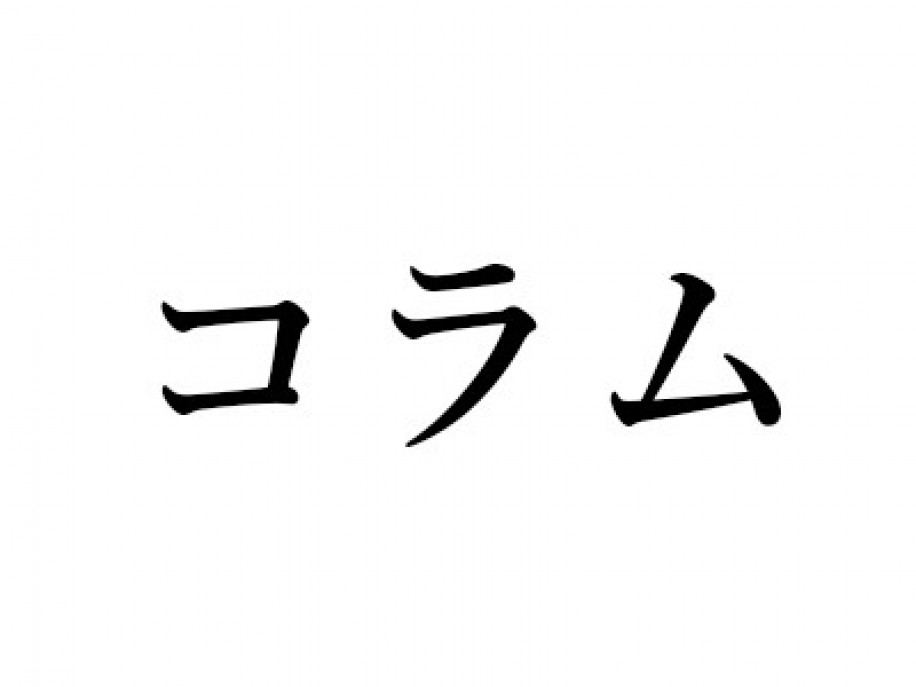書評
『満洲崩壊: 大東亜文学と作家たち』(文藝春秋)
戦後の文壇を見直す辛く偏らない批評眼
十数年、町で聞き取りをしていて思い知らされるのは、兵士ばかりでなく、満州・朝鮮などの日本の旧植民地居住者の多さだ。この小さな町にすら無数の〈外地〉体験、郷愁や恐怖、悔恨が埋まっているのに、それはふつう語られず、家族にも継承されない。川村湊氏は、文学世界において、その戦後空間のゆがみを補正しようとする。いや文学者や文壇が光を当てなかったマイナーな作家たちを掘り起こし、大衆文学として故意に無視された「人間の条件」や「大地の子」を爼上(そじょう)にのせる。さらに満州国の文化高官を父にもつ別役実や赤川次郎にそのことがどのように影響をもったか。意外な所まで論を広げて見せた。
評論、小説、紀行文、うらやましいような自由な手法で書かれたなかで、「花豚正伝」「林和別伝」「小林勝外伝」が圧巻だ。
「林和別伝」は、松本清張のモデル小説『北の詩人』に疑問を呈す。林和は果たしてアメリカのスパイか。これは朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)発表の裁判記録をうのみにしたフィクションではなかったか。
ひるがえって著者は林和と親しかった中野重治の「雨の降る品川駅」を考える。朝鮮人を「日本プロレタリアートの前だて後ろだて」とした“民族エゴイズム”を確かに中野は自己批判した。しかし「朝鮮人=テロリストという通俗的イメージ」にもたれかかり、彼らに昭和天皇暗殺を教唆した原詩についての自己批判は遅れた。「それが中野重治の“誠実さ”を割り引かせて考えさせるということに、私は口惜しい思いを禁じえないのである」
別の所で、「『帝国主義』権力と人民を区別することによって『日本人民』を免罪しようとする考え方」を批判し、「こうした言い方は、日本をも北朝鮮をも思想的に堕落させた」と指摘する。この、日本人であることだけにとらわれない、すこやかな目は本書のここかしこに生き、読む者は、自分を問われるのである。
ダダイストから共産主義者に、さらにコミューンを夢見て満州へ、あるいは朝鮮独立の闘士からファナチックな親日家へ。時代は変転し、思想や肉体は厳しく試された。忘れられた作家たちへの厳しい批評であり、あたたかい紙碑である。
朝日新聞 1997年9月21日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする