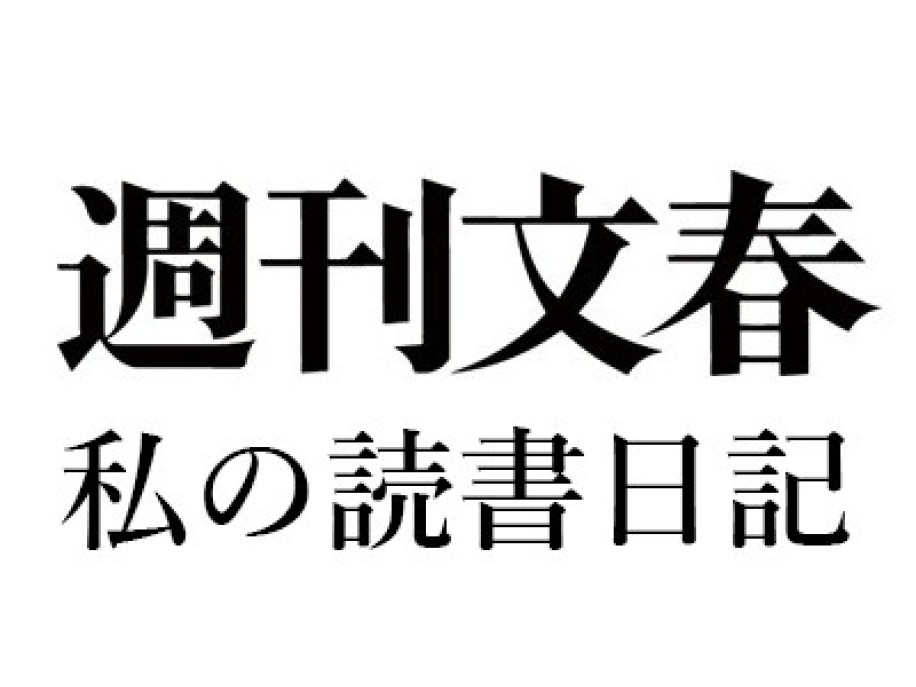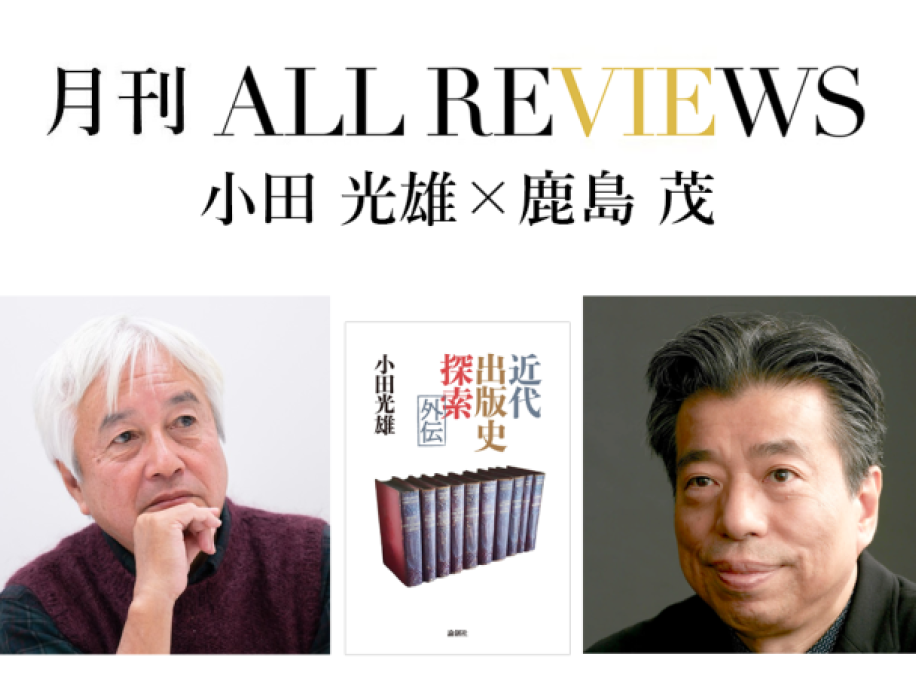書評
『ことばの劇場』(論創社)
舞台は「瞬間」で終わらない 心に沈む
演劇とミュージカルの評論書二冊に接し、メディアを超えた「瞬間」の記録と、その思索の道のりと情熱に打たれた。ひとの生を模倣し再現するあらゆるアートは人間が死に向かうための準備ではないか。それは、死、あるいは死による己の完全消滅に対抗し、同時に他者の存在を記録し継承する営為だと思う。
文学と演劇の決定的な違いと言えば、前者は保存と複製がきくのに対し、演劇はその世界がひとときで魔法の如(ごと)く消えるということだ。しかし『ことばの劇場』の著者は言う。「舞台を観(み)て、一晩寝れば、その記憶は消え去るものでしょうか。いえ、時間とともに発酵して、その経験は心に沈んでいきます」と。
本書に収められた全三部の文章は狭義の劇評ではない。著者は舞台上に出現する刹那(せつな)の時空間を、劇作家、演出家、役者たちの人生を織り交ぜつつ、言葉で補完し保管する。だから『ことばの劇場』なのだ。
第一部と第二部は、著者が初めて芝居を自分の意志で観た(唐十郎作・演出『二都物語』)一九七〇年代まで遡(さかのぼ)り、蜷川幸雄演出『ハムレット』(江守徹)から、藤田俊太郎演出『天保十二年のシェイクスピア』などがぎりぎり上演された二〇二〇年春のコロナ禍直前までの公演が比較的多く評される。
海外の劇場もめぐる。ブレヒト創立の「ベルリナー・アンサンブル」によるオリヴァー・レーゼ演出『ブリキの太鼓』(二〇一八年)の一人芝居(ニコ・ホロニクス)について、詳しく知る機会が(演劇誌を見逃した者に)あるだろうか。文字だけで場面が眼前に立ちあがってくる。
装置としては舞台の下手に巨大な木製の椅子が一つあるのみ。成人男性の俳優を三歳児に見せる工夫だ。歌舞伎にも暁通した著者は「歌舞伎舞踊の『藤娘』で六代目菊五郎が、装置の藤の房を大きく作った挿話」を引いてくる。
芝居に「血肉」を備えさせる補助技術として、著者はワイヤレスマイクや照明などの最新テクノロジーの力を認める。舞台を観客に届けるシアター・ライブやライブビューイング、テレビなどの舞台の記録、複製、放映についても肯定的だ。それらが劇場での上演を脅かすとは考えていない。音楽分野では録音やネット配信があっても、ひとはいまもホールへ足を運ぶではないか。それが舞台の魔力だ。
第三部は、市川團十郎、野田秀樹、ケラリーノ・サンドロヴィッチ、前川知大の近作について集中的に綴(つづ)る。「劇場の秘奥にある原初と直接ふれる技術」と著者が呼ぶものによって文字という二次元に呼び出されてなお演劇の精たちは躍る。
もう一冊はストレートプレイではなく、ミュージカルに特化した書である。
ブロードウェイ最高峰の賞にトニー賞がある。今年のミュージカル作品賞は『メイビー、ハッピーエンディング』。主要登場人物は二人(人間ではなくロボット)、豪華な舞台セットや大仕掛けの場面転換もあまりない韓国発の作品だと言うと、驚く人が多い。韓国発に驚くのもさることながら、ブロードウェイと言うと、超ロングランした『キャッツ』や『オペラ座の怪人』のような大がかりで、ファンタジックで、煌(きらび)やかなショーのイメージがいまも強いのだと思う。アカデミー賞に比べてトニー賞の傾向の変化は日本でほとんど知られていない。
そういう点でも『ミュージカルの「現在」 変容するトニー賞』は前世紀からブロードウェイで生舞台を観劇し劇評してきた著者による非常に貴重な体系的記録・評論だ。小山内は言う。「風に書かれた文字」と言われる演劇は公演が終わると消えてしまうが、その上演を活字で後世に残したい、と。
一時期、英国ウエストエンド発の大作に押され気味だったブロードウェイは、今世紀以降、米国らしさを俄然(がぜん)発揮する。著者はその契機を『レント』に見る。人種的少数者、移民、政治闘争、LGBTQ、対人関係などを題材に格差や分断をあぶり出す「社会派」の作品が激増するのだ。『イン・ザ・ハイツ』『キンキー・ブーツ』『ファン・ホーム』『ハミルトン』……かつての絢爛(けんらん)たるショーとは違う、ストリップトダウン(簡素化)した舞台も多い。
もう一つ本書で指摘されるのが、オフブロードウェイで好評を博しオンに昇格するショーが、高確率でヒットし受賞に至っているボトムアップの構造である。右に挙げた四作中三作がそれに当たる。
著者の克明な記憶力によるセリフや楽曲の精緻な分析も読みどころだ。『ハミルトン』で歌詞を替えて繰り返される旋律と英国王の零落。人間そのものへの風刺だと気づかされる。第二部には東京での公演の劇評を収録。「現在」のミュージカルの知性と奥深さを伝えてくれる一冊だ。
ALL REVIEWSをフォローする