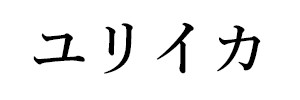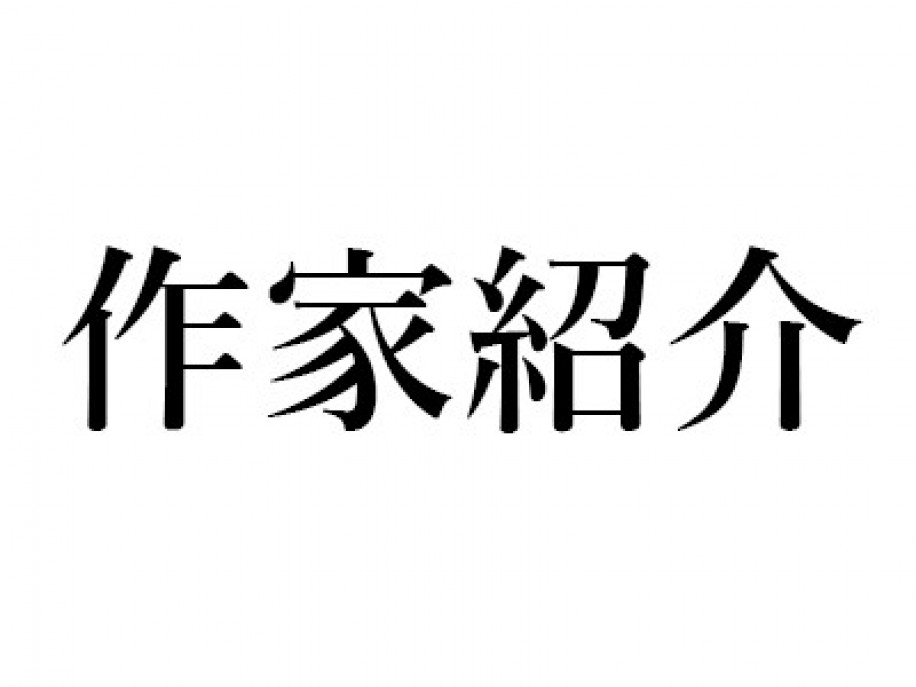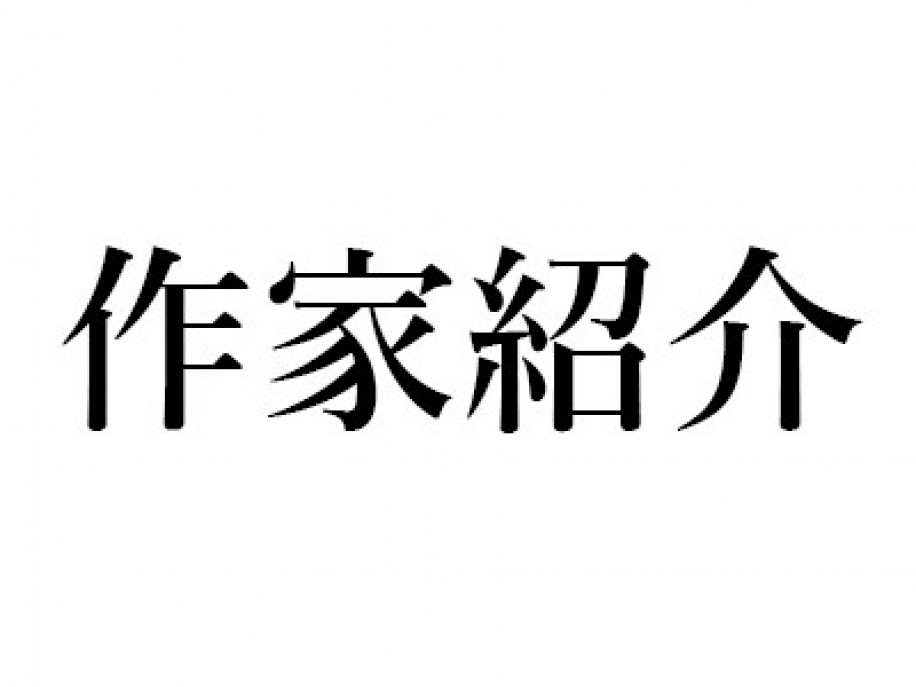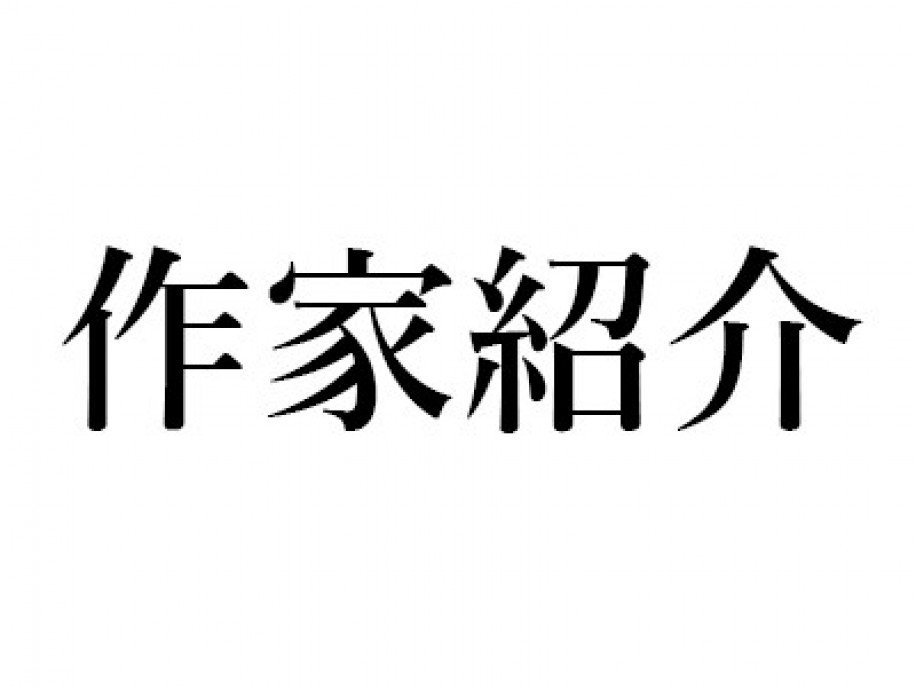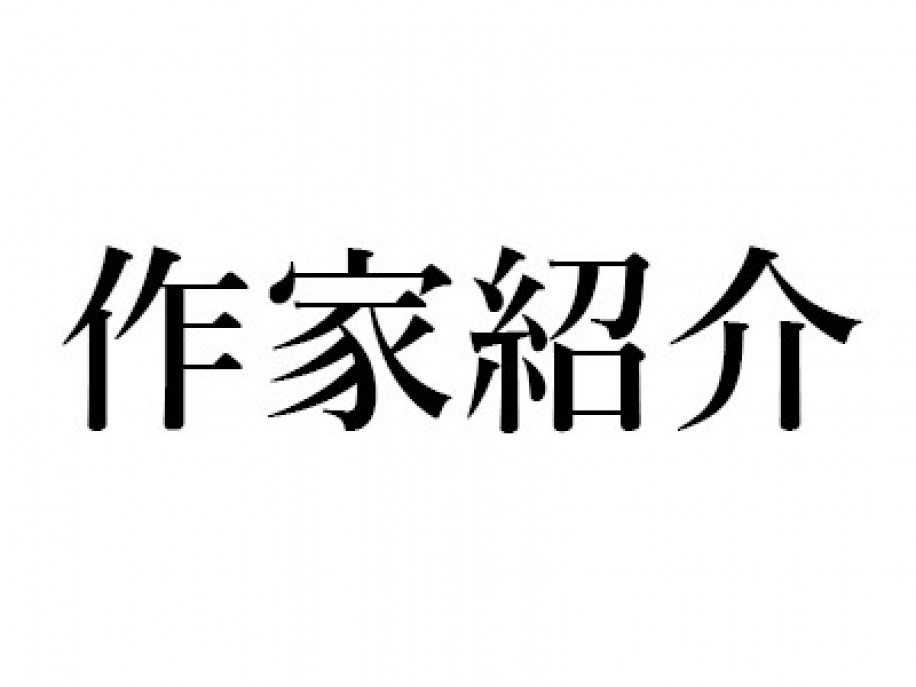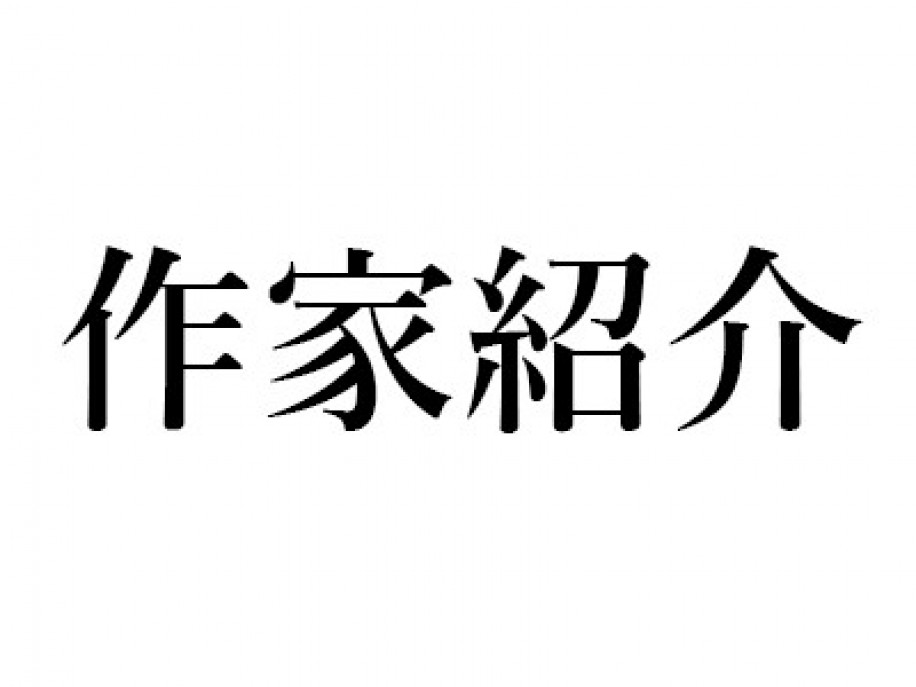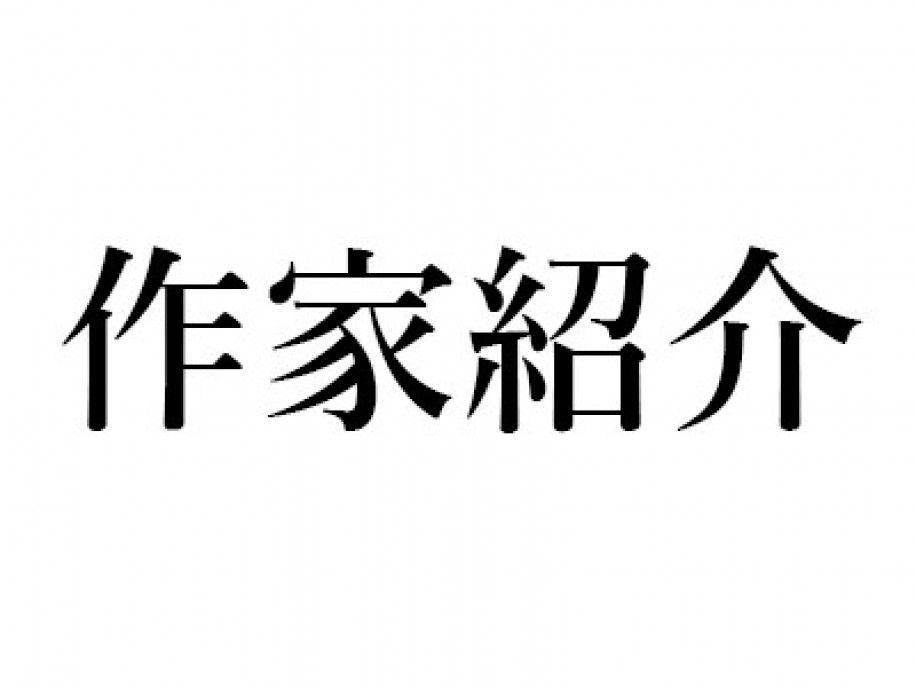作家論/作家紹介
【ノワール作家ガイド】レイモンド・チャンドラー『大いなる眠り』『湖中の女』『事件屋稼業』
一八八八年、シカゴ生まれ。幼少期にイギリスに渡り、当地で教育を受けたのち、二三歳で帰国。第一次世界大戦に志願兵として参戦したのち、石油会社に勤務。職を辞してパルプ・マガジン『ブラックマスク』に投稿した短篇「脅迫者は射たない」で作家デビュー、やがてハードボイルド探偵の代名詞たるフィリップ・マーロウを生み出す。七つの長篇を残したが、すべてがこのマーロウを一人称の語り手とした連作である。いまなお信奉者の多い「ハードボイルドの巨匠」である。
ここ数年、レイモンド・チャンドラーへの風当たりが強い。これまでの「ハードボイルドの巨匠」という評価に疑問を投げかける者が増えはじめたのだ。「現代ノワール」勃興の事実上の牽引者となったジェイムズ・エルロイ、日本で唯一と言ってもいいノワールの意識的な実作者/読み手である馳星周、さらには一貫してチャンドラー否定論を唱える船戸与一が代表格だ。エルロイはチャンドラーを「インチキ野郎」と呼び、馳星周はチャンドラーおよびそのフォロワーを「中産階級の手なぐさみ」と切り捨て、船戸与一は「自己韜晦の小説でしかない」と断じる。
この顔ぶれを見るかぎり、「ノワール」の視座に立てば、チャンドラーは大した作家ではないということになる。だが一方で、「正統ハードボイルド」の享受者にとっては、チャンドラーはいまも巨匠でありつづけている。
チャンドラーの作品――とりわけ探偵フィリップ・マーロウが主役を張る長篇――を他とわける最大のポイントは、その独特の散文(そして台詞回し)にあると言っていいだろう。長篇におけるプロットの弱さは多くのひとの指摘することだし、リアリズム描写にしたところで、それはすべてのハードボイルドの要件であるわけだから、とりたてて称揚できるほどのものではない。つまりは、当時勃興した「ハードボイルド小説」にチャンドラーが注入した、優れた散文の源泉たる独特の美意識こそが、その独自性の根拠なのである。
チャンドラーが自らのハードボイルド観を綴った有名な評論「簡単な殺人法」を見ると、こうした「美意識」は、ある種のロマンティシズムであることがうかがえる。稲葉明雄の評論「フィリップ・マーロウ誕生の前夜」から孫引きすれば、チャンドラーはその日記に、「現代という時代の殺伐さは(中略)さまざまなロマンチックな夢を打ち砕いてしまった」と綴っているという。つまりチャンドラーの見るかぎり、探偵小説=ハードボイルドを産み落としたこの時代の空気のなかでは、もはやロマンティシズムはリアリティを持ち得なくなっていたのだ。さらに、そうした事態に対する憤懣のようなものもこの文章の底には垣問見える。こうした思いから、チャンドラーは「卑しい街を往く騎士」たるフィリップ・マーロウに象徴される、「殺伐とした時代で生存し得るロマンティシズム」を生み出そうと試みたのではなかったか。そして、その試みを成功させたことが、チャンドラーに「巨匠」の称号を与える功績となったのだ。
だが、このロマンティシズムの存在が、チャンドラー否定論者の最大の論拠となっているのだ。凝った比喩や皮肉な軽口に彩られたチャンドラー作品の語り口は、その語り手たるマーロウが、そこで描かれる事態に深くコミットしていないことを暗示する。事態を冷静に眺め、感情移入を抑制しているがゆえに、それらを皮肉な洞察をもって描写することができるのだから。むろん、抑制の下にマーロウのセンチメンタルな部分が示されていることはたしかだが、少なくとも感情を抑制し得る程度のコミットメントしか、マーロウは行なっていない、と言うことはできよう。
つまりマーロウは、ロマンティシズムの担い手であるがゆえに、ロマンティシズムが生存し得ない殺伐とした世界と隔てられた存在にならざるを得ないのである。マーロウは、どんな状況にいても、すべてを他人事として皮肉に受け流す「アウトサイダー」であるのだ。だからこそ、マーロウは戦後の娯楽小説史のなかでつねにヒーローたり得た。われらの時代における、「正義」に代表されるロマンティシズムの体現者として。
こうしたヒーローを生み出し得たのは、チャンドラー自身の生育歴と無縁でないように思われる。アメリカに生まれ、人格形成期をイギリスで送り、最終的にはアメリカに戻った男。イギリス的な教養を持ちながらもアメリカの実業界に長く身をおき、イギリス人的ふるまいに対しても侮蔑感を抱いていた男。二つの国の文化がアンビヴァレントな状態で共存する男。チャンドラー自身が、己のコミットすべき場を見失った「アウトサイダー」だったのではないか。それが、マーロウのありようとして顕われたのではなかったか。
「ノワール」という点でチャンドラー作品に見るべきものは、あまりない。紙数の制約ゆえにロマンティシズムの含有量の少ない短篇小説――「雨の殺人者」「事件屋稼業」「ネヴァダ・ガス」など――に、そうした匂いを喚ぐことはできる。だがそれも、ポール・ケインあたりのノワール作家と比べれば、とりたてて優れたものではない。
チャンドラーをめぐる肯定/否定の立場のちがいは、なかなか見えづらい「ハードボイルド」と「ノワール」の相違を反映しているのではあるまいか。「リアリズムによって描かれる殺伐とした世界」という共通の舞台を持ちながらも、その世界から距離を保ってロマンティシズムを守るか、あるいはその世界に深くコミットして絶望とあがきを描き出すのか――そこに両者の境界線は引かれるのである。
【必読】『大いなる眠り』『湖中の女』『事件屋稼業』
ここ数年、レイモンド・チャンドラーへの風当たりが強い。これまでの「ハードボイルドの巨匠」という評価に疑問を投げかける者が増えはじめたのだ。「現代ノワール」勃興の事実上の牽引者となったジェイムズ・エルロイ、日本で唯一と言ってもいいノワールの意識的な実作者/読み手である馳星周、さらには一貫してチャンドラー否定論を唱える船戸与一が代表格だ。エルロイはチャンドラーを「インチキ野郎」と呼び、馳星周はチャンドラーおよびそのフォロワーを「中産階級の手なぐさみ」と切り捨て、船戸与一は「自己韜晦の小説でしかない」と断じる。
この顔ぶれを見るかぎり、「ノワール」の視座に立てば、チャンドラーは大した作家ではないということになる。だが一方で、「正統ハードボイルド」の享受者にとっては、チャンドラーはいまも巨匠でありつづけている。
チャンドラーの作品――とりわけ探偵フィリップ・マーロウが主役を張る長篇――を他とわける最大のポイントは、その独特の散文(そして台詞回し)にあると言っていいだろう。長篇におけるプロットの弱さは多くのひとの指摘することだし、リアリズム描写にしたところで、それはすべてのハードボイルドの要件であるわけだから、とりたてて称揚できるほどのものではない。つまりは、当時勃興した「ハードボイルド小説」にチャンドラーが注入した、優れた散文の源泉たる独特の美意識こそが、その独自性の根拠なのである。
チャンドラーが自らのハードボイルド観を綴った有名な評論「簡単な殺人法」を見ると、こうした「美意識」は、ある種のロマンティシズムであることがうかがえる。稲葉明雄の評論「フィリップ・マーロウ誕生の前夜」から孫引きすれば、チャンドラーはその日記に、「現代という時代の殺伐さは(中略)さまざまなロマンチックな夢を打ち砕いてしまった」と綴っているという。つまりチャンドラーの見るかぎり、探偵小説=ハードボイルドを産み落としたこの時代の空気のなかでは、もはやロマンティシズムはリアリティを持ち得なくなっていたのだ。さらに、そうした事態に対する憤懣のようなものもこの文章の底には垣問見える。こうした思いから、チャンドラーは「卑しい街を往く騎士」たるフィリップ・マーロウに象徴される、「殺伐とした時代で生存し得るロマンティシズム」を生み出そうと試みたのではなかったか。そして、その試みを成功させたことが、チャンドラーに「巨匠」の称号を与える功績となったのだ。
だが、このロマンティシズムの存在が、チャンドラー否定論者の最大の論拠となっているのだ。凝った比喩や皮肉な軽口に彩られたチャンドラー作品の語り口は、その語り手たるマーロウが、そこで描かれる事態に深くコミットしていないことを暗示する。事態を冷静に眺め、感情移入を抑制しているがゆえに、それらを皮肉な洞察をもって描写することができるのだから。むろん、抑制の下にマーロウのセンチメンタルな部分が示されていることはたしかだが、少なくとも感情を抑制し得る程度のコミットメントしか、マーロウは行なっていない、と言うことはできよう。
つまりマーロウは、ロマンティシズムの担い手であるがゆえに、ロマンティシズムが生存し得ない殺伐とした世界と隔てられた存在にならざるを得ないのである。マーロウは、どんな状況にいても、すべてを他人事として皮肉に受け流す「アウトサイダー」であるのだ。だからこそ、マーロウは戦後の娯楽小説史のなかでつねにヒーローたり得た。われらの時代における、「正義」に代表されるロマンティシズムの体現者として。
こうしたヒーローを生み出し得たのは、チャンドラー自身の生育歴と無縁でないように思われる。アメリカに生まれ、人格形成期をイギリスで送り、最終的にはアメリカに戻った男。イギリス的な教養を持ちながらもアメリカの実業界に長く身をおき、イギリス人的ふるまいに対しても侮蔑感を抱いていた男。二つの国の文化がアンビヴァレントな状態で共存する男。チャンドラー自身が、己のコミットすべき場を見失った「アウトサイダー」だったのではないか。それが、マーロウのありようとして顕われたのではなかったか。
「ノワール」という点でチャンドラー作品に見るべきものは、あまりない。紙数の制約ゆえにロマンティシズムの含有量の少ない短篇小説――「雨の殺人者」「事件屋稼業」「ネヴァダ・ガス」など――に、そうした匂いを喚ぐことはできる。だがそれも、ポール・ケインあたりのノワール作家と比べれば、とりたてて優れたものではない。
チャンドラーをめぐる肯定/否定の立場のちがいは、なかなか見えづらい「ハードボイルド」と「ノワール」の相違を反映しているのではあるまいか。「リアリズムによって描かれる殺伐とした世界」という共通の舞台を持ちながらも、その世界から距離を保ってロマンティシズムを守るか、あるいはその世界に深くコミットして絶望とあがきを描き出すのか――そこに両者の境界線は引かれるのである。
【必読】『大いなる眠り』『湖中の女』『事件屋稼業』
ALL REVIEWSをフォローする