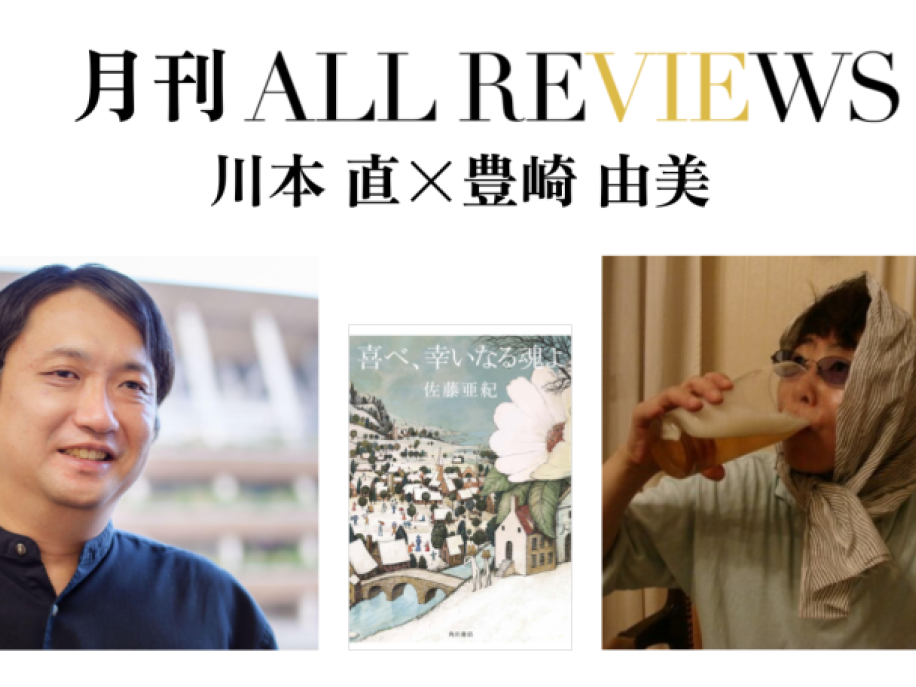読書日記
多和田葉子『百年の散歩』(新潮社)、佐藤亜紀『スウィングしなけりゃ意味がない』(KADOKAWA)、松浦理英子『最愛の子ども』(文藝春秋)
不意打ちを楽しむ『百年の散歩』がすばらしい
「わたし」は、住んでいるベルリンの町を歩く。10の通りを歩く。カント通り、ローザ・ルクセンブルク通り、リヒャルト・ワーグナー通り……歴史上の人物名が冠されたそれらの通りを歩きながら「わたし」は「あの人」を待ち、想っている。どこかへ行くためではない散歩は「わたし」の耳に、目に、さまざまな不意打ちを与える。その不意打ちからひろがる思索を綴った多和田葉子『百年の散歩』(新潮社一七〇〇円)がすばらしかった。奇異茶店とか、国旗がハタハタめくとか、米寿色のスカートとか、散りばめられた言葉遊びがまず楽しい。〈字があると読んでしまう〉〈目の前に見える物を次々日本語に訳して〉しまう性分の「わたし」にとって、町は〈言葉の作業場〉なのだ。言葉はときに、サッカーの鋭いシュートのように「わたし」を直撃する。「あの人」を待つ古い店で、飛んできたのは「しぇるしぇ」というフランス語。「わたし」は昨日タクシーの運転手と交わした会話を思い出す。彼はこう言ったのだった。〈Berlinはフランス人がつくった町だ〉〈Berlinを都市にしたのはフランス人ですよ〉。
どこにいても、どの通りを歩いていても、その場所にまつわる声がいろいろな姿をまとって「わたし」に語りかけてくる。ときに「わたし」も彼らに語りかける。喧嘩を売ったり、彼らに同化したりもする。
たとえばコルヴィッツ通り。版画家・彫刻家のケーテ・コルヴィッツの名が付けられたその通りの、かつては東ドイツだった場所にある自然食料品店で、「わたし」は子供の幽霊にお菓子をねだられる。戦前から売られているお菓子だ。子供をあしらっていると、見知らぬ男に話しかけられる。「何も買えない世界から商品が溢れる世界に急に送り込まれて、とまどっているんです」。
店を出ると白黒の世界。「わたし」は近くの公園で人々を眺めるコルヴィッツを発見し、彼女の内面に入ってゆく。戦争に行きたいという次男の背中を押し、死なせてしまったことに対する激しい悔恨が渦巻いている。〈「祖国のための戦争などありえない」ことを教えてあげるべきだったのだ〉「わたし」は彼女を批判するが、それはコルヴィッツ自身の思いだ。
小さな縫い目ほどの穴が過去と現在の間にあるのではないか、そこを行き来している人たちがいるのではないかと「わたし」は思う。もしかしたら「わたし」が待ち続ける「あの人」もそのひとりなのかもしれない。いや、「わたし」がそうなのかも。随筆のようで幻想小説のようでもある連作短編集だ。
1940年代、ベルリンに次ぐドイツ第二の都市ハンブルクに「スウィング・ボーイズ」と呼ばれた若者たちがいた。ナチス政権下で頽廃音楽、敵性音楽とされたジャズに熱狂していた少年や少女。彼らから着想を得て書かれたのが佐藤亜紀『スウィングしなけりゃ意味がない』(KADOKAWA一八〇〇円)だ。
語り手のエディは、軍需工場を経営する父を持つブルジョアのお坊ちゃん。物語が始まる1939年、15歳の彼は、ヒトラー・ユーゲントの団歌を歌わされたり野暮臭い半ズボンを履かされたりすることに辟易している。ばっかじゃねえの、と思っている。生活に余裕はあるし、兵役を逃れる手立てもあるので、基本的にはイケイケのノリで生きている。
洒落た服と靴を身に着け、年齢をごまかしてカフェに入り、ジャズに身を浸し、踊る。天才的なピアノの腕を持つ友人マックスの即興演奏に心酔する(マックスが〈ドビュッシーを、ぐいっ、とスウィングさせ〉るシーンは最高だ)。BBCラジオから録音した音源で海賊盤のレコードを仲間たちと作って売り、それなりの稼ぎを得たりもする。スリリングな青春の日々。しかしそれが長くは続かないことは読者が知っている。エディは地獄を見る。
読み始めたら最後、徹頭徹尾クールで毅然とした文章に取り込まれ没頭せずにはいられない。負傷者が横たえられた工場内で「世界は日の出を待っている」が流れるラスト近くの場面は、しばらく本から顔を上げられなかった。今読むべき一冊だと全力で言いたい。
松浦理英子『最愛の子ども』(文藝春秋一七〇〇円)にも心底痺れた。舞台は、男女が別々のクラスに分けられている私学の高等部。高2の女子クラスの「わたしたち」が、教室内のアイドル──〈わたしたちのファミリー〉──を愛で、鑑賞する。配役はパパが舞原日夏、ママが今里真汐、そして子どもが薬井空穂。同級生であるところの「わたしたち」によって、この「三人家族」のふるまいと関係のなりゆきが語られる。
ときにどきりとするような言葉のやりとり、身体的接触の描写に甘い体臭を感じて胸苦しくなり、同時にああこれこそ松浦作品を読むときの快だ、と思う。天性の人たらしである日夏、意固地さが魅力の真汐、庇護欲をそそる小動物のような空穂。三人は「わたしたち」が共有する宝物だ。傍観者として、当事者として〈ファミリー〉を見守る「わたしたち」はやがて、学校内で繰り広げられた出来事のみならず、目の前にいないときの三人の言動、そして心の中までをも語り始める。〈ファミリー〉は言ってみれば「わたしたち」を「わたしたち」たらしめてくれている存在で、三人を語ることはすなわち「わたしたち」が「わたしたち」でいられることの証明だ。いつまでも〈ファミリー〉を見ていたいという切実な願いが「語りの中」に存在している。
日夏と真汐が近づくきっかけはあるちいさな事件だった。その場面に、アリシア・キーズのヒット曲「If I Ain’t Got You」が使われている。読後思い返してこの曲を聴いた。作者の初期の作品『ナチュラル・ウーマン』を読んだとき、アレサ・フランクリンのバージョンを探して聴いたことを思い出した。
ALL REVIEWSをフォローする