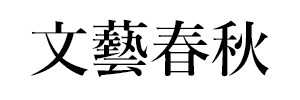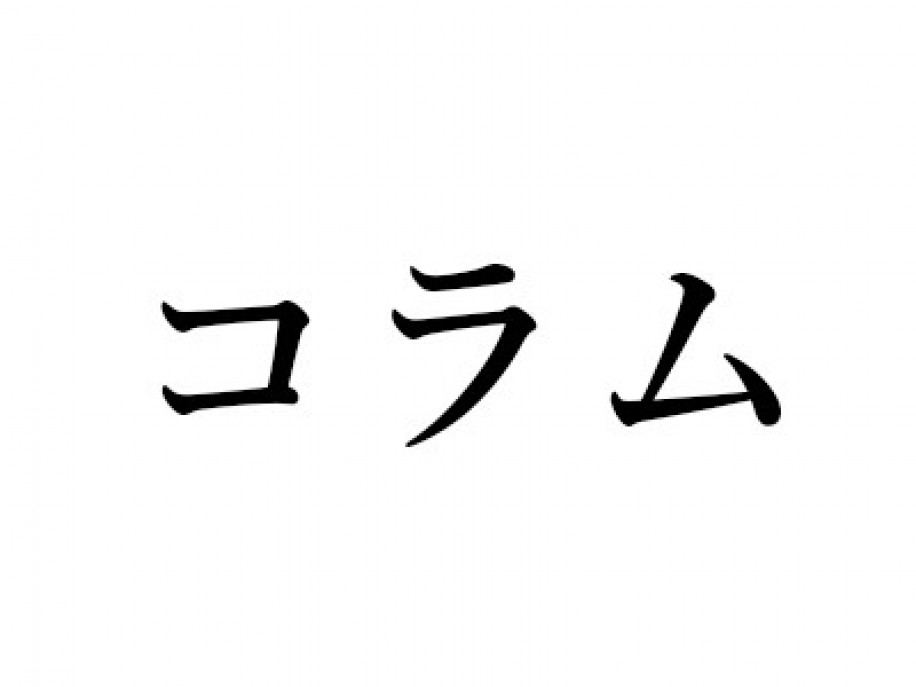対談・鼎談
ジョン・K・ガルブレイス『不確実性の時代』(TBSブリタニカ/講談社)|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
山崎 わたくしは、日本が万々歳だといいたいんじゃないんですよ。つまり、アメリカの知識人が挫折したとき、そこに見えてくるものは、世界全体の没落であったり、近代文明全体の傾きであったりするらしい。けれども、もう少し、彼が客観的にアメリカ以外の国を見回したら、そう慌てることはない、ということなんですよね。
木村 そう、この本が表わしているのは、まさに現代は哲学なき時代であるということですね。哲学なき時代であるということは、この本によると、非常に不確かな時代というふうに受け取られています。
しかし、十九世紀に哲学が必要だったのは、個人がいつも背中に死をしょってなければいけない状態だったからで、むしろ哲学なき時代というものが史上初めて到来したことの積極的な意義という点も強調してもらいたかった、と思いますね。
丸谷 アダム・スミスという人は、最初は哲学者だったわけでしょう。ところが経済学の祖となった。その扱った主題のせいでグングン哲学から離れていくことになるわけね。つまり、イデオロギーを捨てることになっていくわけですよ、逆にいえばね。これで経済学という学問の本来的な性格が非常にはっきりわかると思うんですよ。
山崎 そのときアダム・スミスが発見したのは「神の見えざる手」というものだったわけですね。競争原理の中からおのずから新しい秩序が生まれてくるーというのは、革命的な発見だった。それは、経済の現象においてそのとき初めて発見されたことだけれども、もっと広い社会秩序とか、道徳とか、哲学について、いま新たにわれわれが発見しつつあることかもしれないんですよね。かつてのように、特定の指導者の知恵ではなくて、大衆社会においては、「神の見えざる手」がこの混乱の中で動き出しているというふうに見てもいいわけでね。
だから、ガルブレイス氏がもう一歩進めば、現代において新しい「神の見えざる手」が動きつつあることを予見すべきだった。
木村 もう一つひっくり返していうと、だからアダム・スミス以来の経済学なるものが、それ自体としては、いま破産しつつあるということじゃないか。
丸谷 これに返事するのはむずかしいね(笑)。
山崎 何人かの友人の顔が浮かぶんですねえ……(笑)。
木村 不確実になってしまったのは経済学のほうで、文化の観点から広く今日の世界を見れば、決して不確実なだけとは思えないんですよ。
山崎 歴史学の世界も、文学の世界も、とうの昔に不確実だったし、それに気づいていたわけですね。ところが経済学だけは、ケインズが出てきたおかげで、ここ数十年間、その不確実性の自覚を先へ延ばして暮らしてきた。だから経済学だけが確実なように見えたんですね。それが要するに、普通の、ほかの学問並みになってきた、ということじゃないですか。
丸谷 経済学が進歩したの?
山崎 そういうことじゃないかな(笑)。
丸谷 翻訳について一言。
社会科学関係の本としては、非常によくできていると思うんです。ことに、講演形式の本であるにもかかわらず、「です」「ます」調ではなくて、「だ」「である」にしたため、頭に入り易くなっている。ところが、「です」「ます」を避けたためか逆にユーモアの出し方が非常にむずかしくなっている個所もありますね。
たとえば大不況の頃のソ連を書いたところがある。
ここのところなんか、どうも冗談の意味がピンとこない。だから、
「なにしろ、あのスターリンが、他人の苦痛のせいで苦しんだというんですから、それはずいぶん辛い時代だったんでしょうね」
とやると、冗談の気持がはっきり出ると思うんですよ。
山崎 まあ、細部には、ちょっと問題があると思います。
たとえば、原文では as well as だろうと思うんですが、そういうときにはただ「……も……も」でいいところを、「と同様に」なんて訳してありますね。
丸谷 多分 any だろうと思うところは、必ず「いかなる」となっている。
山崎 そうそう。そういう誤訳とスレスレの杓子定規が若干ありますね。
木村 それから地名の表記ですけれども、大体みんな英語読みになっているんですね。トリノがチューリンとなっている。セビリアがセビィルでしょう。
山崎 それにしても、ガルブレイスはこの十三回の連続テレビ講演をやるために、三年間用意したっていうんですね。これは、ガルブレイスさんも偉いが、BBCもたいへん偉い。三年間、多分ガルブレイスさんはタダで用意をしていたわけではなく、当然、それに見合うだけの報酬をBBCが払ったはずです。日本ではなかなか、十三回のテレビドラマのために三年間の用意はできない。
木村 非常に知的レベルの高い、力のこもったものに、こうやって国営放送がまとまった金を出していくというのは、日本でも必要なことですね。いま日本ではNHKが早朝とか深夜にやっている大学講座くらいがせいぜいでしょう。これまでもE・H・カーの『歴史とは何か』とか、ケネス・クラークの『芸術と文明』その他様々な本がBBCから出ていますけれども、その点は、ちょっと羨ましいと思いました。
丸谷 まったく同感。こういうテレビ番組を見たいものですね。
【新版】
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
木村 そう、この本が表わしているのは、まさに現代は哲学なき時代であるということですね。哲学なき時代であるということは、この本によると、非常に不確かな時代というふうに受け取られています。
しかし、十九世紀に哲学が必要だったのは、個人がいつも背中に死をしょってなければいけない状態だったからで、むしろ哲学なき時代というものが史上初めて到来したことの積極的な意義という点も強調してもらいたかった、と思いますね。
丸谷 アダム・スミスという人は、最初は哲学者だったわけでしょう。ところが経済学の祖となった。その扱った主題のせいでグングン哲学から離れていくことになるわけね。つまり、イデオロギーを捨てることになっていくわけですよ、逆にいえばね。これで経済学という学問の本来的な性格が非常にはっきりわかると思うんですよ。
山崎 そのときアダム・スミスが発見したのは「神の見えざる手」というものだったわけですね。競争原理の中からおのずから新しい秩序が生まれてくるーというのは、革命的な発見だった。それは、経済の現象においてそのとき初めて発見されたことだけれども、もっと広い社会秩序とか、道徳とか、哲学について、いま新たにわれわれが発見しつつあることかもしれないんですよね。かつてのように、特定の指導者の知恵ではなくて、大衆社会においては、「神の見えざる手」がこの混乱の中で動き出しているというふうに見てもいいわけでね。
だから、ガルブレイス氏がもう一歩進めば、現代において新しい「神の見えざる手」が動きつつあることを予見すべきだった。
木村 もう一つひっくり返していうと、だからアダム・スミス以来の経済学なるものが、それ自体としては、いま破産しつつあるということじゃないか。
丸谷 これに返事するのはむずかしいね(笑)。
山崎 何人かの友人の顔が浮かぶんですねえ……(笑)。
木村 不確実になってしまったのは経済学のほうで、文化の観点から広く今日の世界を見れば、決して不確実なだけとは思えないんですよ。
山崎 歴史学の世界も、文学の世界も、とうの昔に不確実だったし、それに気づいていたわけですね。ところが経済学だけは、ケインズが出てきたおかげで、ここ数十年間、その不確実性の自覚を先へ延ばして暮らしてきた。だから経済学だけが確実なように見えたんですね。それが要するに、普通の、ほかの学問並みになってきた、ということじゃないですか。
丸谷 経済学が進歩したの?
山崎 そういうことじゃないかな(笑)。
丸谷 翻訳について一言。
社会科学関係の本としては、非常によくできていると思うんです。ことに、講演形式の本であるにもかかわらず、「です」「ます」調ではなくて、「だ」「である」にしたため、頭に入り易くなっている。ところが、「です」「ます」を避けたためか逆にユーモアの出し方が非常にむずかしくなっている個所もありますね。
たとえば大不況の頃のソ連を書いたところがある。
スターリン自身が後にチャーチルに語ったところでは、この時期が自分の生涯でいちばん苦しい時期だったという。スターリンが他人の苦痛ゆえに苦しんだというのであれば、それこそ本当に苦痛の時代だったのであろう
ここのところなんか、どうも冗談の意味がピンとこない。だから、
「なにしろ、あのスターリンが、他人の苦痛のせいで苦しんだというんですから、それはずいぶん辛い時代だったんでしょうね」
とやると、冗談の気持がはっきり出ると思うんですよ。
山崎 まあ、細部には、ちょっと問題があると思います。
たとえば、原文では as well as だろうと思うんですが、そういうときにはただ「……も……も」でいいところを、「と同様に」なんて訳してありますね。
丸谷 多分 any だろうと思うところは、必ず「いかなる」となっている。
山崎 そうそう。そういう誤訳とスレスレの杓子定規が若干ありますね。
木村 それから地名の表記ですけれども、大体みんな英語読みになっているんですね。トリノがチューリンとなっている。セビリアがセビィルでしょう。
山崎 それにしても、ガルブレイスはこの十三回の連続テレビ講演をやるために、三年間用意したっていうんですね。これは、ガルブレイスさんも偉いが、BBCもたいへん偉い。三年間、多分ガルブレイスさんはタダで用意をしていたわけではなく、当然、それに見合うだけの報酬をBBCが払ったはずです。日本ではなかなか、十三回のテレビドラマのために三年間の用意はできない。
木村 非常に知的レベルの高い、力のこもったものに、こうやって国営放送がまとまった金を出していくというのは、日本でも必要なことですね。いま日本ではNHKが早朝とか深夜にやっている大学講座くらいがせいぜいでしょう。これまでもE・H・カーの『歴史とは何か』とか、ケネス・クラークの『芸術と文明』その他様々な本がBBCから出ていますけれども、その点は、ちょっと羨ましいと思いました。
丸谷 まったく同感。こういうテレビ番組を見たいものですね。
【新版】
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする