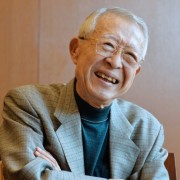書評
『自由の条件:スミス・トクヴィル・福澤諭吉の思想的系譜』(ミネルヴァ書房)
中産階級、民主主義への寄与と陥穽(かんせい)
著者は今年、自由を主題として二冊の本を発表した。五月の『自由の思想史 市場とデモクラシーは擁護できるか』(新潮選書)と、九月刊行の本書である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2016年11月)。どちらも著者らしい博捜の労作だが、後者はとくに論点を自由成立の社会的条件に集中し、それをめぐる一筋の思想の系譜を描出した。その点で叙述の具体性が増し、著者の政策的示唆もより明晰(めいせき)に読めるので、ここではこれを広く江湖(こうこ)に推奨したい。一言でいえば、自由が社会的に成立する条件は「中産階級」の隆盛である。それはトクヴィルが一九世紀の米国で刮目(かつもく)した現象であり、遡(さかのぼ)ればスミスが工業化初期の英国に見た都市商工民の誕生である。博識の著者は、同じ中流重視の見解を古くはアリストテレスに見いだし、降っては福澤諭吉の「ミッヅルカラッス」論に及ぶことを指摘する。
富みすぎず貧しすぎない中産階級は、第一に階層的な流動性に恵まれ、努力すれば上昇できるという可能性を信じている。すでに幾ばくかを所有している彼らは、過激な改革に走らず、より上層の階級にたいして怨嗟(えんさ)を抱くことも少ない。結果としてアリストテレスによれば、中間層はより柔軟に理性に従ってものを考え、福澤によれば「智力を以(もっ)て一世を指揮したる者」になりうる。
中産階級を生む商工業はまた、民衆に剥(む)き出しの自己利益ではなく、スミスのいう「同情」にもとづき、「全体の利益」との調和を計ったほうが得策であることを教える。トクヴィルは、この「啓発された自己利益」の精神が政治に現れたとき、米国の民主主義が成立すると考える。米国民にとって、全体との政治的な調和は貴族的な美徳ではなく、有益な処世術の一つであり、彼らはそれを経験から学んだのだった。
だが商工業を基盤とする中産階級は、一方では重大な欠陥を持つ。それは商工業が必然的に分業という方式をとり、それが民衆を専門化に導いて、知識と関心の「アトム化」を招くからである。分業は人を専門の狭い世界に閉じ込め、その外に広がる「公」の世界を忘れさせる。このアトム化による政治の危機は、トクヴィルをも福澤をも憂慮させ、著者自身にも深い懸念を抱かせる。
トクヴィルの見た米国には、この脅威を防ぐ三つの社会制度があった。一つにはタウンを中心とする小共同体への帰属、二つには裁判の陪審を務める義務、三つには財団や協会のような「結社」への参加であった。民衆はこれらによって国家と「私」の中間的な組織に触れ、「公」の存在を身近なものとして感じることができた。ちなみにこれと並ぶのが新聞のような報道機関であり、みずから結社の一種である新聞が情報を束ね、周囲に世論という共同体を組織することが、アトム化を防ぐ砦(とりで)として期待されるのである。
全巻を通じて著者が重視するのが言論の自由であって、これはたんに政治的自由の手段ではなく、真実にいたるための対話の自由、ソクラテス的弁証の自由として求められる。そのさい著者が清沢洌(きよし)を引いて、感覚や慣習から反射的に生まれる「第一思念」と、理性的な対話を経て生じる「第二思念」を峻別(しゅんべつ)しているのは、時宜に適(かな)っている。
二一世紀の現代、スマートフォンのような電子機器の普及が人びとの対話を断片化して、反射的な第一思念の交換ばかりを氾濫させている。結果として、隣近所のような社会の中間的な組織が弱体化して、まったく新しい種類のアトム化が進むことが恐れられるからである。
ALL REVIEWSをフォローする