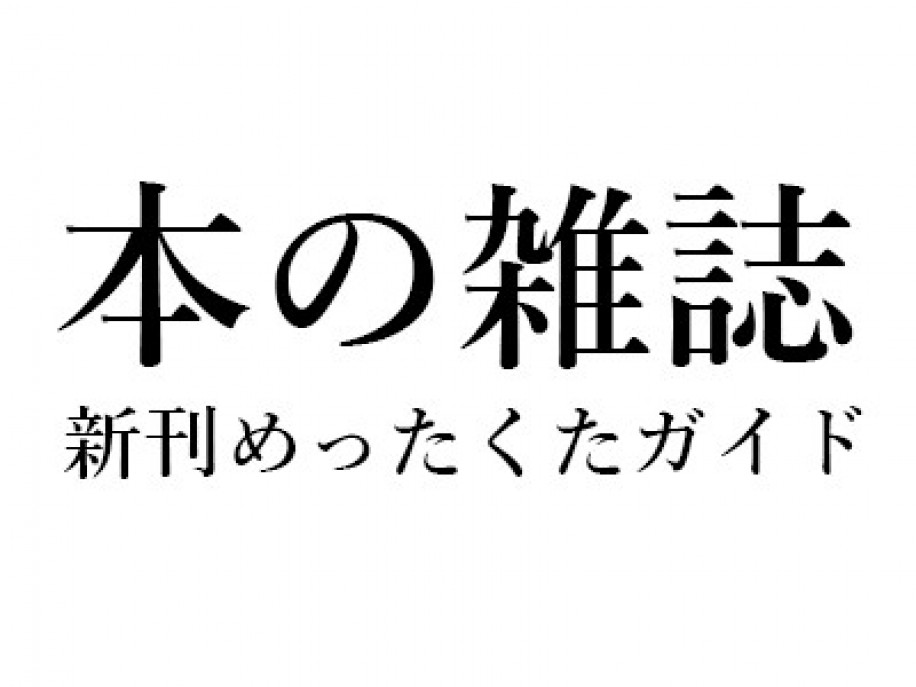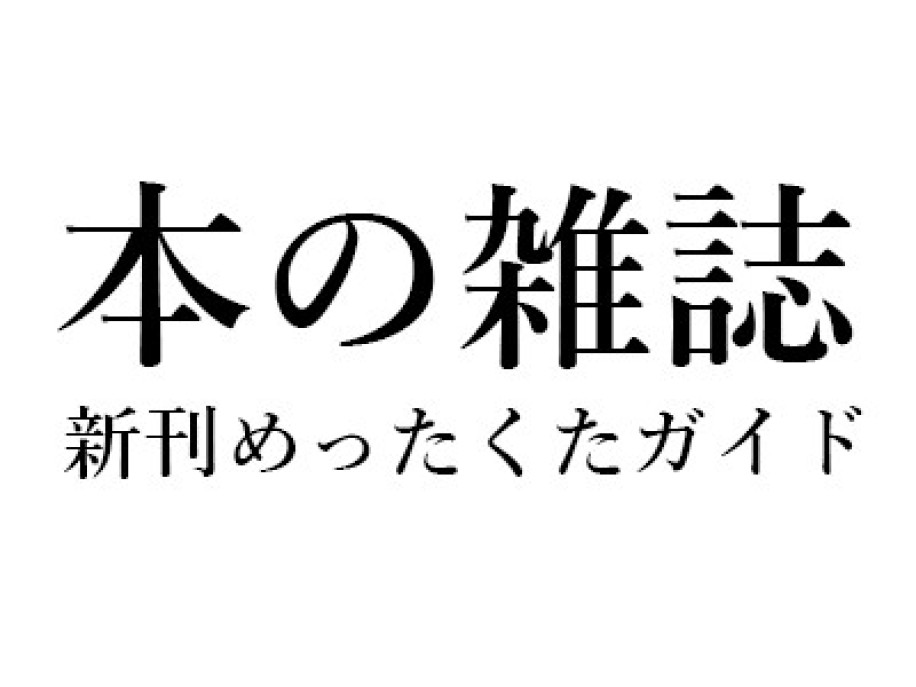読書日記
米光 一成「新刊めったくたガイド」本の雑誌2005年1月号―斎藤美奈子『物は言いよう』(平凡社)、金原瑞人『大人になれないまま成熟するために』(洋泉社)、他
(頭抱えて)こまってるんですよー。斎藤美奈子『物は言いよう』(平凡社/一六〇〇円)って本で、「セクハラですッ!」って口にするのはキツすぎる場合に、ピッタリくるのは「FC的にどうよ」だ、と提案してるのね。FCってのはフェミコードの略で、性別にまつわるおかしい言動を検討するための基準のこと。FCセンスを鍛えるためにダメ例をあげて斬りまくってる痛快本なんだけど。
よわっちゃうのが「ぼく」問題。哲学者・東浩紀の文章が、イラストライター・326(みつる)の文章にそっくりだって指摘してる項があって。そこでFC的非難をあびせられるのが、一人称の「ぼく」なんですよ。〝日本語文章のファルス(男性器)である〟なんて言われちゃうのなー。ぼくも一人称「ぼく」なので、えぇぇ、どうしよう、私とか小生にすべきかッって悩んじまうよね、初回の原稿だし(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年1月)。
でも、「ぼく」以外の一人称がうまく使えないってところを起点にして、大人らしい大人になれない自分をどう生きるかを語ってる本もある。金原瑞人『大人になれないまま成熟するために』(洋泉社/七四〇円)で、サブタイトルが〝前略。「ぼく」としか言えないオジさんたちへ〟。アンチ権威主義で、フェミ的にも歓迎されるスタンスだと思うんだけどなぁ。
何故音楽シーンにロックが登場したか、ヤングアダルト小説『アウトサイダーズ』(S・E・ヒントン著)が克服した課題とは何だったのか、なんてところがおもしろいし、まじめな「DT」本としても読めるし、団塊の世代への愚痴にも読める。聞き書き本なのに、修飾句が長くて文章が読みにくいのが残念なんだけどね。
ぼく問題を考えると、ぼくぼく言う人よりも恐ろしいのが、一人称単数を使わない人たちじゃないかな。ぼくって言わずに「わたしたちは」とか言っちゃって自分の責任を薄めちゃうようなタイプ。そういう己をちゃんと持たない人に苛立ってるのが森達也。彼の『世界が完全に思考停止する前に』(角川書店/一三〇〇円)は時事ネタの短いテキストを集めた本だから、そういった苛立ちがストレートに出てておもしろい。「主語のない述語は暴走する」なんてタイトルもあるし。「タマちゃんを食べる会」ってのもあるよ。
抗議されて、作品を簡単に封印しちゃうのも、やっぱり一人称単数的な覚悟がないからだと思うんだけど、安藤健二『封印作品の謎』(太田出版/一四八〇円)は、まさにそこに迫る本。『ウルトラセブン』十二話や、映画『ノストラダムスの大預言』や、『ブラックジャック』の脳関係のエピソードなどが、どうして封印されちゃったかを探るルポタージュで、なかなか「ぼくの作品だ!」って言う人にたどりつけないのが興味深い。
菊池成孔+大谷能生『憂鬱と官能を教えた学校』(河出書房新社/三五〇〇円)は、バークリー・メソッドと呼ばれる音楽教育システムについての講義の記録。
簡単に言えることを、哲学用語や難しい言葉使ったりして言う人のことを、わたくしは「難解ポエマー」って呼んでるんだけど、菊池さんは、いい難解ポエマー。難しい言葉を使うんだけど、それがカッコイイし、意味が伝わる。音楽に詳しくないから、わからないところもたくさんあるけど、読んでて楽しかった。オススメ。
ポール・スローン+デス・マクヘール『ポール・スローンのウミガメのスープ』(エクスナレッジ/一三〇〇円)は、推理問題集。たんなるクイズじゃなくて、おおぜいで遊ぶ推理合戦ゲームってところがミソ。
たとえば、「ある日、男がレストランでウミガメのスープを注文して飲んだ。その後、男は自殺した。何故だ?」って問題。で、みんなで質問する。「値段が高かった?」とか。出題者はあらかじめ解答を知ってるんだけど、「イエス」「ノー」「関係ない」しか返事しない。それで質問を重ねていって答えに近づいていく。「ウミガメ飼ってた?」「ノー」「船乗りだった?」「イエス」「過去に何かあった?」「イエス!」ってノリで。驚愕の真相に辿りつくまで、全員が探偵になってミステリー小説に入り込んだような興奮を味わえるので、ぜひ遊んでみて。問題が粒ぞろいな『推理クイズ道場ウミガメのスープ』(バジリコ/一二〇〇円)って本もあります。
そ、そして、オレをびっくりさせたのが、朱門『ありがとうのワークブック』(GAM出版/八〇〇円)! 開運のために四千回掛ける年齢分の「ありがとう」を、とにかくつぶやけっていう最初の説明をのぞくと、あとは全ページ「ありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとう」と〝ありがとう〟が一万個印刷されている奇書。(本を頭上に掲げて)今月の奇想本大賞に決定! 「ありがとう」の言霊のパワーに気づいたきっかけもすごい。近所にコンビニがたくさんあるけど何故かサンクスばかり行ってしまうから、サンクス(ありがとう)って言葉に力があるんだって気づいたそうですよッ。
荒井良二『ぼくとチマチマ』(学研おはなし絵本/一二〇〇円)は、絵本。猫を拾ったぼく。よあけがやってくる。鳥がやってきて、たいこがやってきて、スープがやってくる。チマチマは猫の名前。朝がやってくる。ただそれだけ。それだけなんだけど、今月、一番くりかえして読んじゃった本。自分の殻をやぶってくれる音楽に出会った時のように何度も読んだ。こどもの絵なの。スープなんて、えんぴつで「スープ」って書いてるんだよ。こどもがぐーでえんぴつ握って描いたような影とか。読むたびに子どもにもどってニコニコになるよね。
うーん、やっぱり、「ぼく」でやっていこう。未熟で甘えてるって非難されるかもしれないけど、まぁ未熟なんだからしょうがない。開き直りじゃない。使いなれない人称を使って、自分らしくないことをやるのヤだから。ぼくがおもしろいと思った本を、素直にオススメするようにがんばりますってことで。よろしく。
あー、最後に漫画だけど、すげぇぇぇので紹介。新條まゆ『ラブセレブ①』(小学館/三九〇円)は、日本最高の権力者にして超絶美形男子に惚れられた少女が、処女喪失寸前までいくたんびにトップアイドルへの道を(権力を使って)駆け上っていくとゆー現代少女の願望充足漫画の頂点ッ、かるちゃーしょぉぉぉっくですよ、お父さん! 美形権力男の一人称は「俺」です、「ぼく」とか言ってちゃモテないかもーーッ。では、また。
よわっちゃうのが「ぼく」問題。哲学者・東浩紀の文章が、イラストライター・326(みつる)の文章にそっくりだって指摘してる項があって。そこでFC的非難をあびせられるのが、一人称の「ぼく」なんですよ。〝日本語文章のファルス(男性器)である〟なんて言われちゃうのなー。ぼくも一人称「ぼく」なので、えぇぇ、どうしよう、私とか小生にすべきかッって悩んじまうよね、初回の原稿だし(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年1月)。
でも、「ぼく」以外の一人称がうまく使えないってところを起点にして、大人らしい大人になれない自分をどう生きるかを語ってる本もある。金原瑞人『大人になれないまま成熟するために』(洋泉社/七四〇円)で、サブタイトルが〝前略。「ぼく」としか言えないオジさんたちへ〟。アンチ権威主義で、フェミ的にも歓迎されるスタンスだと思うんだけどなぁ。
何故音楽シーンにロックが登場したか、ヤングアダルト小説『アウトサイダーズ』(S・E・ヒントン著)が克服した課題とは何だったのか、なんてところがおもしろいし、まじめな「DT」本としても読めるし、団塊の世代への愚痴にも読める。聞き書き本なのに、修飾句が長くて文章が読みにくいのが残念なんだけどね。
ぼく問題を考えると、ぼくぼく言う人よりも恐ろしいのが、一人称単数を使わない人たちじゃないかな。ぼくって言わずに「わたしたちは」とか言っちゃって自分の責任を薄めちゃうようなタイプ。そういう己をちゃんと持たない人に苛立ってるのが森達也。彼の『世界が完全に思考停止する前に』(角川書店/一三〇〇円)は時事ネタの短いテキストを集めた本だから、そういった苛立ちがストレートに出てておもしろい。「主語のない述語は暴走する」なんてタイトルもあるし。「タマちゃんを食べる会」ってのもあるよ。
抗議されて、作品を簡単に封印しちゃうのも、やっぱり一人称単数的な覚悟がないからだと思うんだけど、安藤健二『封印作品の謎』(太田出版/一四八〇円)は、まさにそこに迫る本。『ウルトラセブン』十二話や、映画『ノストラダムスの大預言』や、『ブラックジャック』の脳関係のエピソードなどが、どうして封印されちゃったかを探るルポタージュで、なかなか「ぼくの作品だ!」って言う人にたどりつけないのが興味深い。
菊池成孔+大谷能生『憂鬱と官能を教えた学校』(河出書房新社/三五〇〇円)は、バークリー・メソッドと呼ばれる音楽教育システムについての講義の記録。
簡単に言えることを、哲学用語や難しい言葉使ったりして言う人のことを、わたくしは「難解ポエマー」って呼んでるんだけど、菊池さんは、いい難解ポエマー。難しい言葉を使うんだけど、それがカッコイイし、意味が伝わる。音楽に詳しくないから、わからないところもたくさんあるけど、読んでて楽しかった。オススメ。
ポール・スローン+デス・マクヘール『ポール・スローンのウミガメのスープ』(エクスナレッジ/一三〇〇円)は、推理問題集。たんなるクイズじゃなくて、おおぜいで遊ぶ推理合戦ゲームってところがミソ。
たとえば、「ある日、男がレストランでウミガメのスープを注文して飲んだ。その後、男は自殺した。何故だ?」って問題。で、みんなで質問する。「値段が高かった?」とか。出題者はあらかじめ解答を知ってるんだけど、「イエス」「ノー」「関係ない」しか返事しない。それで質問を重ねていって答えに近づいていく。「ウミガメ飼ってた?」「ノー」「船乗りだった?」「イエス」「過去に何かあった?」「イエス!」ってノリで。驚愕の真相に辿りつくまで、全員が探偵になってミステリー小説に入り込んだような興奮を味わえるので、ぜひ遊んでみて。問題が粒ぞろいな『推理クイズ道場ウミガメのスープ』(バジリコ/一二〇〇円)って本もあります。
そ、そして、オレをびっくりさせたのが、朱門『ありがとうのワークブック』(GAM出版/八〇〇円)! 開運のために四千回掛ける年齢分の「ありがとう」を、とにかくつぶやけっていう最初の説明をのぞくと、あとは全ページ「ありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとう」と〝ありがとう〟が一万個印刷されている奇書。(本を頭上に掲げて)今月の奇想本大賞に決定! 「ありがとう」の言霊のパワーに気づいたきっかけもすごい。近所にコンビニがたくさんあるけど何故かサンクスばかり行ってしまうから、サンクス(ありがとう)って言葉に力があるんだって気づいたそうですよッ。
荒井良二『ぼくとチマチマ』(学研おはなし絵本/一二〇〇円)は、絵本。猫を拾ったぼく。よあけがやってくる。鳥がやってきて、たいこがやってきて、スープがやってくる。チマチマは猫の名前。朝がやってくる。ただそれだけ。それだけなんだけど、今月、一番くりかえして読んじゃった本。自分の殻をやぶってくれる音楽に出会った時のように何度も読んだ。こどもの絵なの。スープなんて、えんぴつで「スープ」って書いてるんだよ。こどもがぐーでえんぴつ握って描いたような影とか。読むたびに子どもにもどってニコニコになるよね。
うーん、やっぱり、「ぼく」でやっていこう。未熟で甘えてるって非難されるかもしれないけど、まぁ未熟なんだからしょうがない。開き直りじゃない。使いなれない人称を使って、自分らしくないことをやるのヤだから。ぼくがおもしろいと思った本を、素直にオススメするようにがんばりますってことで。よろしく。
あー、最後に漫画だけど、すげぇぇぇので紹介。新條まゆ『ラブセレブ①』(小学館/三九〇円)は、日本最高の権力者にして超絶美形男子に惚れられた少女が、処女喪失寸前までいくたんびにトップアイドルへの道を(権力を使って)駆け上っていくとゆー現代少女の願望充足漫画の頂点ッ、かるちゃーしょぉぉぉっくですよ、お父さん! 美形権力男の一人称は「俺」です、「ぼく」とか言ってちゃモテないかもーーッ。では、また。
ALL REVIEWSをフォローする