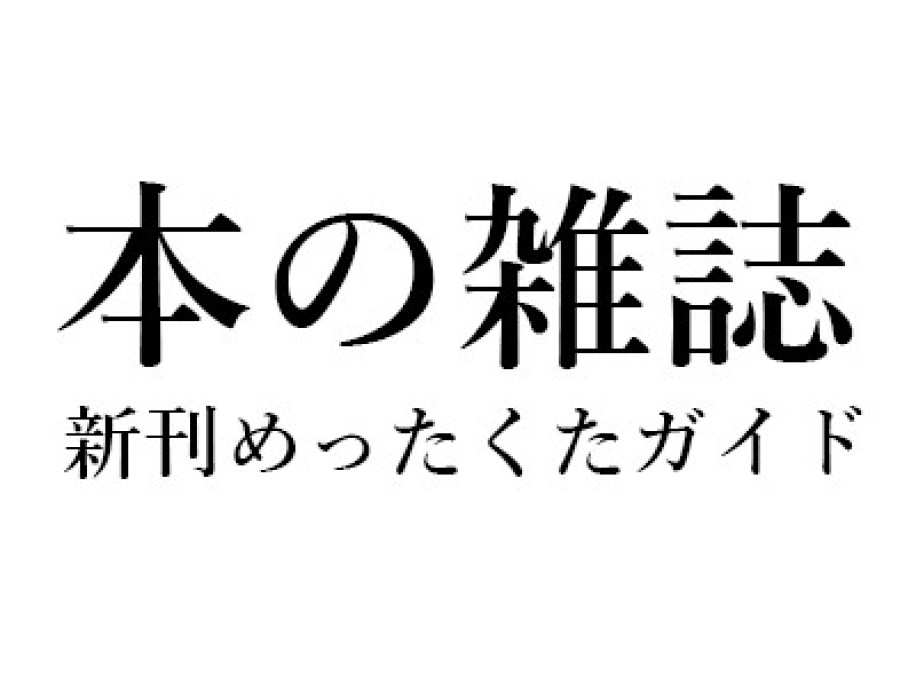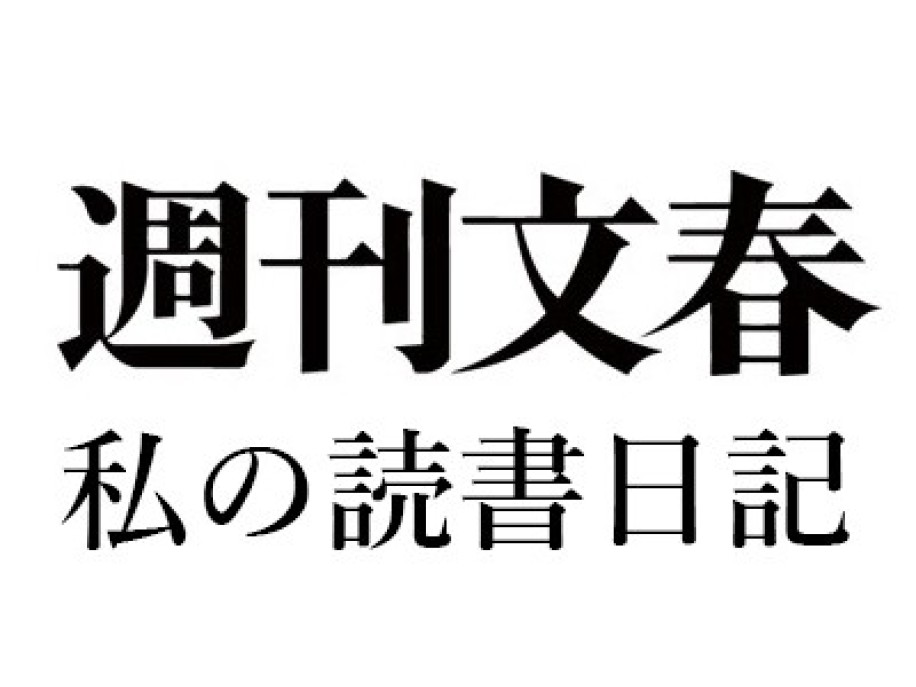書評
『植草甚一の勉強』(本の雑誌社)
図式化を拒み続けた渾身の十二年
稀代(きたい)のヒップ・スター植草甚一は、明治四十一(一九〇八)年に生まれて、昭和五十四(一九七九)年に没した。本書を開くとまず簡単な年譜が目に入るが、大衆消費文化を予言的に体現したサブカルチャー・アイコンにして、オタクの原型とも言い得るこの人物が明治生まれであったことにあらためて驚かされる。最初の本格的な単行本『ジャズの前衛と黒人たち』が出版されたのは一九六七年。還暦手前だ。四十一歳から専業の文筆活動に入っていたが知る人ぞ知る存在に留(とど)まっており、今日の植草のイメージは、それから死去までのわずか十二年間でつくられたものだ。その十二年間に植草は、書き捨てられていた原稿を編んだものなども含め二十冊を少し欠く著作を発表し、『ワンダーランド』(後に『宝島』)の責任編集者を務めた。一九七六年から実質的な全集である『植草甚一スクラップ・ブック』の刊行が始まり、死後一九八〇年に全四〇巻+別巻として完結した。
文章も書くジャズ・ミュージシャンである大谷能生が、植草の残した全著作を時系列に沿って読み、解題の体裁で著わした評伝、と本書は位置づけられるだろう。だが、この「時系列」というのが曲者だったと著者は最後に記している。
読むべきものが膨大なのははじめから分かっていたが、それがこれだけ体系を欠いた、実に感覚的な、どう切っても図式に還元できない細部の集積だとは思っていなかったのである。
これはしかし、植草が無節操だったことを意味しない。いや、興味対象が多岐にわたった点では無節操だったのだが、映画にしろミステリにしろジャズにしろキッチュの蒐集(しゅうしゅう)にしろ、徹底した「勉強」が「価値=権威の創出」にことごとく結びついていないのだ。
体系化図式化を拒むのは、植草の想像力のあり方そのものであり、発露としての文体であり文章である。
自伝が象徴的だ。植草には二つ自伝があるのだが、いずれも、過去の情景が「切断的」「点滅的」に昨日見たことなどと交錯しながらもぶつ切れのまま放り出されており、それぞれのイメージはクリアで情報の量も多いのに「「植草甚一の生涯」を再構築する作業は、とてもむつかしい」。記憶の再現からは自身の興味を欠くもの一切のみならず父母の死さえも消し去られており、おまけにある時点を限界に巻き戻される。この歴史化体系化に対するおそらくはトラウマ的な拒絶を、大谷は、故平岡正明の言を借りて「ニヒリズム」であるとする――「彼の明るさを支えているのは、徹底したニヒリズムなのだ」。
大谷の興味は自然、ニヒリズムにより生み出されたであろう植草の想像力を巡り、映画的と言い得る「具体的なイメージの運動」としての批評のスタイルに分け入っていく。音楽家ならではのこまやかさで。
さて、いま「批評」と書いた。植草の著述は普通「エッセイ」と呼ばれ「批評」とは見なされない。それを終始「批評」と呼ぶところにも、モダン・ジャズの歴史および批評の更新に長らく奮闘してきた著者の批評意識を読むべきである。
ALL REVIEWSをフォローする