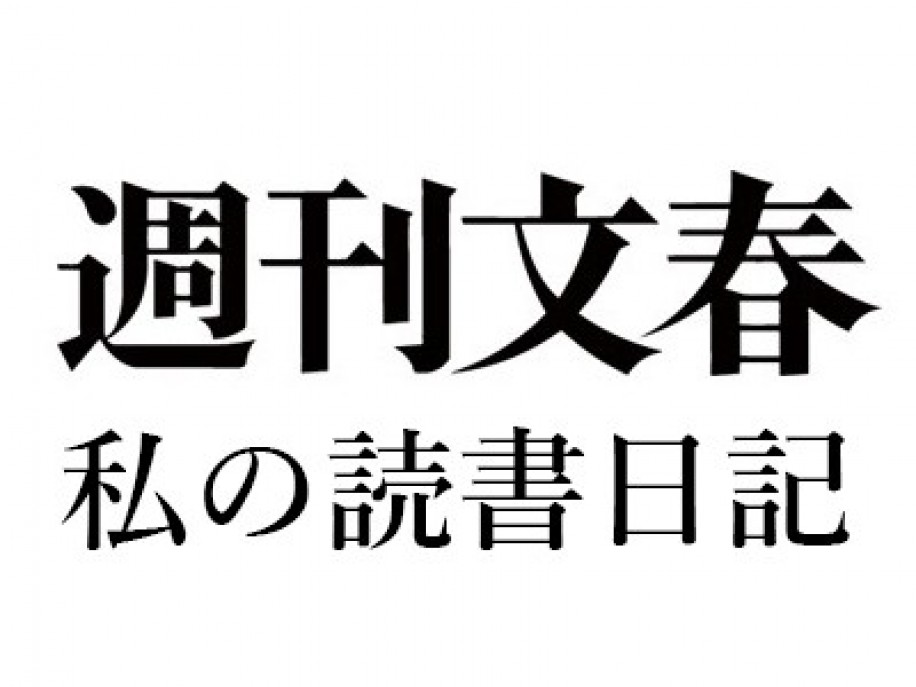読書日記
佐藤彰一『贖罪のヨーロッパ 中世修道院の祈りと書物』(中央公論新社)、フィリップ・セリエ『聖書入門』(講談社)
週刊文春「私の読書日記」
×月×日
二月末から三月にかけて出る大著三冊のゲラをチェックして出版社に送付した後、飛行機に飛び乗る。機中で佐藤彰一『贖罪(しよくざい)のヨーロッパ 中世修道院の祈りと書物』(中公新書 920円+税)を読み始める。同じ中公新書から二〇一四年に出た『禁欲のヨーロッパ』と対になる研究であり、ローマ帝国崩壊後のヨーロッパが、知的な面ばかりか経済的な面でも修道院によって支えられた社会であった事実を浮き彫りにした傑作である。私のような中世史のアマチュアにも非常に興味深く読むことができた。まず、通史から読み所をいくつか挙げてみよう。ローマ帝国末期、聖ホノラトゥス創設の南仏レランス修道院や聖マルティヌスが創ったマールムティエ修道院が大きな影響力を及ぼし、ガリア全土に修道院が建設されたが、西ローマ帝国が崩壊し、またメロヴィング朝フランクがサリカ法典特有の平等相続で分割を繰り返したことで社会的混迷が深まったため、修道院の影響力はいちじるしく低下した。そんな中、修道院ネットワークを支えたのが、イタリア半島からイベリア半島を回ってアイルランド、ブリテン島へと至る海洋ルートだった。中でもアイルランドから五九一年にブルターニュに到着して「ヨーロッパ修道制の歴史の転轍手として新しい地平を切り開いた」聖コルンバヌスの功績は大きかった。コルンバヌスはアウストラシアとブルグンドの分王国を支配していたキルデベルト二世の宮廷に招かれ、ローマ軍の要塞跡地に修道院を次々に建設していったが、それには全能の神に宗教的・倫理的な罪の赦しを乞う「贖罪」という観念を強く前面に押し出して、これを救済手段として社会上層部に訴えたことが大きく作用した。「コルンバヌス修道制の特徴はこれを修道・禁欲生活の中心に据えただけでなく、これを修道院の外の俗人にも届かせようとしたことであった」。その意図は初期フランクには存在していなかったとおぼしいフランク人貴族層がこの頃から台頭してきたことにより、見事に達せられることとなる。すなわち、コルンバヌス修道制がフランク貴族の門閥の心を捉えて領地の寄進を促し、「幼児献納」というかたちで子弟の修道院入りを増加させたのである。「こうした修道院には、しばしば土地の寄進がなされた。最大の寄進元は創建門閥であり、故人となった成員の『魂の救済』のための記念祈祷は、莫大な寄進が前提であった」。やがて寄進は創建門閥から近隣の大土地所有者に及び、修道院は地域の大所領主として成長してゆくのであるが、そのさい、所領の財産管理を管区司教権力から独立させる特権が与えられたことが中世社会を変容させる。なぜなら政治的・経済的な自由を得た修道院が「修道院経済」なる社会・経済システムを生み出していたからだ。それは市場での活発な交換・流通を伴う交換経済の段階に達していた。農民保有地が多い地域では領主が自由に労働や資本を配分できなかったのに対し、各地の大規模な修道院では賃労働者を自由に使って利益率の高い農業産品に特化し、これを分業的に生産することに成功したからである。さらに、修道院は金融活動や造幣活動さえ活発に行っていたが、それは利子を禁じた聖書の教えに反するとも思われていなかった。
では、「農村コングロマリット」として巨万の富を得ていた修道院は利益をいったい何につぎ込んでいたのかというと、これが写本の制作であった。写本制作は霊的修行と並んで末期ローマ以来修道院の主要な活動であり、高価だったパピルスや鞣皮紙に多くのテクストを詰め込むために独特の楷書体や草書体が考案された。とはいえ修道士の労働は無報酬だとしても鞣皮紙やインクに費用がかかった(一巻で約五〇〇頭の犢(こうし))ため、志の高い修道院はどこも巨額の資金の捻出を迫られていたが、所蔵する写本は修道院の財力とステータスのシンボルでもあったから、経済活動で得た富の多くは写本制作に費やされたのである。
ところが、こうした修道院経済は、カロリング・フランクでシャルルマーニュの跡を受けて王座についたルイ(ルートヴィヒ)敬虔帝がアニアーヌの聖ベネディクトをブレーンに起用して修道院改革に当たらせてからは、うまく回転しなくなる。ベネディクト戒律を厳格化して適用し、聖務と祈祷時間をより長くしたため、修道士たちが写本制作に時間を割くことができなくなってしまったからだ。
かくて、九世紀には修道院の経済活動と写本文化は衰退の一途をたどるが、その衰勢に追い打ちをかけたのが、ヴァイキング、イスラム、マジャールの侵略だった。彼らはキリスト教圏の富のありかを正確に見抜き、貴金属の聖具や写本を多く蔵する修道院を集中して略奪したため、カロリング・ルネッサンスの一翼を担った修道院は荒廃に任されたのである。修道制が回復するには彼らの襲撃を免れていたマコン地方からクリュニー修道院が起こって、ローマ教皇権力を後ろ盾に「修道院の系列化」を開始するまで待たなければならない。修道院という窓から眺めることで中世前期がまったく違うものに見えてくる。二〇一六年の新書ベスト・ワンである。
×月×日
歴史的興味が一九世紀から中世に移ってゆくにつれ、あらためて痛感するのは、ユダヤ・キリスト教文化に対する素養のなさである。旧約も新約も一通りは読んだつもりだったが、基礎力が足りないので理解がどうしても浅くなる。『源氏物語』を知らずに『新古今』を読むようなものである。かくてはならじと手に取ったのが、パスカル学の泰斗フィリップ・セリエの『聖書入門』(支倉崇晴・支倉寿子訳 講談社選書メチエ 2200円+税)。いや素晴らしい! ヨーロッパ文化の正しい理解には『聖書』の基礎知識が不可欠という姿勢で書かれた入門書であるからだけではない。それがパスカルという『聖書』の最も深い読解者を研究対象とした学者の手になる本である点がミソなのである。脱宗教化が著しいカトリック国フランスでベストセラーとなったのもむべなるかなである。
なにより作り方が巧みである。「聖書を構成している一つ一つの書は、まず最初に簡単に紹介される。次いで、各書の重要な人物やエピソードが、筋の通った簡潔な物語が展開する中に位置づけられて現れる」。すなわち、「聖書を構成している一つ一つの書」は、まず聖書学的見地からその成立過程や成立の時代が明らかにされてから、次いで「あらすじ」が解説的に記述され、最後に、それが後世の文学・美術・音楽などのジャンルにどのような影響を及ぼしたかが概観されるのだが、このどれにも類書にはない学問的蘊蓄が込められているのである。
たとえば、「モーセ五書」の一つ『創世記』のうちカインとアベルの物語は「兄の弟に対する憎悪、血のほとばしり、罪を犯した兄の苦悩と彷徨、暴力の氾濫は、寓話となって、いつまでも西洋の文学につきまとってきた」と簡潔に紹介されたあと、「暗いカイン像は特に演劇において数えきれないほど取り上げられ、ロマン主義のヒーローの一人となった。たとえば、バイロン(一八二一年)、ネルヴァルの『朝の女王と天分に溢れた君主ソリマンの物語』(『東方旅行記』一八五一年)、ザッヘル・マゾッホ、そしてとりわけユゴー。彼の精神分析医シャルル・ボードワンは、ユゴーの作品全体がカインのイメージにとりつかれていることを指摘した(『諸世紀の伝説』の中の『良心』)」と後世への影響が記されるが、これこそがわれわれ日本人にとって欲しかった知識なのである。
ヨーロッパの文学・芸術・思想に多少とも関心のある人なら座右の書となること間違いなしの一冊。こちらは選書部門のベスト・ワン。
ALL REVIEWSをフォローする