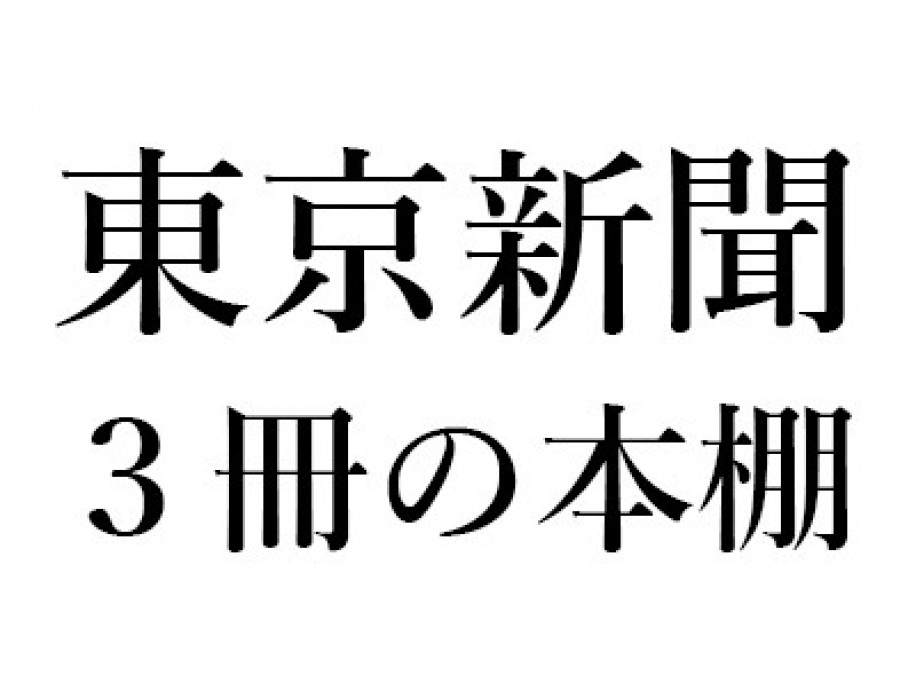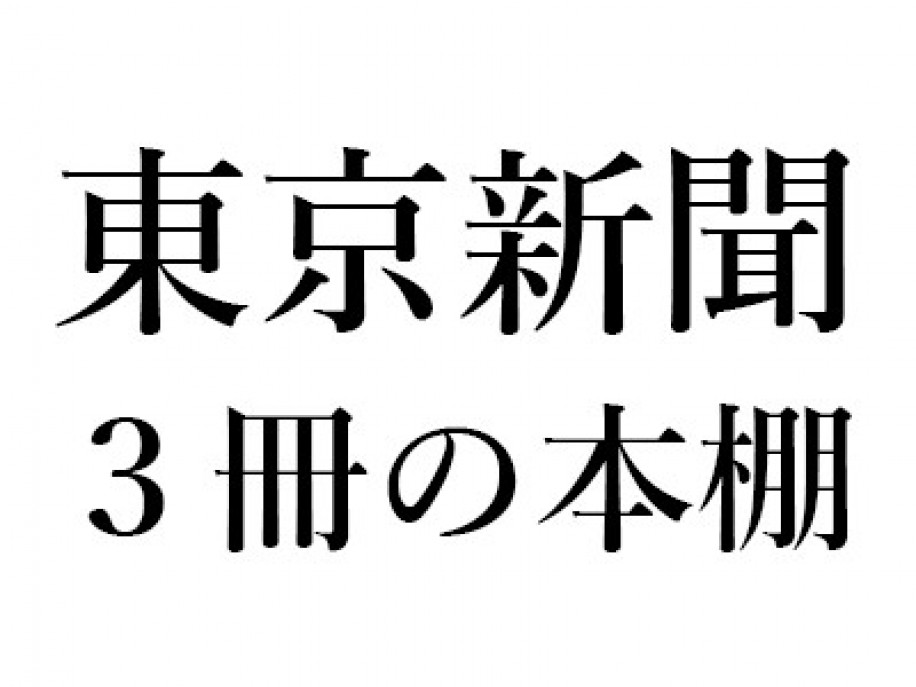読書日記
樹木 希林『いつも心に樹木希林』(キネマ旬報社)、原 武史+三浦 しをん『皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。』(角川書店)ほか
◆『いつも心に樹木希林 ~ひとりの役者の咲きざま、死にざま』(キネマ旬報社/税別1000円)
昨年9月に逝去して半年、生前の声や生きかたに共感し、称揚する出版物が続々と出ている。稀有な例だろう。『いつも心に樹木希林』は、インタビュー、対談、エッセー、関係者の追憶などで構成。「発掘」された原稿も。
芸能人の役割について「この世での役は、死に目に出会わなくなった世の人びとに、己の死にざまをお見せすることかもしれません」と、39歳で書いている。同調圧力になびかず、終始一貫「個」を貫いた人だった。
「万引き家族」の監督として濃密な時間を一緒に過ごした是枝裕和の弔辞。亡くなった日は、是枝の母の命日と同じだったという。さまざまなエピソードとともに「希林さん、私と、出会ってくれて、ありがとうございました」の挨拶(あいさつ)に、万感の思いがこもる。
1997年、本誌『サンデー毎日』に全5回で本人のイラスト入りのエッセーを連載していた。これも初耳。まことに天晴れな人生が、この一冊で通覧できる。
◆『皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。』原武史、三浦しをん・著(角川書店/税別1500円)
原武史と三浦しをん。天皇史を中心とした政治学と鉄学のスペシャリストと、『舟を編む』ほかでご存じの人気作家。異色の組み合わせがうまくハマって、対談集『皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。』ができ上がった。
原は三浦の小説もちゃんと読んできて、本人も気づかぬ鉄道史的背景を指摘する。過剰な「鉄オタ」ぶりに呆れつつ、しっかり食いついていく三浦も偉い。宮中女官の世界を描く松本清張作品『神々の乱心』をめぐる丁々発止のやりとりが前半の白眉か。
対談第4回は、2人で東武特急に乗って鬼怒川温泉への遠足旅。「いいなあ」「楽しそう」と三浦の素朴な感想に、東武にコンパートメント車両がある由来を瞬く間に解説してしまう原。すさまじい「鉄」分の血を感じる。絶妙の、いいコンビなのだ。
話題になった映画「シン・ゴジラ」も、原に言わせれば「鉄道的には見るところがなかった」と一刀両断。いやあ、徹底してるわ。
◆『世界怪奇残酷実話 浴槽の花嫁』牧逸馬・著(河出書房新社/税別1750円)
『世界怪奇残酷実話 浴槽の花嫁』の著者・牧逸馬を知らなくても、『丹下左膳』の林不忘は知っているだろう。同一人物で、ほかに谷譲次の筆名も持つ流行作家。若き日の滞米生活で収集した資料をもとに書いたのが、本書ほか一連の「実話」もの。「浴槽の花嫁」は、浴槽で新婚夫婦の妻が次々と溺死する事件を扱う。夫はいつも「スミス」(変名)で、金目当ての犯罪だった。ほか「女肉を料理する男」「都会の類人猿」「肉屋に化けた人鬼」と、タイトルからして恐怖に満ちている。
◆『明夫と良二』/庄野潤三・著(講談社文芸文庫/税別1800円)
徹底して家族を描き続けた庄野潤三。「山の上の家」と名付けられた主(あるじ)なき家は、昨年より早春と秋の2回、読者に開放されることとなった。今年2月には、日本全国から300人もの読者が集い、皆すぐに親しくなり、さながら知己のようだったという。読者を迎えるのが長男・龍也さん。本書『明夫と良二』の「明夫」のモデルだ。子ども向けに書かれた小説だが、いつも通りの筆致で、移ろいやすい家族の日々が描かれる。名作『夕べの雲』の一家は、作品と残された家で生き続けているのだ。
◆『平成の東京12の貌(かお)』文藝春秋/編(文春新書/税別980円)
文藝春秋編『平成の東京12の貌(かお)』は、高山文彦、稲泉連、服部文祥、野村進など一級の書き手が、「東京人の光と闇に迫る」。「保育園反対を叫ぶ人たち」(森健)、「東大を女子が敬遠する理由」(松本博文)、「将棋の聖地に通う男たちの青春」(北野新太)と、いずれも切り口がいい。自然や大地から遠ざかる、超高層の「タワマン」を取材した高山は、そこには「便利と安全が備わっている。でも大いなるものを人間から遮断し、奪っていはしないか」と突きつける。さようなら、平成。
昨年9月に逝去して半年、生前の声や生きかたに共感し、称揚する出版物が続々と出ている。稀有な例だろう。『いつも心に樹木希林』は、インタビュー、対談、エッセー、関係者の追憶などで構成。「発掘」された原稿も。
芸能人の役割について「この世での役は、死に目に出会わなくなった世の人びとに、己の死にざまをお見せすることかもしれません」と、39歳で書いている。同調圧力になびかず、終始一貫「個」を貫いた人だった。
「万引き家族」の監督として濃密な時間を一緒に過ごした是枝裕和の弔辞。亡くなった日は、是枝の母の命日と同じだったという。さまざまなエピソードとともに「希林さん、私と、出会ってくれて、ありがとうございました」の挨拶(あいさつ)に、万感の思いがこもる。
1997年、本誌『サンデー毎日』に全5回で本人のイラスト入りのエッセーを連載していた。これも初耳。まことに天晴れな人生が、この一冊で通覧できる。
◆『皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。』原武史、三浦しをん・著(角川書店/税別1500円)
原武史と三浦しをん。天皇史を中心とした政治学と鉄学のスペシャリストと、『舟を編む』ほかでご存じの人気作家。異色の組み合わせがうまくハマって、対談集『皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。』ができ上がった。
原は三浦の小説もちゃんと読んできて、本人も気づかぬ鉄道史的背景を指摘する。過剰な「鉄オタ」ぶりに呆れつつ、しっかり食いついていく三浦も偉い。宮中女官の世界を描く松本清張作品『神々の乱心』をめぐる丁々発止のやりとりが前半の白眉か。
対談第4回は、2人で東武特急に乗って鬼怒川温泉への遠足旅。「いいなあ」「楽しそう」と三浦の素朴な感想に、東武にコンパートメント車両がある由来を瞬く間に解説してしまう原。すさまじい「鉄」分の血を感じる。絶妙の、いいコンビなのだ。
話題になった映画「シン・ゴジラ」も、原に言わせれば「鉄道的には見るところがなかった」と一刀両断。いやあ、徹底してるわ。
◆『世界怪奇残酷実話 浴槽の花嫁』牧逸馬・著(河出書房新社/税別1750円)
『世界怪奇残酷実話 浴槽の花嫁』の著者・牧逸馬を知らなくても、『丹下左膳』の林不忘は知っているだろう。同一人物で、ほかに谷譲次の筆名も持つ流行作家。若き日の滞米生活で収集した資料をもとに書いたのが、本書ほか一連の「実話」もの。「浴槽の花嫁」は、浴槽で新婚夫婦の妻が次々と溺死する事件を扱う。夫はいつも「スミス」(変名)で、金目当ての犯罪だった。ほか「女肉を料理する男」「都会の類人猿」「肉屋に化けた人鬼」と、タイトルからして恐怖に満ちている。
◆『明夫と良二』/庄野潤三・著(講談社文芸文庫/税別1800円)
徹底して家族を描き続けた庄野潤三。「山の上の家」と名付けられた主(あるじ)なき家は、昨年より早春と秋の2回、読者に開放されることとなった。今年2月には、日本全国から300人もの読者が集い、皆すぐに親しくなり、さながら知己のようだったという。読者を迎えるのが長男・龍也さん。本書『明夫と良二』の「明夫」のモデルだ。子ども向けに書かれた小説だが、いつも通りの筆致で、移ろいやすい家族の日々が描かれる。名作『夕べの雲』の一家は、作品と残された家で生き続けているのだ。
◆『平成の東京12の貌(かお)』文藝春秋/編(文春新書/税別980円)
文藝春秋編『平成の東京12の貌(かお)』は、高山文彦、稲泉連、服部文祥、野村進など一級の書き手が、「東京人の光と闇に迫る」。「保育園反対を叫ぶ人たち」(森健)、「東大を女子が敬遠する理由」(松本博文)、「将棋の聖地に通う男たちの青春」(北野新太)と、いずれも切り口がいい。自然や大地から遠ざかる、超高層の「タワマン」を取材した高山は、そこには「便利と安全が備わっている。でも大いなるものを人間から遮断し、奪っていはしないか」と突きつける。さようなら、平成。
ALL REVIEWSをフォローする