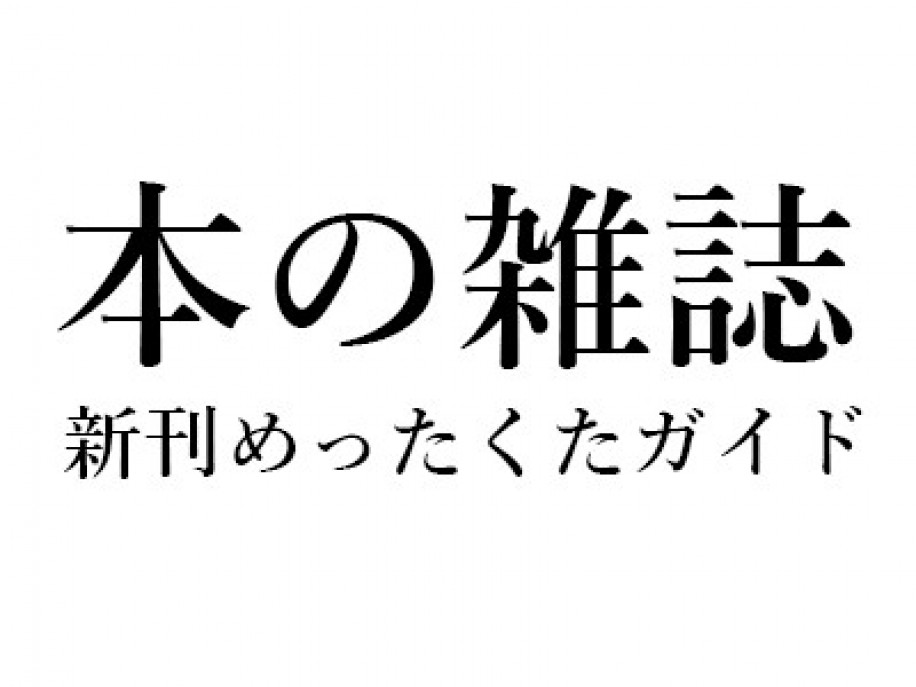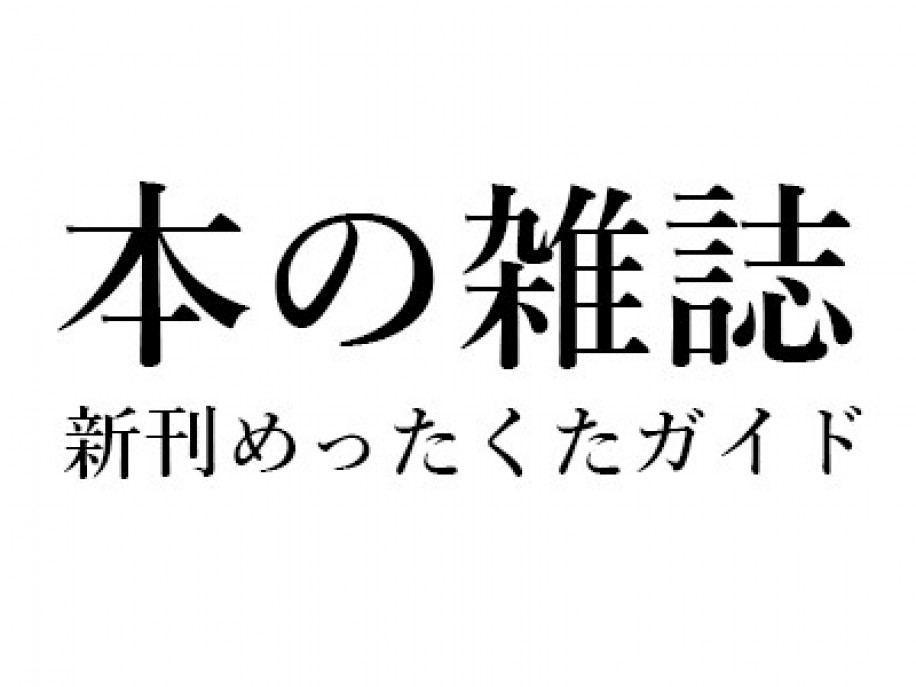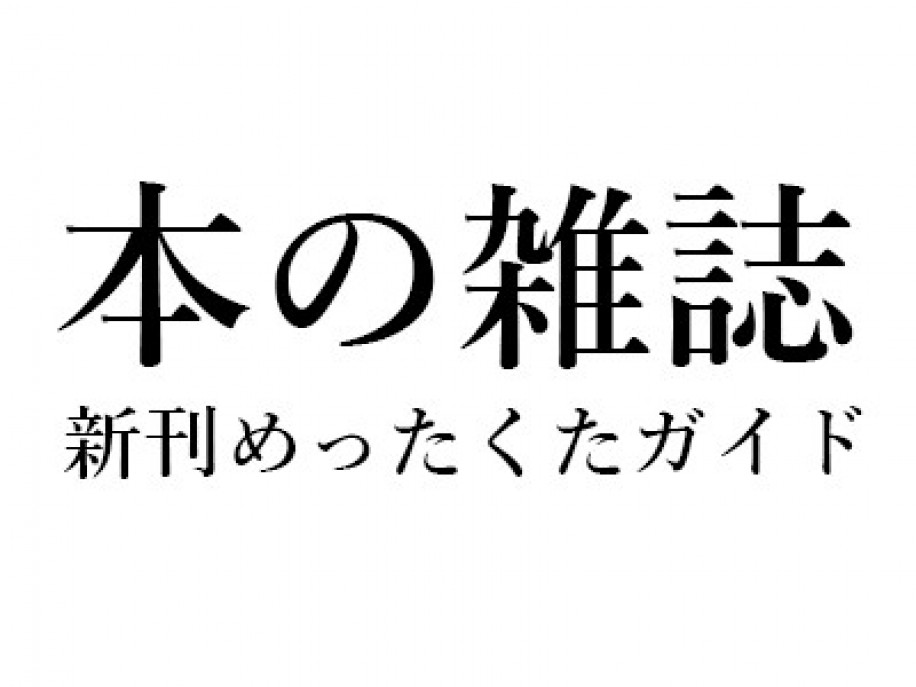読書日記
ジェームズ・ティプトリー他『20世紀SF〈4〉1970年代―接続された女』(河出書房新社)、中村 融,山岸 真『20世紀SF〈5〉1980年代―冬のマーケット』(河出書房新社)ほか
前世紀をまるごと総括する《20世紀SF》、ついに完結
河出文庫の年代別SFアンソロジー《20世紀SF》全六巻(中村融・山岸真編)が完結した。一九四〇年代から九〇年代まで、時代を十年ごとに区切り、二〇世紀の英米SFを文庫六冊で総括する。作品選択と歴史認識には若干の異論もあるが、英米SF短篇六十年の成果を凝縮したこの六冊は全SFファン必読の好企画。中村融による各巻巻末の解説は(巻によっては)大胆な史観を積極的に打ち出し、それ自体、クロノロジカルな英米SF論としても読める労作だ(ただし、各篇の前に付けられた一ページの解題は、わりと平気でネタを割ってたりするので、作品を読了後に読むほうが正解かも)。SFおたく歴三十年の大森の場合、ほとんどの作品は再読だったりするんですが、むかし傑作だと信じてた作品が経年変化ですっかり色褪せてたり、子供の頃はたいして感心しなかった作品の意外な深みに驚いたり、このアンソロジーを通読して評価が一変した作品も少なくない。企画としてはこれが二〇〇一年度文庫SFのナンバーワン。各巻ごとでは、初心者からマニアまでだれが読んでも平均的に面白いのが『②初めの終わり』(ただし、セレクションはこれがいちばん偏向してるかも)。一九六一年生まれの大森にとっては、④がいちばん懐かしい感じでした。まあとにかく、SFファンなら全巻揃えるのが基本。合計六千円はお買い得でしょう。
以下、当欄で未紹介の後半三巻( 70 年代〜90年代)について簡単に。
『④1970年代 接続された女』★★★☆では、G・R・R・マーティンの本邦初訳作「七たび戒めん、人を殺めるなかれと」が収穫。発表当時本国で絶賛されたビショップ「情けを分かつ者たちの館」はどこがいいのか謎。ラファティ「空」もやや疑問の残る選択だが、ヴァーリイ「逆行の夏」とプリースト「限りなき夏」を同時に収録したのはヒットですね。ル・グィンとラスはいま読むとちょっとつらい。
『⑤1980年代 冬のマーケット』★★★☆は、ラッカー「宇宙の恍惚」が思いきり浮いてますがオレは好き。スターリングの初訳「美と崇高」はまずまず。ライマン「征(う)たれざる国」は、アフガン空爆の続く今こそ再読したい傑作。スタン・ドライヤー「ほうれん草の最期」はこんなのをどうして入れたのかまったく理解できない。ま、すでに小川隆・山岸真編の『80年代SF傑作選』が出てることを思えば、この巻はじゅうぶん健闘していると言うべきか。
最終巻の『⑥1990年代 遺伝子戦争』★★★★では「しあわせの理由」がダントツ。イーガンの凄さを改めて実感しました。次点はビッスン「平ら山を越えて」。時代的な特徴が見えにくいのがこの巻の特徴か。全巻通して読むと、年代を追ってSFの水準がレベルアップしてきていることがよくわかる。
ちなみに、二十五人が投票したウェブ上の全作品考課表(林哲矢作成)http://www2s.biglobe.ne.jp/~ttsyhysh/diary/20cen_enq.html によると、全七十三篇のベスト10は、①イーガン「しあわせの理由」②ティプトリー「接続された女」③ヴァンス「月の蛾」④ライマン「征たれざる国」⑤ラファティ「町かどの穴」⑥ベア「姉妹たち」⑦ハーネス「現実創造」⑧ムーア「美女ありき」⑨ヴァーリイ「逆行の夏」⑩ビッスン「平ら山を越えて」というほぼ妥当な結果。ワースト3は、①ドライヤー「ほうれん草の最期」②クラーク「時の矢」③ディクスン「イルカの流儀」と、これまた納得の結果が出ている。
国内SFのほうは、あいかわらずの新刊ラッシュ。祥伝社文庫の中篇百五十枚書き下ろしシリーズ《400円文庫》第二弾は、前回から飛躍的にSFが増えて一挙五点を刊行。菅浩江『アイ・アム』★★★はホスピスで患者のケアを担当するロボットが主役。イーガンの短篇みたいな方向性だが、すれたSF読者には一瞬で結末が読めるのが難。ふだんSFを読まない人のほうが素直に感動できるかも。瀬名秀明『虹の天象儀』★★★は、プラネタリウム
にタイムトラベルを組み合わせた『八月の博物館』系列のリリカルな時間SF。織田作之助の登場に意表を突かれるが、いまいち機能してない。山田正紀『日曜日には鼠ラツトを殺せ』★★は、専制国家と化した日本が舞台の山田版『バトルランナー』。この長さなら視点人物を絞った方がよかった気が。鯨統一郎『CANDY』★☆は、なんとも言いようがない二人称パラレルワールド駄洒落SF。田中啓文『星の国のアリス』★☆は宇宙船が舞台のグロ系吸血鬼SFミステリ。もっと暴走するか、意外な本格ネタで落としてほしかった。
好調の徳間デュアル文庫からも税込み五百円の書き下ろし中篇シリーズ《DUAL NOVELLA》が新登場。第一弾は五冊すべてがSF系で、総合力では《400円文庫》第二弾を(価格差の百円分以上に)上回る。北野勇作『ザリガニマン』★★★☆は、ウェブ上で圧倒的人気を集めた『かめくん』の姉妹篇。ディック的に現実が崩壊していく後半は評価が分かれそうだが、文体と世界観に揺らぎはない。乾くるみ『マリオネット症候群』★★★☆は、オフビートな人格転移モノSFミステリ。フーダニットはあっという間に解決するものの、その後の人を食った(しかし論理的な)展開がこの著者らしい。ネタの転がし方は明らかにSFなので、乾くるみを読んだことがない人も楽しく読めるはず。林譲治『大赤斑追撃』★★★は木星圏が舞台の宇宙活劇。《那國》シリーズに比べるとストレートな分やや古めかしいが、ソツのない仕上がり。篠田真由美『聖杯伝説』★★★は、七〇年代アメリカの文化人類学SF、あるいは同時期の日本のSF少女マンガを彷彿とさせるノスタルジックな叙情SF。梶尾真治『かりそめエマノン』★★☆は、エマノンの双子のお兄ちゃんが主役の番外篇。敵の正体はどうかと思うが、こういう話をいま平気で書けてしまうのがこのシリーズの強みか。王道の結末では梶尾節が冴え渡る。
残る新刊を超特急で。ハルキ文庫《ヌーヴェルSF》シリーズからは、笹本祐一の新シリーズ開幕篇『ほしからきたもの。1』★★と夏緑『イマジナル・ディスク』★★が出ている。前者は異星人の侵略下にある〝もうひとつの一九六〇年代〟を舞台にした航空宇宙SF。地球の領空(?)を侵犯するUFO迎撃に飛び立つエースパイロットは十二歳の少女──というわけで、懐かしの「謎の円盤UFO」ティーンズ版の趣き(ただし、キャラよりメカ重視)。後者は宇治の京大理学研究所が殺人蝶に襲われるバイオSFホラーというか昆虫パニック小説。ワンナイトものにふさわしくスピード感は出ているが、説得力に難あり。
秋山瑞人の新シリーズ『イリヤの空、UFOの夏』第一巻(電撃文庫)★★★★は、平凡な高校生の少年が平凡じゃない転校生の少女と出会うほのぼのハードSF。少年小説としても抜群にうまく、夏休み最後の日、無人のプールに忍び込んで泳ぐ冒頭からもう完璧。今後の展開に強く期待したい。
米田淳一『エスコート・エンジェル』(ハヤカワ文庫JA)★★は、デビュー作『プリンセス・プラスティック』の前日譚。「ローマの休日」風に二二世紀日本を観光案内する趣向で、前作よりずっと読みやすくなったものの、その分、設定の無理が目立つ。
今野敏『宇宙海兵隊ギガース』(講談社ノベルス)★★は、ニュータイプ(じゃないけど)の少女が試験的に実戦配備された新型モビルスーツ(じゃないけど)プロトタイプのパイロットとして活躍する、もうひとつのガンダム。ソウヤーがスタトレのスピンオフ小説書かずに『スタープレックス』書くようなもんですか。非ガンダムおやじのオレでも部分的には意外と楽しく、これはコロンブスの卵かも。
最後に翻訳SF長篇を一冊だけ。デニス・ダンヴァーズ『エンド・オブ・デイズ』上下(川副智子訳/ハヤカワ文庫SF)★★★は、『天界を翔ける夢』の後日譚。前作より出来がよく、イーガン『順列都市』以後の仮想現実SFとして見ても、それなりに健闘している。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする