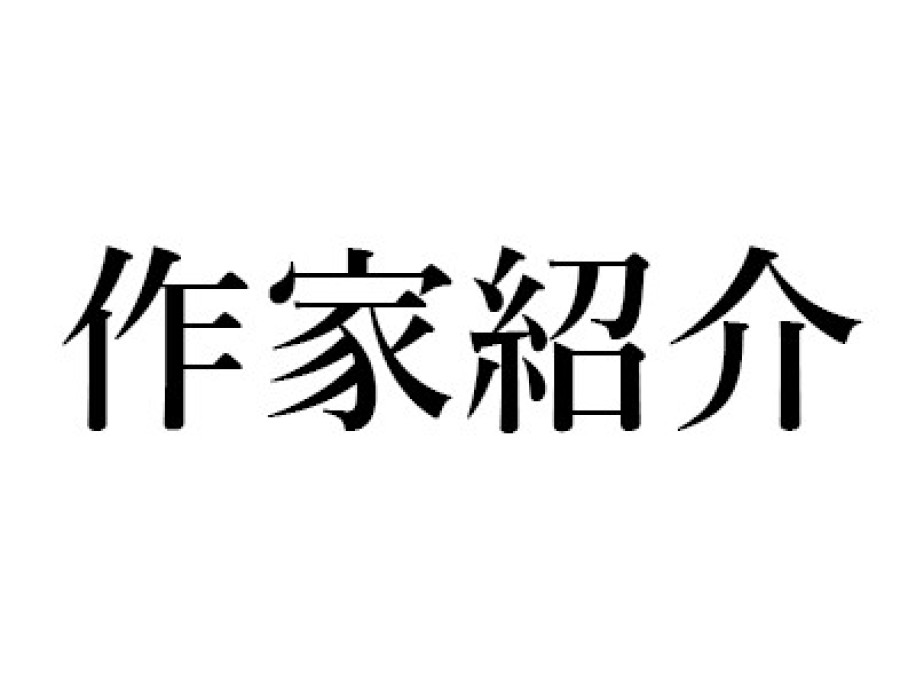書評
『徹底抗戦!文士の森』(河出書房新社)
英国の作家ゴードン・スティーヴンズが書いた『カーラのゲーム』(創元ノヴェルズ)という冒険小説があります。内戦に揺れるボスニアで愛する夫も息子も家も失ったカーラが、この戦争に知らん顔を決めこんでいる世界を相手に戦いを挑むという、女性が共感できる感動大作なのです。カーラは彼女を助けてくれたSAS(イギリス陸軍特殊空挺部隊)の隊員からこんな言葉を贈られます。
男であれ女であれ、正々堂々と戦う人は美しい。というわけで、今、文壇でもっとも美しい存在が笙野頼子なんであります。『徹底抗戦!文士の森 実録純文学闘争十四年史』は、「文学は死んだ」とか「純文学は売れないから意味がない」といった、理性もなければ愛もない発言によって純文学叩きを繰り返す有象無象の言論と、敢然と戦ってきた笙野さんの血のにじむような孤軍奮闘記なのです。
今から二〇数年前、デビューしたばかりの笙野さんに向かい、未婚の母になってその体験を書けと要求した編集者。三島賞の受賞会見で笙野さんの容貌のことをあてこする発言にどっと笑った男性記者。荒唐無稽なスキャンダルをでっち上げたブラックジャーナリズム。最近の芥川賞受賞作は売れないんだから、いっそ芥川賞を廃止すればいいのではないかと提案する新聞記事。そして、赤字の文芸誌に存在価値はない、文学は不良債権も同然だ、文学はサブカルチャーの下位にあるといった発言を対談や評論で展開している、漫画の原作者にして批評家の大塚英志氏。
笙野さんはそのいちいちに対して吠える。憤懣を隠さない。そして正面きって戦う。大塚氏を守ろうとする雑誌から幾度ボツをくらおうがめげない。そのエネルギーたるや、本書の厚さと熱さに接すれば一目瞭然でありましょう。これまでにさまざまな媒体で発表してきた(笙野さん曰く、相手が出てこないゆえにカッコ付きの)「論争」の文章をすべて収めているばかりか、ボツになって発表できなかった原稿、編集者からの直しや指示があったゲラ、今は休刊になっている「噂の眞相」編集長からの実印入りの謝罪文、論争関連対談、笙野さんが選考委員を務めている文学賞の選評、大量の書き下ろし原稿まで収録。真摯ではあっても、エンターテインする心意気を忘れない芸のある語り(さすが!)もあいまって、実に読み応えのある面白い論争文集になっているのです。
主な標的たる大塚氏をはじめ、ここでやり玉に挙げられている男性もの書き諸氏がほとんど反論らしい反論をしていないため、読者は笙野さんサイドから提出された「論争」経緯しか知ることができないので、その勝敗は判断がつかないとはいえ、名誉は圧倒的に笙野さんのものだと言えます。なぜなら、独り敢然と戦ったのだから。そして、ごくごく個人的な感想を述べれば、勝利だって笙野さんのものだと、わたしは思うのです。それは、男性もの書き諸氏が反論しないで逃げ回ってばかりいたからではありません。この本を読めばわかりますが、笙野さんには文学というジャンルに向ける大きな愛があるからなのです。やっぱり、愛がなくちゃね(©矢野顕子)。愛のない発言になんの建設性がありましょうか。
これは、日本文学史に残る「論争」の顛末を記して資料的な価値の高い一冊です。でも、それだけではありません。ソシュールやデリダなど西洋哲学者の影響の下、堅苦しくて一面的な批評を繰り返してきたこれまでの男性批評家に対し、たとえば神話や土俗、フェミニズム、SFといった世界へと至るたくさんのコードをごった煮的に用いて読みこんでいかなければ、二一世紀の文学は理解できないのではないかという、新しい批評のありようを提示している点において、とても刺激的な批評集でもあるのです。
血がしたたっているかのような跡を記すミルキィ・イソベ氏の装幀は、まさにこの本の本質を表しているように思います。そう、これは笙野頼子の血判書なのです。ならば、わたしも押してし止まん。小説愛という血判を。
【この書評が収録されている書籍】
名誉は戦いに臨む者にのみ与えられる。(中略)かりに敗北を喫したとしても、それは敢然と戦ったすえの敗北だ。
男であれ女であれ、正々堂々と戦う人は美しい。というわけで、今、文壇でもっとも美しい存在が笙野頼子なんであります。『徹底抗戦!文士の森 実録純文学闘争十四年史』は、「文学は死んだ」とか「純文学は売れないから意味がない」といった、理性もなければ愛もない発言によって純文学叩きを繰り返す有象無象の言論と、敢然と戦ってきた笙野さんの血のにじむような孤軍奮闘記なのです。
今から二〇数年前、デビューしたばかりの笙野さんに向かい、未婚の母になってその体験を書けと要求した編集者。三島賞の受賞会見で笙野さんの容貌のことをあてこする発言にどっと笑った男性記者。荒唐無稽なスキャンダルをでっち上げたブラックジャーナリズム。最近の芥川賞受賞作は売れないんだから、いっそ芥川賞を廃止すればいいのではないかと提案する新聞記事。そして、赤字の文芸誌に存在価値はない、文学は不良債権も同然だ、文学はサブカルチャーの下位にあるといった発言を対談や評論で展開している、漫画の原作者にして批評家の大塚英志氏。
笙野さんはそのいちいちに対して吠える。憤懣を隠さない。そして正面きって戦う。大塚氏を守ろうとする雑誌から幾度ボツをくらおうがめげない。そのエネルギーたるや、本書の厚さと熱さに接すれば一目瞭然でありましょう。これまでにさまざまな媒体で発表してきた(笙野さん曰く、相手が出てこないゆえにカッコ付きの)「論争」の文章をすべて収めているばかりか、ボツになって発表できなかった原稿、編集者からの直しや指示があったゲラ、今は休刊になっている「噂の眞相」編集長からの実印入りの謝罪文、論争関連対談、笙野さんが選考委員を務めている文学賞の選評、大量の書き下ろし原稿まで収録。真摯ではあっても、エンターテインする心意気を忘れない芸のある語り(さすが!)もあいまって、実に読み応えのある面白い論争文集になっているのです。
主な標的たる大塚氏をはじめ、ここでやり玉に挙げられている男性もの書き諸氏がほとんど反論らしい反論をしていないため、読者は笙野さんサイドから提出された「論争」経緯しか知ることができないので、その勝敗は判断がつかないとはいえ、名誉は圧倒的に笙野さんのものだと言えます。なぜなら、独り敢然と戦ったのだから。そして、ごくごく個人的な感想を述べれば、勝利だって笙野さんのものだと、わたしは思うのです。それは、男性もの書き諸氏が反論しないで逃げ回ってばかりいたからではありません。この本を読めばわかりますが、笙野さんには文学というジャンルに向ける大きな愛があるからなのです。やっぱり、愛がなくちゃね(©矢野顕子)。愛のない発言になんの建設性がありましょうか。
これは、日本文学史に残る「論争」の顛末を記して資料的な価値の高い一冊です。でも、それだけではありません。ソシュールやデリダなど西洋哲学者の影響の下、堅苦しくて一面的な批評を繰り返してきたこれまでの男性批評家に対し、たとえば神話や土俗、フェミニズム、SFといった世界へと至るたくさんのコードをごった煮的に用いて読みこんでいかなければ、二一世紀の文学は理解できないのではないかという、新しい批評のありようを提示している点において、とても刺激的な批評集でもあるのです。
血がしたたっているかのような跡を記すミルキィ・イソベ氏の装幀は、まさにこの本の本質を表しているように思います。そう、これは笙野頼子の血判書なのです。ならば、わたしも押してし止まん。小説愛という血判を。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
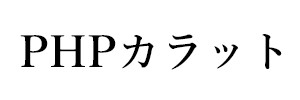
PHPカラット(終刊) 2005年11月号
ALL REVIEWSをフォローする