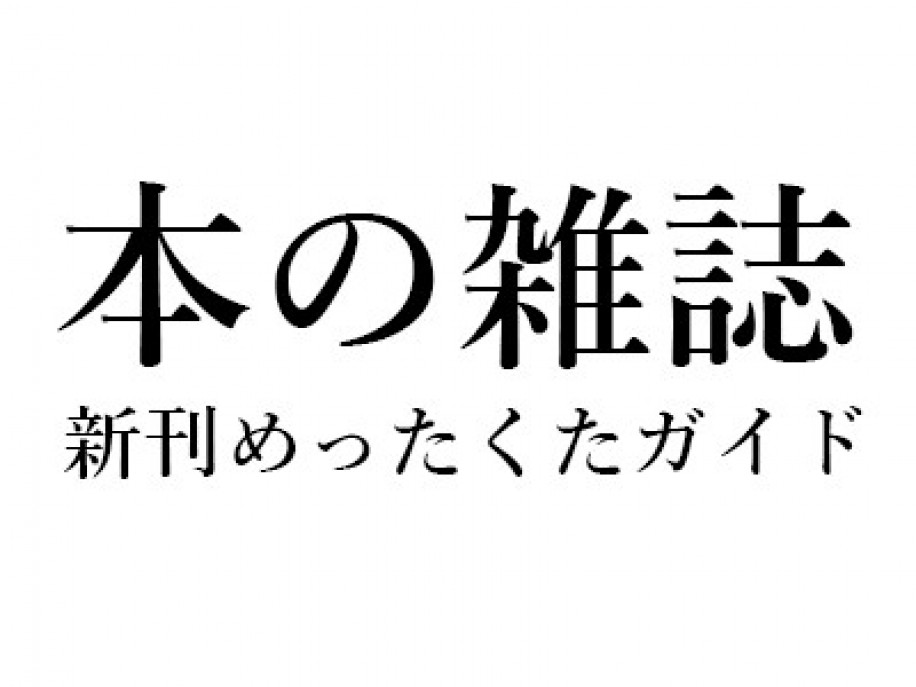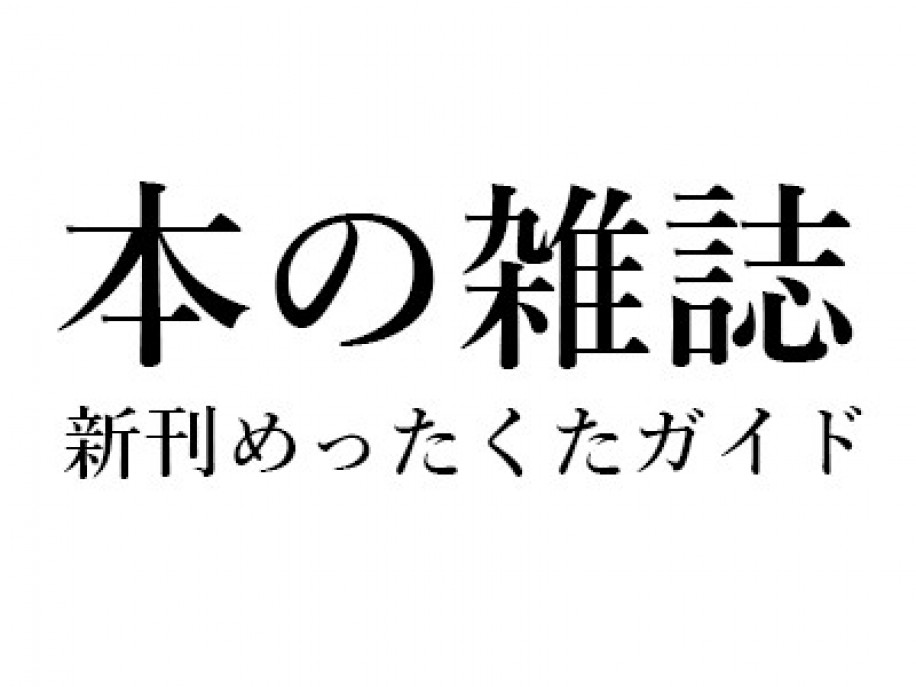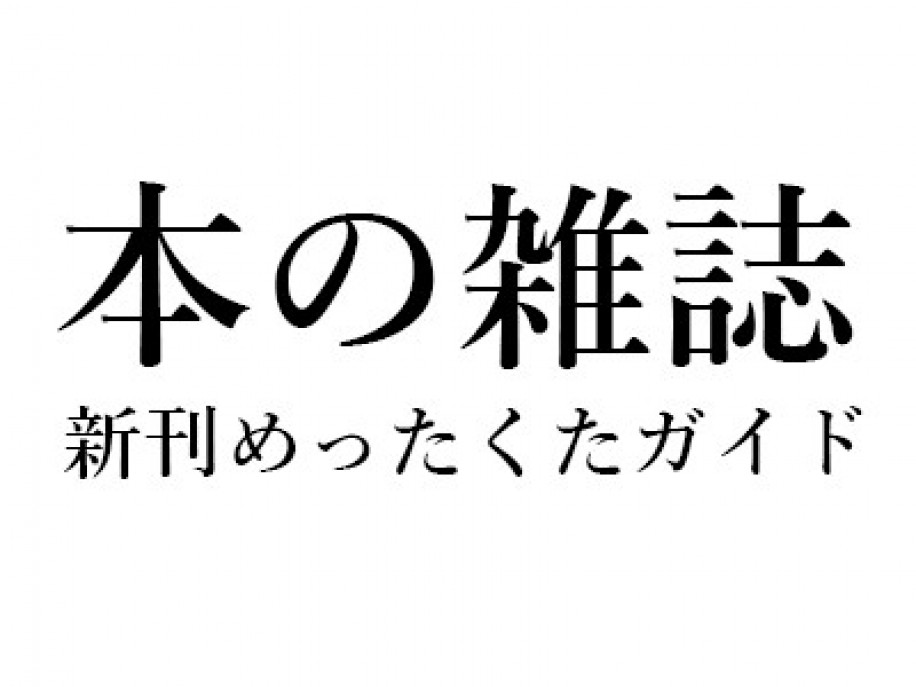文芸時評
大森望「新刊めったくたガイド」本の雑誌2001年5月号『銀河帝国の弘法も筆の誤り』他
駄洒落SFの極北、田中啓文『銀河帝国の弘法も筆の誤り』
昭和の御代から無秩序に堆積する本の山を整理しはじめたら、これがもう風間賢二邸の雪かき並みのシジフォス神話で、吐き気さえ覚えた。捨てても捨てても減らないのはなぜ。おかげで今月は新刊が読めなくて──という言い訳はさておき、その地層の最奥から十二年前の写真が出土した。生まれたばかりの仔猫四匹に母猫が授乳するの図。そのうち一匹は山岸真に、もう一匹はSF研の後輩に貰われていったが、残る二匹はついに引き取り手が見つからず、それからどうしたかというと今もそのへんで勝手に暮らしている。仔猫の養子縁組はことほどさように難しい。というわけで、待望久しい森岡浩之の『星界の戦旗Ⅲ』(ハヤカワ文庫JA)★★★☆は、ディアーホがセルクルカに産ませた仔猫たちの貰い手を見つけるべく、われらがジントが奮闘する話である。さすがにそれだけじゃ《星界》シリーズにならないので、新艦隊創設とか軍事演習とかの話も出てきますが、基本的には忙中閑ありというか、楽しい里帰り休暇篇。二年以上待たせてこんな話を書く勇気は拍手と敬服に値するが(実際、中身は面白い)、しかしもうちょっと執筆ペースを上げてもバチは当たらないと思う。
同じ宇宙戦争物でも怒濤の大団円に雪崩れ込むのがオースン・スコット・カードの四部作完結篇、『エンダーの子どもたち』上下(田中一江訳/ハヤカワ文庫SF)★★★☆。こないだ『没落』文庫版の解説を書くのに《ハイペリオン》四部作を読み直してみて思ったんですが、これと《エンダー》四部作って、表裏一体みたいな関係かも。「全宇宙ネットワークに宿る知性を抹殺するために即時通信システムを遮断する」ってモチーフとか、共感と自己犠牲を核に据えるところとか、共通点が少なくない。ただし、物語を語る道具として人物を配置するシモンズに対して、カードの場合は〝人間を描く〟情熱が物語を破壊して暴走する。せっかくピーターを復活させたのに、エンダーに対抗する役割を与えず、エンダーの問題を描くための器として使うのも、人間の理想像が抱える問題にしか興味がないせいか。そこを徹底的に突き詰めて独自の世界を構築するのがカード流だが、今回は、三千年に及ぶ長大な物語に幕を引くのが大目標なので、前二作ほどには作家性が爆発しない。バランスの崩れ方が異様な迫力を生み、カードにしか書けない傑作となった『ゼノサイド』の続巻としてはおとなしすぎ。前作の中国文化に対し今回は日本文化が(部分的に)採用されてるのも難点で、いきなりツツミ・ヤスジロウ(堤家の子孫)に登場されてもなあ……。とはいえ、カードの作家性とジャンルSFの器が正面から激突するこの四部作は、《ハイペリオン》四部作とは別の意味で重要な現代SFだと思う。
田中啓文の『銀河帝国の弘法も筆の誤り』(ハヤカワ文庫JA)★★★☆も、同じく宇宙戦争ものの連作──というより、地口と楽屋落ち満載の色物にしか見えないつくりで、まあ確かに駄洒落SFなんだけど、「脳光速」と「銀河を駆ける呪詛」の二篇は、超弩級のアイデアを惜しげもなく使い捨てにした歴史的傑作として高く評価したい。パースペクティヴが一気に広がる瞬間の快感がSFのセンス・オブ・ワンダーだとすれば、田中啓文はワイドスクリーン・バロックの壮大なヴィジョンをたった一個の駄洒落で瞬間的に葬り去る。その圧倒的脱力感は、いわば負のセンス・オブ・ワンダーか。その意味では、裏イーガンとも呼ぶべき、世界に類例を見ないSF作家かもしれない。もっとも、この著者の場合、狙ってそうなったわけではなく、たまたまそこに落着しただけだろう。ほら、昔からよう言うやないですか、田中はボタ餅って。
ごほん。とひとつ咳払いしただけで竹本健治『連星ルギイの胆汁』(e‐NOVELS)★★を紹介するのも失礼な話だが、異常さの程度では似たようなものか。職業作家のSF長篇がウェブ上だけで出版された珍しいケースで、中身のほうもかなりレア。『腐蝕』の後日譚だが、著者みずから「多分、今まで発表した僕の作品のなかで、最も変な話だろう」というだけあって、小説かどうかも疑わしい。『閉じ箱』収録の初期短篇群に通底する世界が存分に描かれる、仮面劇のような哲学問答寓話。その意味ではもっとも竹本健治らしいSFだし、竹本版『百億の昼と千億の夜』的な趣きもある。重度竹本マニア向けの怪作。
その竹本健治が〝我が国の幻想文学における一大収穫〟と絶賛する東海洋士の第一長篇『刻丫卵(こくあらん)』(講談社ノベルス)★★★★は、卵の形をした奇妙なからくり時計をめぐる異色作。SFファンなら『果しなき流れの果に』の砂時計を思い出すところだが、こちらは島原の乱をめぐる伝奇小説的な逸話が挿入されて、虚実入り乱れたウロボロス的迷宮世界が構築されてゆく。今年の収穫に数えたい巧緻な秀作。
しかし、個人的に〝我が国の幻想文学における一大収穫〟と呼びたいのは、津原泰水の『ペニス』(双葉社)★★★★☆。こんな小説が《小説推理》に三年(中断期間含む)も連載されていたこと自体が奇蹟です。語り手は井ノ頭公園の管理事務所に勤める初老のインポテンツ男。その彼がなぜか少年の冷凍死体と同居して、隣のサイコさんに振り回される話と要約すれば異常心理サスペンスだし、現代の不能性をめぐるポルノとしても読めるが、濃密な文章はむしろ全体小説的なスケールを感じさせる。精緻な細部と重層的な隠喩が現実を反転させ、見慣れた日常が巨大な幻想空間に変貌する。技のデパートさながらに繰り出される小説技巧は圧倒的で、ページを繰る手が止まらない。純文学の方法論とジャンル小説の娯楽性が完璧に融合した希有な傑作。
今月最後の一冊は、梶尾真治、篠田真由美、二階堂黎人、大塚英志など六人の書き下ろしSFアンソロジー『NOVEL21 少女の空間』(徳間デュアル文庫)★★★。小林泰三「独裁者の掟」は、TVアニメ「今、ここにいる僕」のハードSF版みたいな設定で、積極的な反時代性が新鮮だが、あとの五篇はノスタルジックな雰囲気で手堅くまとめた感じ。残念ながら、前巻『少年の時間』より印象は薄い。
【この文芸時評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする