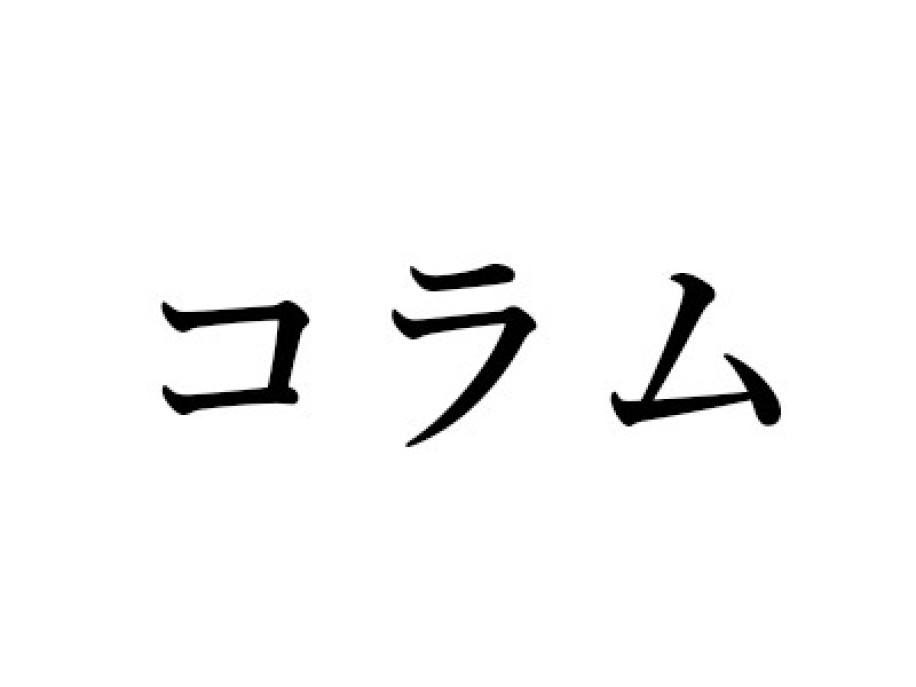読書日記
安生正『東京クライシス 』(祥伝社)、嵐山光三郎『ゆうゆうヨシ子さん』(中央公論新社)、萩野正昭『これからの本の話をしよう』(晶文社)
◆『東京クライシス 内閣府企画官・文月祐美 』安生正・著(祥伝社/税別1700円)
ときは真夏、関東の雷と竜巻が変電所を襲い、豪雨は荒川を決壊させる寸前。大規模停電が起き、鉄道はマヒ、帰宅困難者が街にあふれ出し、都心はパニックに!
安生正『東京クライシス』は、未曽有の災害に見舞われた東京の混乱を、きわめてリアルに描いた。グズな政府の対応が危機管理能力のなさを暴露……という展開は、小説であることを忘れる。そんな中で孤軍奮闘するのが内閣府企画官・文月祐美(ふづきゆみ)。災害対応の専門家として、毅然と国難を乗りこえる。
国民に目を向けず、「政治そのものが目的になっている」内閣に対し、現場で自ら判断し対処する人たちがいる。クビを覚悟で行動するのは仕事への誇りがあるから。無責任の連鎖の前で、文月と彼らが持ち場を死守する姿は感動的だ。
東日本大震災で活躍した元内閣府の役人が、助っ人で呼び寄せられる。彼は文月に「最後まで逃げない勇気」を求めるのだ。災害と官邸を相手に闘い続けるヒロインに、最後の1ページまで目が離せない。
◆『ゆうゆうヨシ子さん ローボ百歳の日々』嵐山光三郎・著(中央公論新社/税別1600円)
「サンデー俳句王」宗匠でおなじみ嵐山光三郎の『ゆうゆうヨシ子さん』。主役は今年102歳になる母。60を過ぎて俳句を詠み出した。75歳の「不良老年(ムスコ)」と「母(ローボ)」の俳句を通じた日々が綴(つづ)られる。
俳句教室へ通い、句誌に参加し、84歳で第一句集出版。句誌主宰者は「努力家で几帳面な性格ですが、一切角張った感じがないのは人徳」と評した。休まず詠み続けた。「母の日の星またたきて闇に消ゆ」は初期の句。息子は「胸にずきんと矢を射られた」気がした。
先に逝った父・ノブちゃんも句作が趣味。俳句一家だ。在住する東京・国立の町、幼なじみの人々、少年時代など、俳句まじりで回想される話も本書の読みどころ。「春風に襁褓の波の白さかな」はヨシ子さんのおむつを詠んだ句。おおらかでユーモラスなのは家風であろうか。足腰が弱り、外出できなくなるなど、老いは進行する。それでも「紫陽花の花の重さを活けりけり」と、俳句がヨシ子さんを生かしている。
◆『これからの本の話をしよう』萩野正昭・著(晶文社/税別1700円)
本離れとデジタル化が加速するいま、本の原点を見直そうとするのが萩野正昭『これからの本の話をしよう』。著者は書籍の電子化を手がけたボイジャー・ジャパンの創業者。本は優れたメディアという基本を踏まえ、「本の輝かしい歴史」などという美談に溺れず、デジタル時代の「本」の姿を提示。米国ボイジャー創業者のこと、ブックデザイナー鈴木一誌にインタビューするなど、多角的な視点が魅力的だ。第4章「本とは、ほんとうにただものではない」のタイトルが力強く未来を指し示す。
◆『赤い館の秘密』A・A・ミルン/著(創元推理文庫/税別940円)
ミステリー史上、極めつきの名作の一つが『赤い館の秘密』。A・A・ミルンは『クマのプーさん』でおなじみ。100年近く前の長編探偵小説が、山田順子の新訳で甦(よみがえ)った。赤い館に住む名士マークを15年ぶりに兄のロバートが訪ねる。館内に一発の銃声。ロバートの死体が転がっていた。事件後に姿を消したマークに疑いがかかるが、いったい真犯人は誰? 館に居合わせたギリンガムが、友人べヴァリーをワトスン役に謎を解く。殺人が起こるのにどこかほのぼのしているのは「プーさん」の著者らしい。
◆『進化する形』倉谷滋・著(講談社現代新書/税別1000円)
倉谷滋『進化する形』の帯に「なぜ世界にはこれほどさまざまな生物がいるのだろう」とある。確かに昆虫や鳥、魚、脊椎(せきつい)動物と、皆見事に違う形をしている。著者は専門の「進化形態学」を基礎に、解剖学や発生学の話題も盛り込み「生物の形が変わるとは、どういうことか」を考察する。「原型論」と「反復説」、「複雑系」や「ゲノム」など専門知識がちりばめられるが、多数の図版が理解を助ける。カブトムシとシーラカンスが生物学的にどうつながるか。ダーウィンを追い抜く快感あり。
ときは真夏、関東の雷と竜巻が変電所を襲い、豪雨は荒川を決壊させる寸前。大規模停電が起き、鉄道はマヒ、帰宅困難者が街にあふれ出し、都心はパニックに!
安生正『東京クライシス』は、未曽有の災害に見舞われた東京の混乱を、きわめてリアルに描いた。グズな政府の対応が危機管理能力のなさを暴露……という展開は、小説であることを忘れる。そんな中で孤軍奮闘するのが内閣府企画官・文月祐美(ふづきゆみ)。災害対応の専門家として、毅然と国難を乗りこえる。
国民に目を向けず、「政治そのものが目的になっている」内閣に対し、現場で自ら判断し対処する人たちがいる。クビを覚悟で行動するのは仕事への誇りがあるから。無責任の連鎖の前で、文月と彼らが持ち場を死守する姿は感動的だ。
東日本大震災で活躍した元内閣府の役人が、助っ人で呼び寄せられる。彼は文月に「最後まで逃げない勇気」を求めるのだ。災害と官邸を相手に闘い続けるヒロインに、最後の1ページまで目が離せない。
◆『ゆうゆうヨシ子さん ローボ百歳の日々』嵐山光三郎・著(中央公論新社/税別1600円)
「サンデー俳句王」宗匠でおなじみ嵐山光三郎の『ゆうゆうヨシ子さん』。主役は今年102歳になる母。60を過ぎて俳句を詠み出した。75歳の「不良老年(ムスコ)」と「母(ローボ)」の俳句を通じた日々が綴(つづ)られる。
俳句教室へ通い、句誌に参加し、84歳で第一句集出版。句誌主宰者は「努力家で几帳面な性格ですが、一切角張った感じがないのは人徳」と評した。休まず詠み続けた。「母の日の星またたきて闇に消ゆ」は初期の句。息子は「胸にずきんと矢を射られた」気がした。
先に逝った父・ノブちゃんも句作が趣味。俳句一家だ。在住する東京・国立の町、幼なじみの人々、少年時代など、俳句まじりで回想される話も本書の読みどころ。「春風に襁褓の波の白さかな」はヨシ子さんのおむつを詠んだ句。おおらかでユーモラスなのは家風であろうか。足腰が弱り、外出できなくなるなど、老いは進行する。それでも「紫陽花の花の重さを活けりけり」と、俳句がヨシ子さんを生かしている。
◆『これからの本の話をしよう』萩野正昭・著(晶文社/税別1700円)
本離れとデジタル化が加速するいま、本の原点を見直そうとするのが萩野正昭『これからの本の話をしよう』。著者は書籍の電子化を手がけたボイジャー・ジャパンの創業者。本は優れたメディアという基本を踏まえ、「本の輝かしい歴史」などという美談に溺れず、デジタル時代の「本」の姿を提示。米国ボイジャー創業者のこと、ブックデザイナー鈴木一誌にインタビューするなど、多角的な視点が魅力的だ。第4章「本とは、ほんとうにただものではない」のタイトルが力強く未来を指し示す。
◆『赤い館の秘密』A・A・ミルン/著(創元推理文庫/税別940円)
ミステリー史上、極めつきの名作の一つが『赤い館の秘密』。A・A・ミルンは『クマのプーさん』でおなじみ。100年近く前の長編探偵小説が、山田順子の新訳で甦(よみがえ)った。赤い館に住む名士マークを15年ぶりに兄のロバートが訪ねる。館内に一発の銃声。ロバートの死体が転がっていた。事件後に姿を消したマークに疑いがかかるが、いったい真犯人は誰? 館に居合わせたギリンガムが、友人べヴァリーをワトスン役に謎を解く。殺人が起こるのにどこかほのぼのしているのは「プーさん」の著者らしい。
◆『進化する形』倉谷滋・著(講談社現代新書/税別1000円)
倉谷滋『進化する形』の帯に「なぜ世界にはこれほどさまざまな生物がいるのだろう」とある。確かに昆虫や鳥、魚、脊椎(せきつい)動物と、皆見事に違う形をしている。著者は専門の「進化形態学」を基礎に、解剖学や発生学の話題も盛り込み「生物の形が変わるとは、どういうことか」を考察する。「原型論」と「反復説」、「複雑系」や「ゲノム」など専門知識がちりばめられるが、多数の図版が理解を助ける。カブトムシとシーラカンスが生物学的にどうつながるか。ダーウィンを追い抜く快感あり。
ALL REVIEWSをフォローする