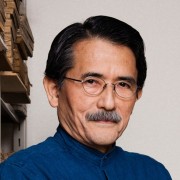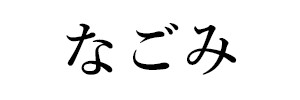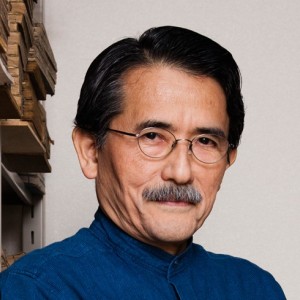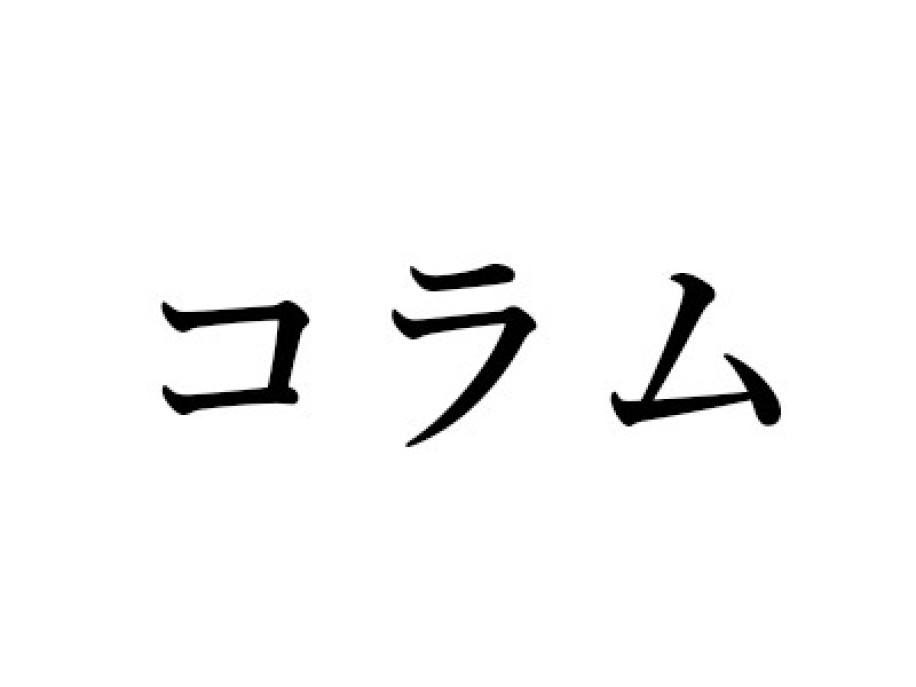書評
『文人悪食』(新潮社)
実に以て面白し
このごろ読んだ書物のなかで、もっとも面白く、含蓄に富んだものはなんだと聞かれたら、私は躊躇なくこう答えるであろう。「それは嵐山光三郎の『文人悪食』であります」
と。この題名からは、その内容が必ずしも十全に把握できない嫌いがあるが、決して、いわゆる「悪食」について論じたものではない。この「悪食」という含意は、自跋に言うところを借りれば「文士は五官で感じた世の仕組みを文字ですくいとる達人だから、舌も喉の回路も常人とは違う」ということである。いわゆる小市民的美味嗜好とか、露悪的悪食開陳の類いとは毫も関係のない真面目な労著である。だから、この「悪食」は、ときに本当に悪食であることもあるが、多くは、美食であり、強迫観念であり、異常な執着であり、または無頓着であり、という塩梅で、その食物に対する異常な対峙の仕方のなかに、非凡な(ということはつまり世間的に言えば変人奇人なということだが)作家たちの、非凡なる生き様が見えてくるということである。
私が、この本を読みながら、並々ならぬ敬意を覚えたのは、著者の、あたかも学術書を書くにも等しい営々孜々たる調査徹底のありようである。前述の自跋に、その著述のために七百冊の参考文献を渉猟したということが述べてあるが、さもありなんと思われる。たとえば、有島武郎の章を書くについて、「武郎がなにを好んで食べたかと、著作集をあらいざらい調べてもサンドイッチと子の弁当以外ほとんど記録がない」と、こうさらりと書いているけれど、これは、苟も文献の学を齧った一研究者として言わせていただくならば、ただこの一行を書くために、どれほどの労力と時間を必要としたか、まさに頭の下る思いがするというものである。本書は、そのどこをとっても、この種の、綿密周到を極めた研究の上にかかれていること、一読して明らかで、じっさい、草稿の段階ではこの倍も量があったそうであるが、さもありなんと納得される。願わくは、その草稿の全量をば、一個の学術書として読みたいものだとさえ思われる。といって、そんな学術的な本ではさぞ読みにくいのではないかと邪推する人があるかもしれないが、それは大間違いである。平易明快なる文章の冴えは、著者の温雅な人柄を反映したものかとも思われ、誰が読んでも、分りにくいとか、退屈だとかいうことは全くない。ああ、面白いなあ、へえ、あの文豪はそんな変人奇人だったのか、と驚いたり感心したりしているうちにいつしか読み終わってしまうであろう。しかし、その一方で、これがまた驚くべき作家論になっていることにも、はっと気付かされる。たとえば、俗には清貧の人として崇拝されている宮沢賢治が、実は、大金持ちの坊ちゃん育ちで、肉も食べたし、高級料亭にも出入りしたし、酒も煙草もやったということをこういう本でよく心得てから「雨ニモマケズ風ニモマケズ」と唱えたほうが宜しいということである。漱石に始まって、三島由紀夫に終わる三十七人の文士の「悪食」ぶり、まずは篤とお読みあれ。面白きこと請け合い。
ALL REVIEWSをフォローする