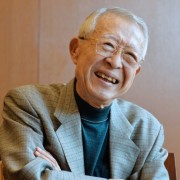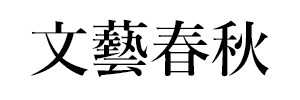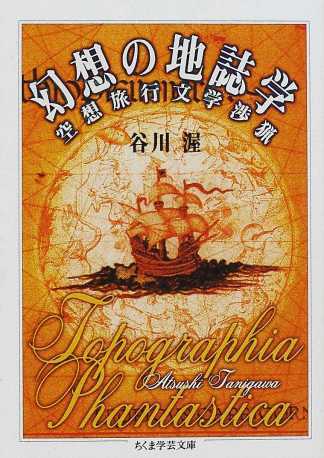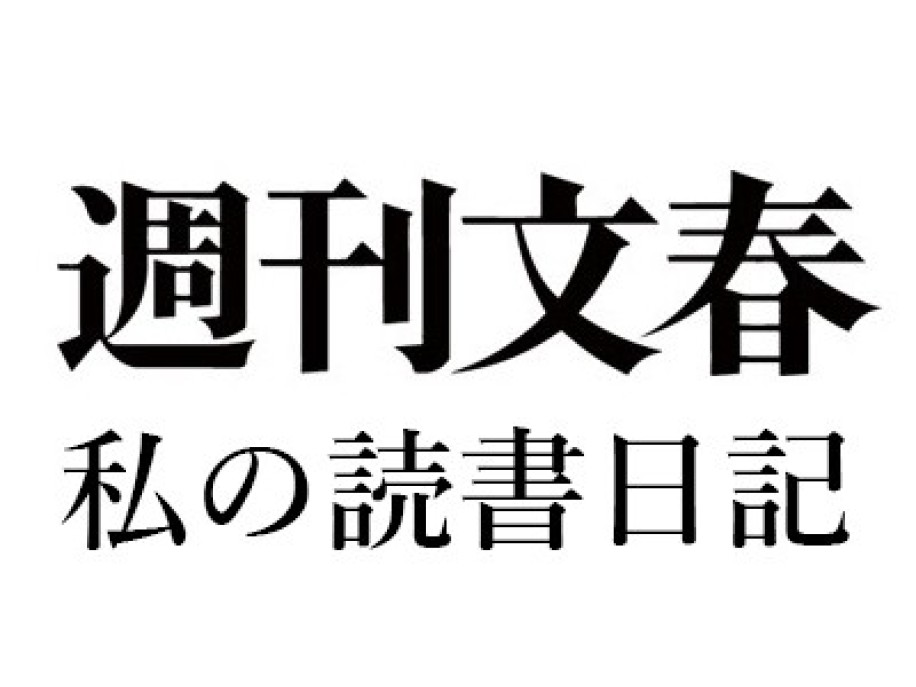読書日記
尾崎 幸男『地図のファンタジア』(文藝春秋)|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
山崎 これは、地図をつくる実際家であり、地理学者でもある筆者が、いわば業余の愉しみとして地図をめぐるいろいろな知識を披露した随筆集です。
この人は、たいへん好奇心の旺盛な、また雑学的知識の豊富な人で、いろいろなエピソードを読むだけでも、結構愉しめます。それと同時に、この本を書くにあたっての筆者の心理的動機を推察すると、地図というものがあまりにも理解されていないことに対する苛立ちではなかろうかという気がします。
たとえば友人を自宅へ招くときに、たばこの箱の裏などに簡単な地図を描いて渡す習慣があります。どうも地図などというものは簡単に描けるものだと思いがちである。ましてや一枚の地図を描くのにいくらお金がかかるであろうかなどということは、毛頭考えない。
そこで、この筆者は博学を駆使して、地図をつくるのにいかに金がかかり、人知と人力を消耗するものであるか、ということを書きたかったのであろうと思います。
こういう自然科学者が、文学的なエピソードを書くと、寺田寅彦という偉大な例外を除くと、概してあまりおもしろくならないのですけれども、この筆者の場合には、まずまずの成績をおさめていると思います。
たとえばスティーヴンソンの有名な『宝島』という小説を取りあげて、もしフリント船長が、いまの標準であの宝島の地図を書いたとしたら、どのくらいの日数と、お金がかかるかを、物好きにも計算してみせてくれます。それによると、ほぼ一億二千五百五十万円かかるそうです。
また『紅はこべ』という小説を取りあげて、当時のパリの全市地図とドーヴァー海峡の地図二枚を、もし現在の経費の見積りでつくれば合わせて十九億五千万円かかる、というような計算も出てきます。
このあたりを読みますと、徒労の愉しみというか、無為の冒険というか、そういった生活の愉しみ方の一つの模範があるような気がします。何か一つヘンなものに興味をもち、それについて一所懸命凝ってみるということは、これから暇がふえる現代社会に一つの生活の指針になるのではなかろうか。
また、現在の地図をつくる上でのいろんな苦心、およびそれにまつわる逸話もおもしろい。たとえば、地図上の各国を別々の色で表現するとします。海は陸地と違った色で描くとして、全体で何色(なんしょく)必要であるかというと、最低限度四色は必要であって、四色以上必要でない、ということが、経験的に古くから知られていた。これは一九七六年にアメリカのアッペルとハーケンという数学者が、大型のコンピューターを使って初めて証明したというようなこともわかります。
いずれにせよ、われわれが日頃見慣れている地図の裏にいろいろな物語があり、人類の歴史や未来があるということがよくわかりました。
丸谷 ぼくも、とてもおもしろがってこの本を読んだんです。第一に、文章がわかり易くて、明晰ですよね。第二に、話術がある。素人には親しみにくい事柄について非常にうまく案内してくれまして、思わず関心をもってしまう。この筆者はたいへんな筆力の持ち主だと感心しました。
しかし、文章が上手で話術が巧みであるあまりに、自分の才能に溺れすぎている傾向があると思うんです。
たとえば「矛盾」のことを論じた部分で、
〈たとえば、たとえ魔法の鏡に向かってでも「鏡よ、鏡よ。世界で誰が一番美しいか」などと、最上級を使った質問を絶対にしなければ、白雪姫の悲劇と矛盾も避けられたわけである〉
ここまではいい。その次に、
〈ただし、その場合はグリムの一番美しいお伽話の一つが失われるという矛盾(?)が新しく生じるが〉
といっている。「ただし」以下は要らないんですね。この思いつきに、すっかり自分で喜んでしまって、余計なことまで書いてしまっている。
本当に論理的な文章を書くためには、比喩的な発想はある程度のところで止めなくちゃならない。そうしないと、きりがなくなって具合が悪いということを、この筆者はあまりわかっていないらしい。
言葉というのは、所詮道具だという面があるわけで、言葉の自己運動をさせてしまうと、論理はおかしくなり、余計なところまで話を運んでしまうんです。
さらに、『宝島』の船長がもっていた地図を、どういうふうにして測ったかという場合に、測るという概念を非常に自然科学的な、厳密な意味で使っている。
ところが、「クレオパトラの鼻が一センチ低かったら世界の歴史は変ったろう」という有名な話を引いて、
〈仮に実際に低くなくても、彼女のお相手であったシーザーが低いと誤測したら(つまりシーザーがクレオパトラをお気に召さなかったら)〉
といっている。ここでの「測る」という言葉は、非常に比喩的ないい回しにすぎない。『宝島』の地図の測り方と、クレォパトラの鼻の高さの測り方と、まったく別の概念になっているわけですね。つまり、「測る」という言葉のおもしろさに溺れているんだと思う。
木村 近世のスペイン、ポルトガルにとって、新大陸の地図が非常に大事だった。地図をもっているということが、スペイン、ポルトガルの経済的な繁栄につながっていたということですね。また、地図は軍事的にも重要なもので、ヒマラヤの登山隊が航空写真を分けてくれ、と現地の国境守備隊に頼んだら、「そんなことしたら死刑になる」と断わられた話がありますね。たしかに航空写真というのは非常に大事なもので、フランスでもこれを撮るためには軍の許可が要る。だから、地図が自由に入手できるということは、平和な日本のシンボルというべきだ、と書いてある。ともかく地図がもっている大きな意味が、ここで解き明かされていて、その点は非常に、わたしにとっても参考になったわけです。
ただ、先ほど丸谷さんもおっしゃったように、ちょっと悪乗りしている点があるんじゃないかと思うんです。
丸谷 悪乗りというのは、非常に温かい言葉ですね(笑)。
木村 「コロンブスの卵」の話が出てきますね。当時はエッグスタンドに一個ずつ半熟卵を入れてサービスされたと書いている。
〈もう少し詳細にいえば「エッグスタンドはナイフやフォークと同様、食卓の七つ道具の一つであり、ゆで卵というものはエッグスタンドに入れて、一個ずつ食卓上にサービスする」というヨーロッパ流の常識を前提とした上での話で……〉
ところが残念ながら、あの時代のヨーロッパは、普通フォークを使っていません。フォークの出現は早くて十六世紀の宮廷からですが、一般には十八、十九世紀のことで、十七世紀のルイ十四世もフォークを使わず、指で食べてました。
丸谷 なるほど、そうか。
木村 それからこのときの卵は、半熟ではなかったと思いますね。
同時代のエラスムスが書いているんですけど、卵を爪でむくのは下品である、ナイフでむかなくてはいけない。それでは、どこからむくか。一六四〇年ころのハウスドルファーというドイツ人によると、ユダヤ人は卵の尖ったほうからむく。フランス人は角度の鈍いほうからむく。ドイツ人は土手ッ腹からむく(笑)。これはよくゆでた卵の話であって、これが一般的だったはずです。
それから、当時の絵を見ると、卵は大きな深皿の上に重ねるようにして置かれている。エッグスタンドがあったとは、ちょっと思えないですね。
山崎 尻馬に乗っていえば、もうひとつ問題があります。例のツェノンのパラドックス、つまり脚の速いアキレスが亀に永久に追いつけない、という定理があります。アキレスが一歩進むあいだに、亀といえども少しは前へ進むわけですね。アキレスは亀に追いつくためには、必ずその中間点を通過しなければいけない。中間点は無限にあるからついに追い越せない、という議論なんです。
なぜ、こういう矛盾が生じるかについて、筆者はこう書いている。
〈この場合は、物体の運動はある一定の最小単位より短かい時間には分割できない、つまり不連続だと考えているわけである。もし、運動をいくらでも細かい瞬間に分割できる、つまり連続であると考えれば、矛盾はなくなる場合が多い〉
これはむしろ、ベルグソンがやったように「運動は分割できない」と考えることによって矛盾を解くのが普通であって、無限に運動が分割できるとすれば、まさにツェノンが主張したように、アキレスは亀を追い越せないことになるはずなんです。ここは、どうも論理的に不徹底なところもある。
こういう勇み足が随所にあるわけですけれども、ともかく一枚の地図を前にして、奇想縦横に走り、古今東西のエピソードをもってくる遊びの精神が、この本の見どころなんじゃないでしょうか。ですから、読者のために申しあげれば、あくまでもお遊びの本であって、これで勉強しようなどとお考えになると間違いになる(笑)。
木村 この著者は、未知の土地のことを「西も東もわからない」と書いていらっしゃる。たしかに、日本の場合には、北や南よりも西や東のほうが大事なんですね。東北地方、東南アジアなど、みんな東、西を先にいって、北、南はあとにいう。ところがヨーロッパ人は逆に、北や南を先にいうわけです。ノースウェスト航空というようにね。測量も、ここに書いてあるように、まず南北からはじまっているわけで、ヨーロッパ人にとっては南北のほうが大事なんですよ。
山崎 中国はどっちでもないんですよ。だってマージャン見てごらんなさい、東南西北(トンナンシャーペー)……(爆笑)。
木村 まあそうですが、しかし一方で、東夷西戎南蛮北狄(ほくてき)というでしょう。東西南北ですね。ところがヨーロッパ人は、まず南北なんです、フランス人も、ドイツ人も、地中海およびその南にあるアフリカに対する関心が昔から高かったからです。
山崎 それはそうだ、日本は北へ行ったって南へ行ったって、何もないもの。
木村 日本はむしろ、江戸と京大阪の東西でしょう。日本列島は本来、南北にかかっているともいえるんだけれども、北日本と南日本というふうには分けなくて、東日本と西日本に分けますね。日本にとっては、まず物の位置が東にあるか、西にあるかが大事なんで、これは、太陽はどこから出て、どこへ沈むかという農耕民の感覚でしょうね。
だから、日本および中国、それからローマは、いずれも東西文化が発達しているわけです。
山崎 ローマもそうですか。
木村 ローマもそうです。ローマは地中海を中心に、東西四八〇〇キロ、南北一八〇〇キロの、細長い東西帝国をつくりました。それが後の東ローマと西ローマとに分れる。ローマ人にとってはオリエンス(東)とオクシデンス(西)だけが大事で、これがオリエントとオクシデントという言葉になって残っているわけですね。北、南は大事じゃなかったんですよ。
ところが、ノースとか、サウスという言葉は、ゲルマン語から来たものなんですね。方向を表わす言葉は、ドイツ語もフランス語も英語も全部ゲルマン語であって、ラテン語からは何も影響を受けていない。北にいる民族にとっては、地中海および南の世界が大事であって、南北をまず考えるわけですね。西は海でしょう。東は寒くて暗いだけだから、あまり関心がなかった。
山崎 ドイツ語に「アーベント・ラント(西洋)」という言葉があるでしょう。これは東西型の発想でしょう。
木村 ええ。そこにはやはり、ローマのオリエンスとオクシデンスの影響があるのかもしれませんね。
戦後の日本では、欧米なみに北、南を先にいういい方に変えられてしまいましたね。だから、東北地方の北東部、東南アジアの南東部などといわなきゃいけない。
これはひどい文化破壊です。つまり、われわれの方位感覚と、西欧人の方位感覚とをごっちゃにしている。
われわれにとっては、東、西が大事なんです。西も東もわからない、東奔西走、東西トォーザイ、相撲の東ィ、西ィーなど、みんなそうですね。北、南とはいわないですよ。あるのは鶴屋南北くらいのものだ(笑)。
山崎 そういえば、現代中国語で、物のことを「東西(トンシー)」といいますね。おそらく地大物博(ちだいぶつはく)なるあの国において東西の物を集めてきて「物」というんでしょうね。
木村 東西感覚が発達した国は、北に対していいようのない恐怖感をもつ。
中国人が万里の長城を築いたのも、ローマ人が、ゲルマン人に対してリーメスという城塞を築いたのもそのせいですね。日本人がロシアを嫌いなのも、根本はこの理屈にならない理由からです。
山崎 なるほど、おもしろいねえ。いろんなことがわかりました。
この人は、たいへん好奇心の旺盛な、また雑学的知識の豊富な人で、いろいろなエピソードを読むだけでも、結構愉しめます。それと同時に、この本を書くにあたっての筆者の心理的動機を推察すると、地図というものがあまりにも理解されていないことに対する苛立ちではなかろうかという気がします。
たとえば友人を自宅へ招くときに、たばこの箱の裏などに簡単な地図を描いて渡す習慣があります。どうも地図などというものは簡単に描けるものだと思いがちである。ましてや一枚の地図を描くのにいくらお金がかかるであろうかなどということは、毛頭考えない。
そこで、この筆者は博学を駆使して、地図をつくるのにいかに金がかかり、人知と人力を消耗するものであるか、ということを書きたかったのであろうと思います。
こういう自然科学者が、文学的なエピソードを書くと、寺田寅彦という偉大な例外を除くと、概してあまりおもしろくならないのですけれども、この筆者の場合には、まずまずの成績をおさめていると思います。
たとえばスティーヴンソンの有名な『宝島』という小説を取りあげて、もしフリント船長が、いまの標準であの宝島の地図を書いたとしたら、どのくらいの日数と、お金がかかるかを、物好きにも計算してみせてくれます。それによると、ほぼ一億二千五百五十万円かかるそうです。
また『紅はこべ』という小説を取りあげて、当時のパリの全市地図とドーヴァー海峡の地図二枚を、もし現在の経費の見積りでつくれば合わせて十九億五千万円かかる、というような計算も出てきます。
このあたりを読みますと、徒労の愉しみというか、無為の冒険というか、そういった生活の愉しみ方の一つの模範があるような気がします。何か一つヘンなものに興味をもち、それについて一所懸命凝ってみるということは、これから暇がふえる現代社会に一つの生活の指針になるのではなかろうか。
また、現在の地図をつくる上でのいろんな苦心、およびそれにまつわる逸話もおもしろい。たとえば、地図上の各国を別々の色で表現するとします。海は陸地と違った色で描くとして、全体で何色(なんしょく)必要であるかというと、最低限度四色は必要であって、四色以上必要でない、ということが、経験的に古くから知られていた。これは一九七六年にアメリカのアッペルとハーケンという数学者が、大型のコンピューターを使って初めて証明したというようなこともわかります。
いずれにせよ、われわれが日頃見慣れている地図の裏にいろいろな物語があり、人類の歴史や未来があるということがよくわかりました。
丸谷 ぼくも、とてもおもしろがってこの本を読んだんです。第一に、文章がわかり易くて、明晰ですよね。第二に、話術がある。素人には親しみにくい事柄について非常にうまく案内してくれまして、思わず関心をもってしまう。この筆者はたいへんな筆力の持ち主だと感心しました。
しかし、文章が上手で話術が巧みであるあまりに、自分の才能に溺れすぎている傾向があると思うんです。
たとえば「矛盾」のことを論じた部分で、
〈たとえば、たとえ魔法の鏡に向かってでも「鏡よ、鏡よ。世界で誰が一番美しいか」などと、最上級を使った質問を絶対にしなければ、白雪姫の悲劇と矛盾も避けられたわけである〉
ここまではいい。その次に、
〈ただし、その場合はグリムの一番美しいお伽話の一つが失われるという矛盾(?)が新しく生じるが〉
といっている。「ただし」以下は要らないんですね。この思いつきに、すっかり自分で喜んでしまって、余計なことまで書いてしまっている。
本当に論理的な文章を書くためには、比喩的な発想はある程度のところで止めなくちゃならない。そうしないと、きりがなくなって具合が悪いということを、この筆者はあまりわかっていないらしい。
言葉というのは、所詮道具だという面があるわけで、言葉の自己運動をさせてしまうと、論理はおかしくなり、余計なところまで話を運んでしまうんです。
さらに、『宝島』の船長がもっていた地図を、どういうふうにして測ったかという場合に、測るという概念を非常に自然科学的な、厳密な意味で使っている。
ところが、「クレオパトラの鼻が一センチ低かったら世界の歴史は変ったろう」という有名な話を引いて、
〈仮に実際に低くなくても、彼女のお相手であったシーザーが低いと誤測したら(つまりシーザーがクレオパトラをお気に召さなかったら)〉
といっている。ここでの「測る」という言葉は、非常に比喩的ないい回しにすぎない。『宝島』の地図の測り方と、クレォパトラの鼻の高さの測り方と、まったく別の概念になっているわけですね。つまり、「測る」という言葉のおもしろさに溺れているんだと思う。
木村 近世のスペイン、ポルトガルにとって、新大陸の地図が非常に大事だった。地図をもっているということが、スペイン、ポルトガルの経済的な繁栄につながっていたということですね。また、地図は軍事的にも重要なもので、ヒマラヤの登山隊が航空写真を分けてくれ、と現地の国境守備隊に頼んだら、「そんなことしたら死刑になる」と断わられた話がありますね。たしかに航空写真というのは非常に大事なもので、フランスでもこれを撮るためには軍の許可が要る。だから、地図が自由に入手できるということは、平和な日本のシンボルというべきだ、と書いてある。ともかく地図がもっている大きな意味が、ここで解き明かされていて、その点は非常に、わたしにとっても参考になったわけです。
ただ、先ほど丸谷さんもおっしゃったように、ちょっと悪乗りしている点があるんじゃないかと思うんです。
丸谷 悪乗りというのは、非常に温かい言葉ですね(笑)。
木村 「コロンブスの卵」の話が出てきますね。当時はエッグスタンドに一個ずつ半熟卵を入れてサービスされたと書いている。
〈もう少し詳細にいえば「エッグスタンドはナイフやフォークと同様、食卓の七つ道具の一つであり、ゆで卵というものはエッグスタンドに入れて、一個ずつ食卓上にサービスする」というヨーロッパ流の常識を前提とした上での話で……〉
ところが残念ながら、あの時代のヨーロッパは、普通フォークを使っていません。フォークの出現は早くて十六世紀の宮廷からですが、一般には十八、十九世紀のことで、十七世紀のルイ十四世もフォークを使わず、指で食べてました。
丸谷 なるほど、そうか。
木村 それからこのときの卵は、半熟ではなかったと思いますね。
同時代のエラスムスが書いているんですけど、卵を爪でむくのは下品である、ナイフでむかなくてはいけない。それでは、どこからむくか。一六四〇年ころのハウスドルファーというドイツ人によると、ユダヤ人は卵の尖ったほうからむく。フランス人は角度の鈍いほうからむく。ドイツ人は土手ッ腹からむく(笑)。これはよくゆでた卵の話であって、これが一般的だったはずです。
それから、当時の絵を見ると、卵は大きな深皿の上に重ねるようにして置かれている。エッグスタンドがあったとは、ちょっと思えないですね。
山崎 尻馬に乗っていえば、もうひとつ問題があります。例のツェノンのパラドックス、つまり脚の速いアキレスが亀に永久に追いつけない、という定理があります。アキレスが一歩進むあいだに、亀といえども少しは前へ進むわけですね。アキレスは亀に追いつくためには、必ずその中間点を通過しなければいけない。中間点は無限にあるからついに追い越せない、という議論なんです。
なぜ、こういう矛盾が生じるかについて、筆者はこう書いている。
〈この場合は、物体の運動はある一定の最小単位より短かい時間には分割できない、つまり不連続だと考えているわけである。もし、運動をいくらでも細かい瞬間に分割できる、つまり連続であると考えれば、矛盾はなくなる場合が多い〉
これはむしろ、ベルグソンがやったように「運動は分割できない」と考えることによって矛盾を解くのが普通であって、無限に運動が分割できるとすれば、まさにツェノンが主張したように、アキレスは亀を追い越せないことになるはずなんです。ここは、どうも論理的に不徹底なところもある。
こういう勇み足が随所にあるわけですけれども、ともかく一枚の地図を前にして、奇想縦横に走り、古今東西のエピソードをもってくる遊びの精神が、この本の見どころなんじゃないでしょうか。ですから、読者のために申しあげれば、あくまでもお遊びの本であって、これで勉強しようなどとお考えになると間違いになる(笑)。
木村 この著者は、未知の土地のことを「西も東もわからない」と書いていらっしゃる。たしかに、日本の場合には、北や南よりも西や東のほうが大事なんですね。東北地方、東南アジアなど、みんな東、西を先にいって、北、南はあとにいう。ところがヨーロッパ人は逆に、北や南を先にいうわけです。ノースウェスト航空というようにね。測量も、ここに書いてあるように、まず南北からはじまっているわけで、ヨーロッパ人にとっては南北のほうが大事なんですよ。
山崎 中国はどっちでもないんですよ。だってマージャン見てごらんなさい、東南西北(トンナンシャーペー)……(爆笑)。
木村 まあそうですが、しかし一方で、東夷西戎南蛮北狄(ほくてき)というでしょう。東西南北ですね。ところがヨーロッパ人は、まず南北なんです、フランス人も、ドイツ人も、地中海およびその南にあるアフリカに対する関心が昔から高かったからです。
山崎 それはそうだ、日本は北へ行ったって南へ行ったって、何もないもの。
木村 日本はむしろ、江戸と京大阪の東西でしょう。日本列島は本来、南北にかかっているともいえるんだけれども、北日本と南日本というふうには分けなくて、東日本と西日本に分けますね。日本にとっては、まず物の位置が東にあるか、西にあるかが大事なんで、これは、太陽はどこから出て、どこへ沈むかという農耕民の感覚でしょうね。
だから、日本および中国、それからローマは、いずれも東西文化が発達しているわけです。
山崎 ローマもそうですか。
木村 ローマもそうです。ローマは地中海を中心に、東西四八〇〇キロ、南北一八〇〇キロの、細長い東西帝国をつくりました。それが後の東ローマと西ローマとに分れる。ローマ人にとってはオリエンス(東)とオクシデンス(西)だけが大事で、これがオリエントとオクシデントという言葉になって残っているわけですね。北、南は大事じゃなかったんですよ。
ところが、ノースとか、サウスという言葉は、ゲルマン語から来たものなんですね。方向を表わす言葉は、ドイツ語もフランス語も英語も全部ゲルマン語であって、ラテン語からは何も影響を受けていない。北にいる民族にとっては、地中海および南の世界が大事であって、南北をまず考えるわけですね。西は海でしょう。東は寒くて暗いだけだから、あまり関心がなかった。
山崎 ドイツ語に「アーベント・ラント(西洋)」という言葉があるでしょう。これは東西型の発想でしょう。
木村 ええ。そこにはやはり、ローマのオリエンスとオクシデンスの影響があるのかもしれませんね。
戦後の日本では、欧米なみに北、南を先にいういい方に変えられてしまいましたね。だから、東北地方の北東部、東南アジアの南東部などといわなきゃいけない。
これはひどい文化破壊です。つまり、われわれの方位感覚と、西欧人の方位感覚とをごっちゃにしている。
われわれにとっては、東、西が大事なんです。西も東もわからない、東奔西走、東西トォーザイ、相撲の東ィ、西ィーなど、みんなそうですね。北、南とはいわないですよ。あるのは鶴屋南北くらいのものだ(笑)。
山崎 そういえば、現代中国語で、物のことを「東西(トンシー)」といいますね。おそらく地大物博(ちだいぶつはく)なるあの国において東西の物を集めてきて「物」というんでしょうね。
木村 東西感覚が発達した国は、北に対していいようのない恐怖感をもつ。
中国人が万里の長城を築いたのも、ローマ人が、ゲルマン人に対してリーメスという城塞を築いたのもそのせいですね。日本人がロシアを嫌いなのも、根本はこの理屈にならない理由からです。
山崎 なるほど、おもしろいねえ。いろんなことがわかりました。
ALL REVIEWSをフォローする