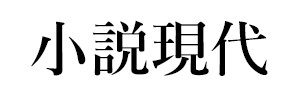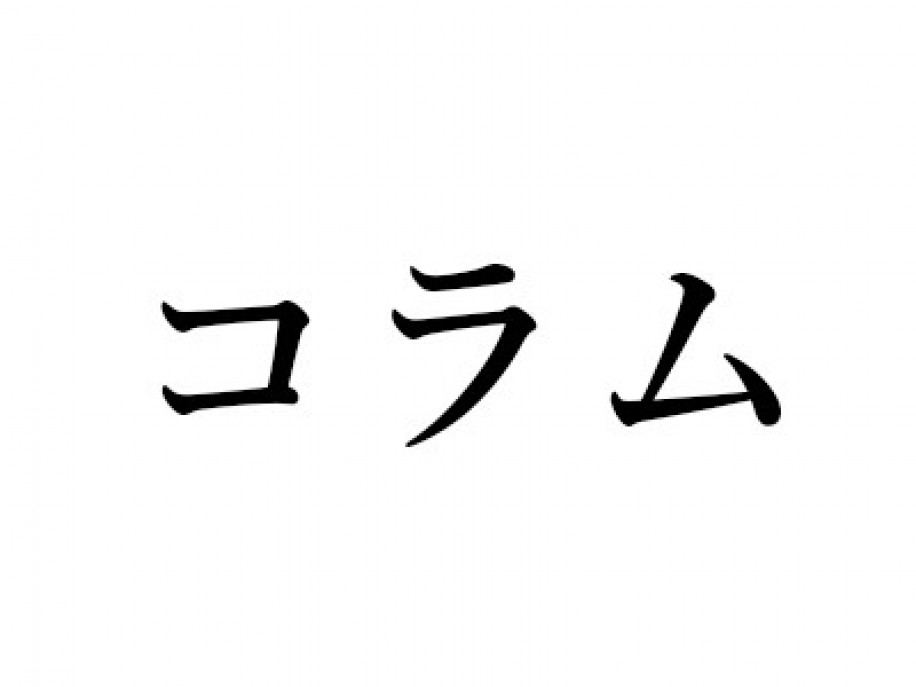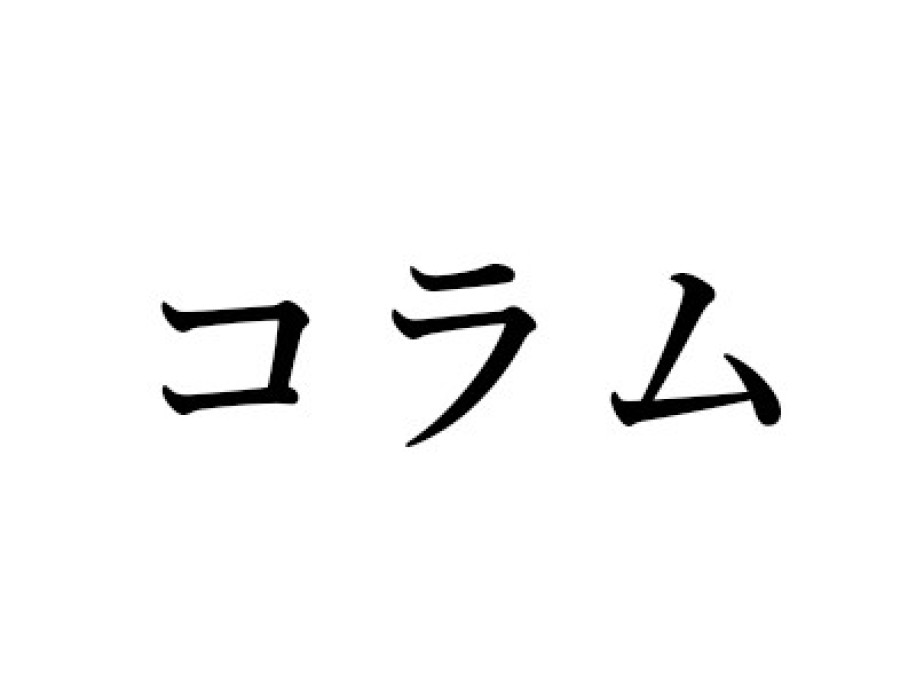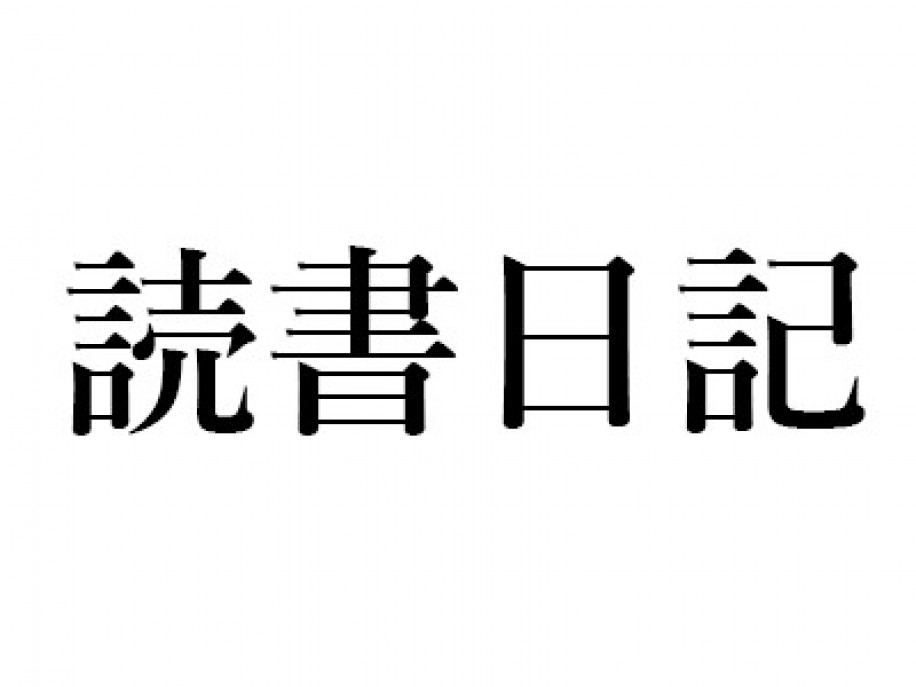コラム
出久根達郎『朝茶と一冊』(リブリオ出版)、上原隆『友がみな我よりえらく見える日は』(学陽書房)、井田真木子『フォーカスな人たち』(新潮社)ほか
本を探しに
必要に迫られ書店に行くときは別として、たまたま時間ができて入ったのに、「なんか読みたいと、前々から思ってたんだけど、何だったかな」
と思い出せぬまま、立ち去ることが、よくある。そういう事態を防ぐため、「読みたい本」と題するノートを作ったが、そのノートをどこへやったか忘れてしまった。
今はノートはやめ、透明のビニールケースの表に「読みたい本」と書いたシールを貼って(私もしつこい)、広告、書評、出版社の刊行案内などから、目についたら即切り抜き、即入れる。ハサミがそばになければ、とりあえず手でちぎり抜く。うかうかしていると、一年ぶんくらいすぐ溜まる。
読書エッセイに出てきた本も、気になったのは書きとめて、同じケースに放り込む。出久根達郎さんの『朝茶と一冊』『粋で野暮天』『書棚の隅っこ』『風がぺージをめくると』(いずれもリブリオ出版)からは、ずいぶんと引き写した。
上原隆著『友がみな我よりえらく見える日は』(学陽書房)は、ケース内のストックから、比較的早く実行に移したもの。特別でない、どこにでもいる、それだけに文字を通して知る機会のない、ふつうの人の内面を伝えるルポだ。
「容貌」の章に出てくる四十六歳の女性は、著者と向き合うのが、男性と二人で話す十五年ぶりのこと。山手線沿線にある小さな会社の経理課勤め。五時三十分の終業と同時に会社を出、同じ山手線沿線のワンルームマンションへ帰る。途中、ファミリーレストランで、夕食をとる。メニューは決まっている。料理はしないからガス代は基本料金のみ。かける相手がいない、電話も同様。
四十五歳になったとき、知り合いに頼んでヌード写真を撮った。でも、自分だけの思い出。明日も、たぶんあさっても、同じくり返しが続く。
彼女のような人とは、電車の中で数限りなく乗り合わせているのだろうが、たんたんとルポすることで、ふつうの人の「凄み」のようなものが伝わってくる。
「ふつうのおばさん」にしか見えない女性が、十二の金融機関から三千四百二十億円にのぼる金を騙(だま)し取ったのが、東洋信金事件である。事件の主役は、尾上縫。
彼女の名は、日本経済新聞社編『検証バブル 犯意なき過ち』(日本経済新聞社)に印象的に登場する。バブル末期、日銀が大手銀行系列ノンバンクの、融資先の実態調査に乗り出したが、そのときの一覧表には「尾上縫製(繊維業?)」とある。名もない個人に一千億円もの金が貸しつけられるとは、調査担当者もまさか思わず、「縫製」の誤植と考えた。
その「まさか」が行われたのが、バブルの実態だった。
井田真木子著『フォーカスな人たち』(新潮文庫)によれば、縫には株の基本的な知識すらなかったという。動機はただ「ちやほやされたかったんや」「一流の銀行や証券の人たちが、みんな寄ってきてくれた」。取り調べに当たった者は、罪を犯したのだということから縫に教えなければならなかったが、彼女は理解しなかった。「この金はでんぶ、うちのもんや。うちのもんをうちが使うて、何が悪い」。
こういうシロウトを「一流の銀行や証券」といった金融のプロが上客とし、彼女を中心に、延べで兆単位もの金が回ったのが、バブルという時代だったことを、この本は描いてみせる。
「この金はでんぶ……」の縫の抗弁で思い出したのは、戦後初の女性に対する死刑執行例となった、小林カウだ。旅館を手に入れ、商売を大きくするために、三人を殺害、四人めも計画中だった。大塚公子著『死刑囚の最後の瞬間』(角川文庫)は、カウの上申書を引いている。「わたしはしょばいがしみ(商売が趣味)で」「殺人をおかしてさいばんになるとゆうこともしりませんでした」。
裁判の何たるかもわからなかったようで、取り調べの検事に足をからませたり、こってりした厚化粧で出廷し、赤い口紅を塗った唇で、裁判長らに媚(こび)をふりまいたりする。
著者によればカウの犯罪は、女性にしては自立的なのが特徴という。目標を定めたら、ひたすら突進、じゃまな者は次々と殺した。生まれてこの方、働きづめに働いてきたカウには、死刑囚となってからの上げ膳据え膳の暮らしは耐えがたかったらしい。何か仕事をさせてくれと、拘置所長に再三訴えている。無知ゆえの攻撃性を割り引いても、昭和二十年代から三十年代の世相と、通ずるものがあると言えまいか。
裏話をすると、井田さんの文庫を機に、以前に読んだ、バブルと死刑囚との二冊を思い出した。が、かんじんの本が手もとにない。家のスペースの問題で、読み終えると売っているのである。参照の必要が出てくると、そのたびにじたばたする。
書名くらいノートにつけておけばいいのだが、まめな人間ではないために、頼りになるのは記憶のみ。「えーっと、たしか角川文庫だった、著者名は……」。額に皺寄せ、脳のひだの奥の奥から絞り出す感じ。書店には、新刊でないと、なかなかない。図書館で検索し、画面上のリストにあって、
「やれ、よかった」
と詳細を調べれば「貸出中」。締め切りに間に合わない!
自分の売った古本屋に、探しにいったこともいくたびか。どうしても手がかりが得られずに、あきらめたものもある。
立花隆著『ぼくが読んだ面白い本・ダメな本そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術』(長い! 文春文庫)には「『捨てる!』技術」批判があるが、次のくだりがなるほどだった。「人間の頭というのは、結局、頭の全体験の歴史の上に築かれてゆくもの」。思いがけない過去の記憶が働くことで、脳は業務を健全にこなしている。「いつか要るかも」はモノを捨てられない元凶だが、本に関しては「いつか」は必ず来るのである。
前に読んだ本を探すのに一日つぶし、「業務」に支障をきたす私には、著者の知的活動とは次元が違えど、共感できた。が、私の場合、たとえ家にとっておいても、それをまた探し出すのに、大騒ぎするだろうから、どの道、じたばたすることには変わりない。
読書エッセイを月一回書いている間は、締め切り前になると、
「あの本とあの本でいきたいけれど、なかったらどうしよう」
の連続だった。最終回の原稿を送るや、
「これでもう、月末ごとに図書館だ本屋だと、焦燥感を抱えて探し回らなくていいのだ」
と解放感がこみ上げてきた。が、他に趣味もない私は、読書は続けるだろうし、元来がお喋り。
「あの本にこんなことが書いてあって、それで思い出したんだけどさ……」
と語るのもおしまいなのは、ちょっと惜しい気もする。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする