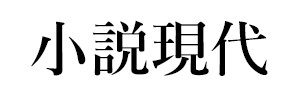コラム
小森 陽一『コモリくん、ニホン語に出会う』(KADOKAWA)、多和田 葉子『カタコトのうわごと』(青土社)、リービ 英雄『新宿の万葉集』(朝日新聞社)、ロジャー・パルバース『旅する帽子』(講談社)
バイリンガルな人々
帰国子女の人が、「頭の中では、何語で考えているんですか」
といった質問をされていると、あさはかな私はつい、
(かっこいい!)
と思ってしまう。十年間習った英語ですらモノにならなかった私には、バイリンガルであるとはどういうことか、想像がつかない。
ひとつの言語が別の言語に通訳される現場には、よく居合わせる。印象的だったのは、台湾人と日本人との文化交流会議。台湾側は、戦後生まれで、大学の日本語学科の教師という女性が、その任に当たっていた。
台湾側の出席者には、経歴からしてあきらかに、日本統治時代の教育を受けた男性がひとりいた。自分の中国語が訳される間、彼は苛立ったようすでいたが、ついに通訳をさえぎり、正した。
「僕の言うのは××××じゃない! ××!」
(たいへんだなあ)
女先生の立場に同情した。十八歳とかそれ以上になってから「外国語」として学ぶのと、子どもの頃、その言葉を使わざるを得ない環境で育ってきたのとでは、たぶん何かが違うのだ。
日本側についた、日本人通訳は、すごかった。外国語を母国語に訳すのに比べ、逆の方はたどたどしくなりがちだが、その中年女性は、スピードがまったく変わらない。聞けば、残留婦人の娘で、十代の半ばまで大陸で育ち、その後日本に移り住んだそうだ。
それぞれに、歴史を感じる面々だった。
のちに通訳の派遣会社に聞いたところでは、中国語に関しては、正確さと同時性が要求されるトップレベルの通訳となると、その会社では全員、彼女のような帰国者ということだった。大学や専門学校から勉強をはじめたのでは、どうしてもそこまでいかない、と。
人と言語との出会い方はさまざまだ。
東大で日本近代文学を研究する小森陽一は『小森陽一ニホン語に出会う』(大修館書店)で、肩書きからはうかがい知れない、独特の言語形成史を綴っている。父親の仕事でプラハに住み、小学校教育のほとんどをロシア語で受けた。母親が授けた日本の教科書に出てくるくらいの日本語は、マスターしたつもりでいたが、六年生で帰国して、こちらの学校に通いはじめてみれば、何か言うたび笑われる。
「ミナサン、ミナサンハ、イッタイ、ナニガオカシイノデショウカ」。そう、彼の話すのは完全な文章語だった。
少年は問いかける。現代日本語は「言文一致」であると、教科書に書かれていたのは、嘘なのか?
もっとも嫌いな教科は「国語」。表向きは周囲に同化し、つらくなるとロシア語でドストエフスキーを読むという、変わった中学生だった。スラブ研究センターなるものがあることを理由に、北海道大学に進んだものの、専門は、定員の関係で、よりによって国文科に振り分けられる。
苦しまぎれに選んだ卒論のテーマが、二葉亭四迷による翻訳小説の、ロシア語の原文との比較。調べはじめて気づいたのが、翻訳と「言文一致」体小説の成立との関わりだ。小学生のとき突き当たった問題に帰ってきた!
二葉亭四迷の「言文一致」体が、円朝の落語や滑稽本の伝統をふまえたにしても、成立の中心には、翻訳という行為が介在した。一つの閉じた言語システム内にあるうちは起こり得ない、ドラスチックな変容が、翻訳を通して起こったのでは。それを跡づけることで、「日本語」への怯えを払拭していった。
自分はどこかに「ふつうの日本人」なるものが存在し「ふつうの日本語」があるのだという「幻想」におびやかされていたのかも知れないと、あとがきに記している。
【単行本】
多和田葉子は、二十二歳からドイツに在住し、日本語でもドイツ語でも小説を著す。エッセイ集『カタコトのうわごと』(青土社)では、いわゆる「美しい日本語」は当てにならないと、くり返し書いている。「日本人でなければ美しい日本語は使えないのだという先入観を植えつけられて育ってきた」。
同様の意味で「美しいドイツ語」も著者は信じない。「国粋主義的な発想」から、あくまでも自由であろうとする試みだ。
リービ英雄著『新宿の万葉集』(朝日新聞社)におさめられた、リービとの対談でも、多和田は語る。ドイツでは、ドイツ語はドイツ人でなければできないと、思われてはいない。だから、自分はどちらかと言うと日本に向かって、ドイツ語でも書いていることを強調したい、と。
リービ英雄はアメリカ生まれ、十六歳のときはじめて日本の土を踏んで以来、往還をくり返し、現在は日本に在住、日本語で著作活動をする。外国人のあなたには日本語で書くことなどできないと、日本人に言われ続けた二十年間があった。
日本語を、自分にとっての「ステップマザータング」と呼ぶ。母語に対する「継母語」とでも訳そうか。マザータングか外国語かという二者択一に、問題が収斂されていくことを拒否してだ。
あるいは、「国家のレベルではモノリンガルに縋りつきはじめた時代に、文学者は必然的に政治とはまったく正反対の方向に走らざるをえなくなったんじゃないか」、その挑戦として。
多和田との違いは、リービにとっては、英語は重要ではない、日本語で小説を書くことが、「日本に入り込むという行為、一つの永遠なる越境行為」であるとする。
ロジャー・パルバース著、上杉隼人訳『旅する帽子』(講談社)は、アメリカで生まれ、ヨーロッパのいくつかの大学を経て、現在は日本に住む著者が、ラフカディオ・ハーンの作品、手紙から、ハーンの日本での日々を再構成した、小説だ。文章は読みやすくはないが、異形のアウトサイダーであったハーンの、孤独が伝わってくる。
ギリシャ人とアイルランド人との間に生まれ、ヨーロッパにもアメリカにも居場所をみいだせず、流浪の末、たどり着いたのが日本。明治時代の外国人教師のひとりとして。タイトルの帽子とは、少年期の事故でつぶれた眼を隠すため、かぶっていたものだ。
欧化の道と天皇の臣民としての道を同時に歩む、愛国主義的な教え子たちにも、日本人に対する優越感むきだしの外国人にも、違和感を覚え、自己疎外の念を強めていく。
「ハーンとぼくは、どの国も代表しない。ぼくたちはぼくたち以外の誰も代表しない」とのあとがきの言葉が、著者に筆を執らせた動機を表すものと読める。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする