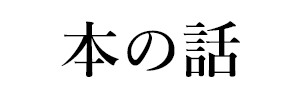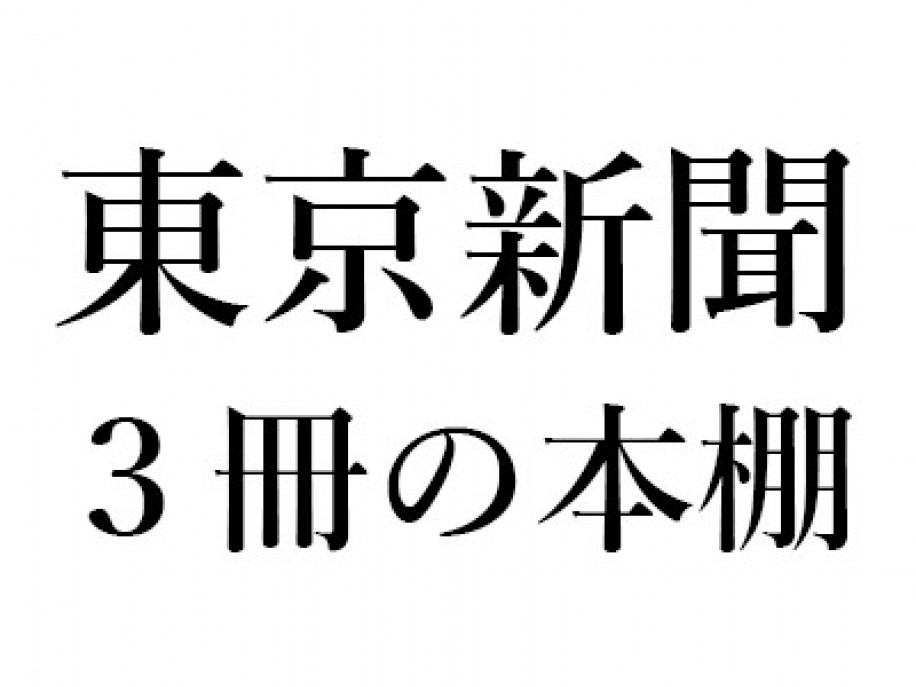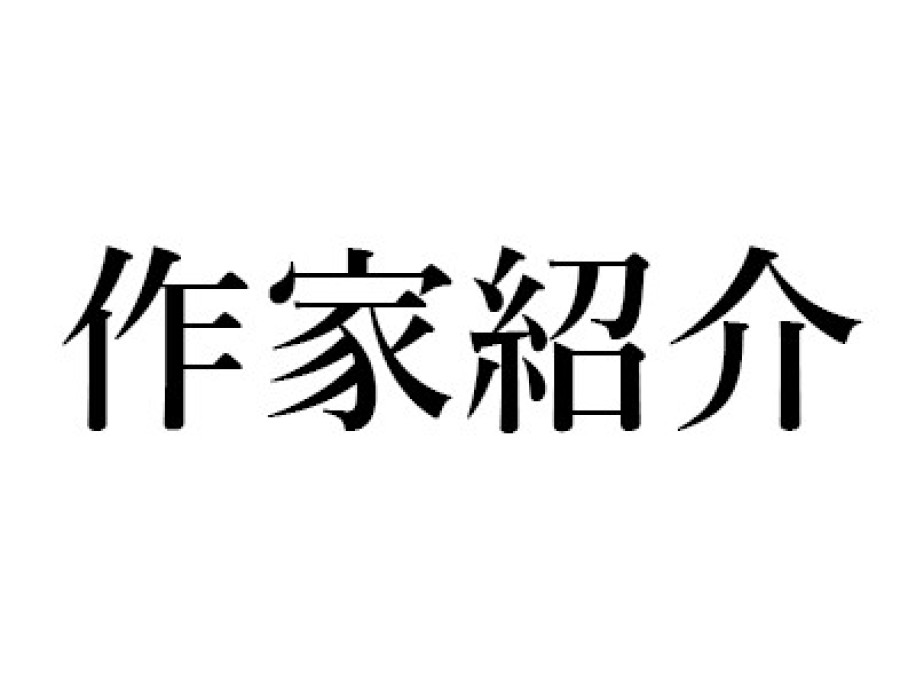コラム
深沢 七郎『楢山節考』(新潮社)、森 茉莉『ボッチチェリの扉』(新潮社)、梅崎春生『ボロ家の春秋』(講談社)、木山 捷平『軽石』(講談社)
ただ笑いたくて
人はいろいろな理由で本を読むが、私の場合はがいして、笑いたくて本を読んでいるようだ。「本の戦後五十年」というテーマを与えられて、どんな本を読んで来たかなあと振り返ってみると、一群の、なんだかよくわからないがおかしな小説が頭に浮かぶ。最も衝撃的だったのは、大学時代に知った深沢七郎作品だ。
『楢山節考』は私の小学生時代に映画化もされていたのだけれど、見ていなかった。貧乏なのでおばあさんが山に捨てられるという話だけは聞いていて、かわいそうでおそろしい話と思っていたので、実際に小説『楢山節考』を読んだときはビックリした。ヒロインであるおりんばあさんは喜び勇んで死地へと向かうのだ。長生きを恥じ、丈夫な歯をみずから折って、としよりらしくなったと晴れがましく思う。思いっきり意表をつくばあさんだ。その心の動きが、いちいち圧倒的だった。「老い」とか「死」にたいする考えに、根底からガタガタガタと揺さぶりをかけられた。
〈笑い〉というのは、基本的にはころがされる快感だと思う。しっかりと二本の足で立って歩いていたのが、バナナの皮でも何でもいいが、何かに滑ったりつまずいたりして、ころぶ。こわばり、固まり、ちぢこまっていたものが、いきなり、こける。そこから〈笑い〉が生まれる。
『楢山節考』はべつだん喜劇を狙ったものではないのだが、「ころがされる快感」に満ちていて、私にとってはそれまで味わったことのない、まったく画期的な、重量級の〈笑い〉の本なのだった。
『楢山節考』を読んでいた男友だちが、ある晩に電話して来て、「おりんばあさんになっちゃったよ」と笑って言ったのも思い出す。彼は、酔っぱらって(ケンカしたんだったかころんだのだったか忘れたが)前歯を折ってしまったのだった。
『笛吹川』を読んだときは、その後ギリシャのテオ・アンゲロプロス監督作品『旅芸人の記録』を見たときのたぶん三倍くらい感動した。ころころころころ人が死に、生まれる。深沢七郎は『人間滅亡の唄』というエッセー集の中で「屁は生理作用で胎内に発生して放出されるもので、人間が生まれることも屁と同じように生理作用で母親の胎内に発生して放出されるのだと思う」と書いているが、『笛吹川』はまさにそういう人間観によって織りあげられた大河ドラマなのだった。
私は「人間なんて屁のようなものだ」といった反ヒューマニズム的な言い方を好む者ではあるけれど、私が言うとどこか突っ張っているような、わざとらしさが漂ってしまうのが自分でもわかるが、深沢七郎はしんそこ、ほんとうに、ねっからそう思っている感じがする。そういう人は(文章を書く人の中では)めったにいない。そこがこわいところである。
大学時代の同じ頃、友人たちが以前に大問題になった『風流夢譚』の海賊版を作った(その後この作品はどこからも出版されていないはずである)。めちゃくちゃアナーキーな小説なのだが、当時の深沢七郎はその反響のもの凄さに本気でおびえて逃げ回ったという。ああいうものを書いてどういう反応が起きるかまるで読めなかったし読もうともしなかったのだろう。小心なんだか大胆なんだか全然わからない、ヘンな人だ。
大学を卒業して勤め始めた頃、森茉莉を知った。『贅沢貧乏』というエッセーに大笑いし、小説のほうも追っかけて読むようになった。一番好きなのは『ボッチチェリの扉』という小説で、これもべつだんお笑いではなく、綺麗な綺麗な恋愛小説なのだが、周辺人物の描写が私にはおかしくてたまらないのだった。
物語の語り手は由里(ユリア)という女で、森茉莉自身に違いないのだが、その女が住んでいる古い邸の家主で田窪絵美矢という老女がいる。「家の中には、まるでその家の主のやうな老女が、灰色のきものを幾重にも纏ひつけた感じで、ふはふはと、漂つてゐた」「絵美矢の気分がこの家を造り出してゐたのに係らず、先にこの家があつて、その中から絵美矢夫人が湧いて来たやうにも、見える」という人物である。
この老女の娘が美貌で、知り合いのアメリカ人がクリスマスなぞには盛大なプレゼントを送って来るのだが、そのおすそわけとして、この老女は銀紙にくるんだチョコレートを一個だけ由里(ユリア)のところに持って来る――という描写がある。
由里もさうがつがつ育つた訳ではないから、他人の所へ来たものの分け前を期待してゐた訳ではないが、夫人の徹底した吝嗇には舌を巻かざるを得ないのであつた。田窪家と由里との関係では三つ五つ位のところが当時としては常識だらうが、一つといふのは徹底してゐた。
とわざわざつけ加えずにはいられない森茉莉という人が、私にはおかしくてたまらないのである。
うまく言えないが……森茉莉の小説(絢爛たるレトリックの耽美小説で、確かに美しくロマンティックである)でもエッセーでも、行間に森茉莉という、まあ、一種の奇人の、おかしく歪んだ「生理」とか「無意識」とかがあふれ出ている感じがして、それで私は笑ってしまうのだと思う。
〈笑い〉というのは、かの有名なベルグソンが言う通り、理知の産物であるが、小説の場合は、そればかりではないようだ。理知の力によるおかしみよりも、もっと動物的なというか、「生理」とか「無意識」の生み出すおかしみのほうが、むしろ、ものを言う感じがする。うーん……すごく乱暴に言ってしまうと、天然ボケとかフラという言葉につながるような何か――。
「たくまざるユーモア」という言い方があるが、そんな言葉ではおとなしすぎる。書き手自身も気がついていないような、書き手のヘンテコさが、おさえがたく行間ににじみ出てしまったような小説――。それが私には一番面白い。
そういう意味で、男では深沢七郎、女では森茉莉が(私にとっては)長年の双璧だ(この二人は一度だけ対面している。森茉莉は「深沢七郎とクレーとおさよ」というエッセーで、深沢七郎のことを「“朦朧として厚い、曇り硝子を被った、理論の言える小説家”という、信じられない一人の人物であって、そこから氏の面妖が、又、正体不明が、出ているらしい」と書いている)。
この御両人に、近頃は梅崎春生と木山捷平が加わった。
二人ともやっぱりお笑い専門というわけではなくて、悲しみのある作家なのだが、それでも何とも言えないボケとかフラがある。
梅崎春生の『ボロ家の春秋』は、昭和二十九年に書かれたもので、その時代らしく貧しく、ボロ家に同居するはめになる二人の男の話。
「野呂旅人という名の男がいます。そいつはどこにいるか。目下僕の家に居住している。つまり僕と同居しているというわけです」という書き出しから、「亡びるものをして亡びしめよ。こういう悲壮な心境をもって、この日常のするどい緊張裡に僕らは毎日生きているのです。ご憫笑下さい」という最後に至るまで、全編「ゆるぎないボケ」に貫かれている。
この人は妙に俗な食べものや、人間のイボとかアザとか、あるいは体に合わない服とか、非常に生理的部分に訴えて来るものに執着している。その歪み方が面白い。
木山捷平は、昭和四十二年に書かれた『軽石』という短編に、この人らしさが凝縮されているような気がする。古いクギを売って得た三円で、「三円均一」の軽石を買った――という、ただそれだけの話である。
私は、古今亭志ん生の落語「寝床」で、銭湯につかっていた人が「あはあはふあああ~」といったふうなアクビをするところに、何だかわけもなく笑ってしまうのだが、『軽石』は、そのアクビのような小説だと思った。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする