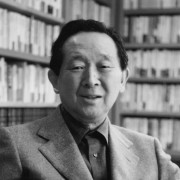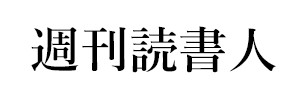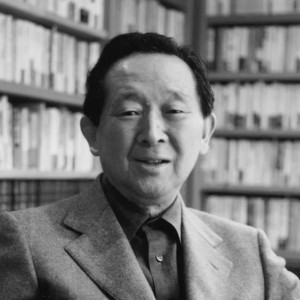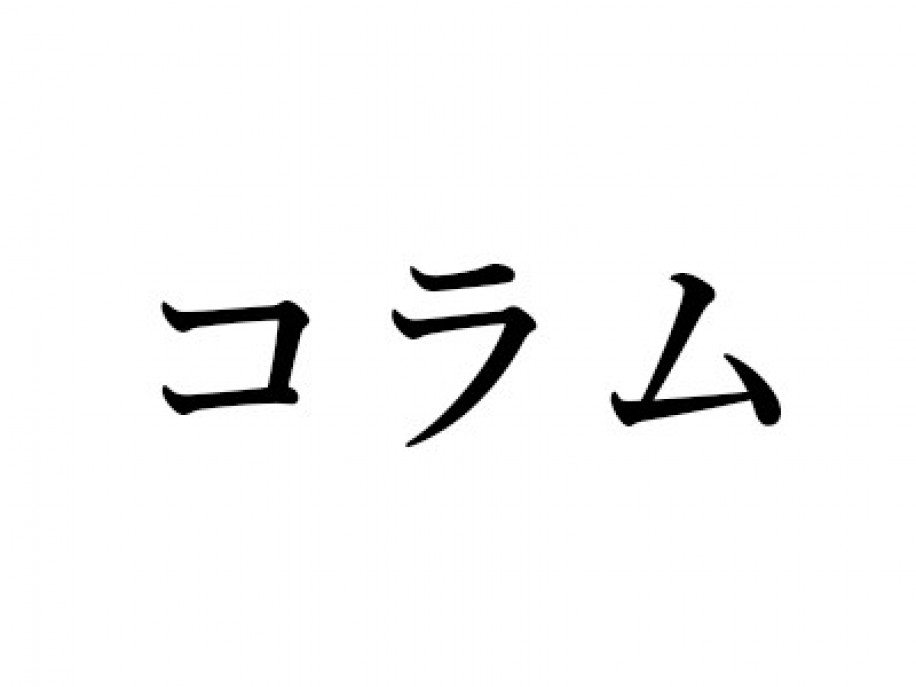書評
『秘花』(新潮社)
この『秘花』には、長年にわたって書き継がれてきた瀬戸内寂聴文学の特徴が出揃っている。咲き揃っていると言ってもいいかもしれない。
美少年の世阿弥が将軍義満に見染められ、その愛童になり、また北朝の最高の公家であり政治家であった二条良基にも愛される存在になり、武と文の二人の最高権力者の引き立てによって、世阿弥能が、天下の舞になっていく、「男(お)時(どき)」の過程を描いた部分がそのひとつである。
ここでは昔ながらの寂聴文学に光彩を与えている官能の祝祭が描かれているが、それでいて、美少年世阿弥に性的な関心を持った上流階級の人々を観察した彼に、
「下賤の生れや育ちのわれらには、あまりに率直な心情や、感動は、まず気恥しさに気おくれし、何かと憚かられることが多く、そのまま口になど出来るものではない。上流の方々にはわれらに共通した恥の観念が欠如しているように見受けられた」
と言わせているところは、瀬戸内寂聴文学の大衆的人気の思想的根拠が率直に示されている。良基は若い将軍義満に最高の公家としてその作法と学識を教える立場にある男だが、その彼が世阿弥に向って、
「これからは、智識人として貯えてきたわが教養のすべてを、藤若(世阿弥の幼名―註筆者)の頭脳と軀の中に注ぎ込んでやろう」
と言い、世阿弥に「かたじけのうございます」
と応えさせた後で、作者は少年の彼に、
「そういう真面目な話を、裸の五十六歳の老体と十三歳の未熟な少年が閨(ねや)の睦言として交わしていることが、ふとおかしくなった。そんなふたりを私の中のもう一対の双眼がじっと見据えている。父(観阿弥)の教える『離(り)見(けん)』とはこういうことなのではないか」
と思わせている。
ここでは権力者や高貴な老人に愛される過程そのものが、芸術創造者への道に通じていたことを作者は描いているのである。こうした部分に触れれば、冒頭の、
「わたしは鵺(ぬえ)こそ世阿弥の心の闇だと思いこみはじめていた」
という言葉の意味が見えてくる。
その世阿弥は、佐渡に流され、七十歳を越す年齢になった時、島で親しくなった沙江の息子の清晴に恋をする。しかし息子は、
「あんな爺(じじい)は厭だ。(中略)おれは仙兄(あにい)に惚れているし、仙兄も俺のことを可愛がってくれている」
と世阿弥を拒否する。こうして設定された世阿弥の失恋の背景には、輪廻と呼ばれる思想があるように僕には思われる。
読み進むにつれて、この〝鵺〟は世阿弥の心の闇であることを越えて、人間に表現することを求める芸術的衝動そのものであることが明らかになってくる。人はなぜ、小説や詩を書き、身体表現に命をかけるのか。それは心のなかに鵺が棲んでいるからだ。しかも、この芸術的衝動という欲求は、これでいいという満足に到達することがないのだ。この構造を
「拷問と恐怖の涯に残る極限の疲労の中で、犯されきらなかった安堵が、いつの間にか、中断された凌辱への不満に変っているのに気付く―」
と書くところに、芸術に向き合う創造者についての作者流の認識が示されている。
これが瀬戸内寂聴文学の、もうひとつの性格なのではないか。
そうした自らの文学構造の上に立って、作者は歴史を描く。言うまでもなく、文学が歴史を描くということは、歴史に浮き沈みし翻弄される人間を描くことである。考えてみれば当然のことだが、これを再認識させる力は、あえて世阿弥自身を主人公に据えた構図が成功しているからだと僕には思われる。身体表現、それを支える稀代の才能であった世阿弥を主人公にして書くというのは、現代文学の手法としては冒険だと言ってもいいだろう。狂言廻しをどこに設定するかという時、描くべき素材そのものが主人公になっていることは、その主人公が大きな存在であればあるほど困難が増すのだから。作品の近代性、批評生を確保するためには、この手法は危険が多いのである。
しかし、瀬戸内寂聴は、あえてその危険を冒した。それは、世阿弥という存在が、いかに長いあいだ作者のなかにあって発酵し続けていたかを証明している事柄である。僕は、世界的な演出家ピーター・ブルックが世阿弥の『花伝書』を読んで驚き、
「一五世紀のはじめの頃、シェイクスピアより一世紀年ほど以前に、このような演劇論がアジアの日本に生れていたとは知らなかった。それにしても今日の日本の現代劇がその伝統の影響をあまり受けていないように見えるのはなぜか」
と質問してきて答に困ったことがあったのを思い出した。そうした存在を主人公として使いきるために、作者は時間軸上に距離を取るという工夫をしている。
この方法は成功したと言うべきで、そこから、才能があるがゆえに歴史に翻弄された世阿弥の姿が浮彫りにされることになった。この作品は、世阿弥が七十二歳の時、一介の罪人として京を追われ、佐渡に流されるところから書きはじめられている。しばしば狂気の虜(とりこ)になり横暴であった足利義教(よしのり)の時代であった。何が原因で罪人にさせられたかについては説明されていない。そのかわり、同じような運命に見舞われた人々の名を、老(おい)の寝覚に算えてみる光景が描かれている。世阿弥は、歴史に弄(もてあそば)れた人の名を菅原道真、源高明、小野篁、在原行平、業平、後鳥羽院、順徳院、崇徳院、と算えていく。
そこから、どうしようもない拡大がりを持って、〝はかなさ〟という副主題が浮び上ってくる。個人の運命ばかりが儚いのではない。順徳院が佐渡に流されるようになって承久の乱そのものも儚いのである。
この乱の中心であり、隠岐に流された後鳥羽院上皇が、秀れた歌人であったところに、なぜ敗けると分っていた北條幕府討伐の兵を起したのかを解く鍵があると思われるが、律令制の秩序が崩壊し、秀吉による全国統一、そして徳川幕府によって封建制が確立するまでの過程のはじまりの時代に世阿弥は生きていたのであった。そうした足利、室町、南北朝のめまぐるしい交替の中にあって、わが国の古典的文化芸術は成熟したのである。
この時代に原型が整ったと言ってもいい日本文化の特徴を、侘び、さび、幽玄にのみ収斂させることは単純に過ぎるのではないか。烈しい人間としての生き方、欲、エロスを包含したものとして捉え直してこそ、世阿弥の芸も全体像を示すことができるのだと僕は思う。この『秘花』は、小説という形を取ることによって見事にそうした役割をも果したのだと僕は思う。
【この書評が収録されている書籍】
美少年の世阿弥が将軍義満に見染められ、その愛童になり、また北朝の最高の公家であり政治家であった二条良基にも愛される存在になり、武と文の二人の最高権力者の引き立てによって、世阿弥能が、天下の舞になっていく、「男(お)時(どき)」の過程を描いた部分がそのひとつである。
ここでは昔ながらの寂聴文学に光彩を与えている官能の祝祭が描かれているが、それでいて、美少年世阿弥に性的な関心を持った上流階級の人々を観察した彼に、
「下賤の生れや育ちのわれらには、あまりに率直な心情や、感動は、まず気恥しさに気おくれし、何かと憚かられることが多く、そのまま口になど出来るものではない。上流の方々にはわれらに共通した恥の観念が欠如しているように見受けられた」
と言わせているところは、瀬戸内寂聴文学の大衆的人気の思想的根拠が率直に示されている。良基は若い将軍義満に最高の公家としてその作法と学識を教える立場にある男だが、その彼が世阿弥に向って、
「これからは、智識人として貯えてきたわが教養のすべてを、藤若(世阿弥の幼名―註筆者)の頭脳と軀の中に注ぎ込んでやろう」
と言い、世阿弥に「かたじけのうございます」
と応えさせた後で、作者は少年の彼に、
「そういう真面目な話を、裸の五十六歳の老体と十三歳の未熟な少年が閨(ねや)の睦言として交わしていることが、ふとおかしくなった。そんなふたりを私の中のもう一対の双眼がじっと見据えている。父(観阿弥)の教える『離(り)見(けん)』とはこういうことなのではないか」
と思わせている。
ここでは権力者や高貴な老人に愛される過程そのものが、芸術創造者への道に通じていたことを作者は描いているのである。こうした部分に触れれば、冒頭の、
「わたしは鵺(ぬえ)こそ世阿弥の心の闇だと思いこみはじめていた」
という言葉の意味が見えてくる。
その世阿弥は、佐渡に流され、七十歳を越す年齢になった時、島で親しくなった沙江の息子の清晴に恋をする。しかし息子は、
「あんな爺(じじい)は厭だ。(中略)おれは仙兄(あにい)に惚れているし、仙兄も俺のことを可愛がってくれている」
と世阿弥を拒否する。こうして設定された世阿弥の失恋の背景には、輪廻と呼ばれる思想があるように僕には思われる。
読み進むにつれて、この〝鵺〟は世阿弥の心の闇であることを越えて、人間に表現することを求める芸術的衝動そのものであることが明らかになってくる。人はなぜ、小説や詩を書き、身体表現に命をかけるのか。それは心のなかに鵺が棲んでいるからだ。しかも、この芸術的衝動という欲求は、これでいいという満足に到達することがないのだ。この構造を
「拷問と恐怖の涯に残る極限の疲労の中で、犯されきらなかった安堵が、いつの間にか、中断された凌辱への不満に変っているのに気付く―」
と書くところに、芸術に向き合う創造者についての作者流の認識が示されている。
これが瀬戸内寂聴文学の、もうひとつの性格なのではないか。
そうした自らの文学構造の上に立って、作者は歴史を描く。言うまでもなく、文学が歴史を描くということは、歴史に浮き沈みし翻弄される人間を描くことである。考えてみれば当然のことだが、これを再認識させる力は、あえて世阿弥自身を主人公に据えた構図が成功しているからだと僕には思われる。身体表現、それを支える稀代の才能であった世阿弥を主人公にして書くというのは、現代文学の手法としては冒険だと言ってもいいだろう。狂言廻しをどこに設定するかという時、描くべき素材そのものが主人公になっていることは、その主人公が大きな存在であればあるほど困難が増すのだから。作品の近代性、批評生を確保するためには、この手法は危険が多いのである。
しかし、瀬戸内寂聴は、あえてその危険を冒した。それは、世阿弥という存在が、いかに長いあいだ作者のなかにあって発酵し続けていたかを証明している事柄である。僕は、世界的な演出家ピーター・ブルックが世阿弥の『花伝書』を読んで驚き、
「一五世紀のはじめの頃、シェイクスピアより一世紀年ほど以前に、このような演劇論がアジアの日本に生れていたとは知らなかった。それにしても今日の日本の現代劇がその伝統の影響をあまり受けていないように見えるのはなぜか」
と質問してきて答に困ったことがあったのを思い出した。そうした存在を主人公として使いきるために、作者は時間軸上に距離を取るという工夫をしている。
この方法は成功したと言うべきで、そこから、才能があるがゆえに歴史に翻弄された世阿弥の姿が浮彫りにされることになった。この作品は、世阿弥が七十二歳の時、一介の罪人として京を追われ、佐渡に流されるところから書きはじめられている。しばしば狂気の虜(とりこ)になり横暴であった足利義教(よしのり)の時代であった。何が原因で罪人にさせられたかについては説明されていない。そのかわり、同じような運命に見舞われた人々の名を、老(おい)の寝覚に算えてみる光景が描かれている。世阿弥は、歴史に弄(もてあそば)れた人の名を菅原道真、源高明、小野篁、在原行平、業平、後鳥羽院、順徳院、崇徳院、と算えていく。
そこから、どうしようもない拡大がりを持って、〝はかなさ〟という副主題が浮び上ってくる。個人の運命ばかりが儚いのではない。順徳院が佐渡に流されるようになって承久の乱そのものも儚いのである。
この乱の中心であり、隠岐に流された後鳥羽院上皇が、秀れた歌人であったところに、なぜ敗けると分っていた北條幕府討伐の兵を起したのかを解く鍵があると思われるが、律令制の秩序が崩壊し、秀吉による全国統一、そして徳川幕府によって封建制が確立するまでの過程のはじまりの時代に世阿弥は生きていたのであった。そうした足利、室町、南北朝のめまぐるしい交替の中にあって、わが国の古典的文化芸術は成熟したのである。
この時代に原型が整ったと言ってもいい日本文化の特徴を、侘び、さび、幽玄にのみ収斂させることは単純に過ぎるのではないか。烈しい人間としての生き方、欲、エロスを包含したものとして捉え直してこそ、世阿弥の芸も全体像を示すことができるのだと僕は思う。この『秘花』は、小説という形を取ることによって見事にそうした役割をも果したのだと僕は思う。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする