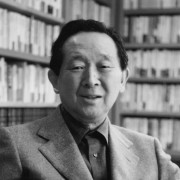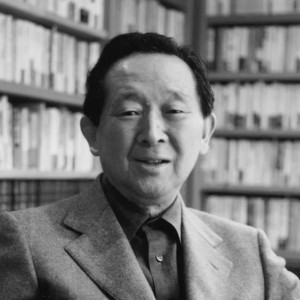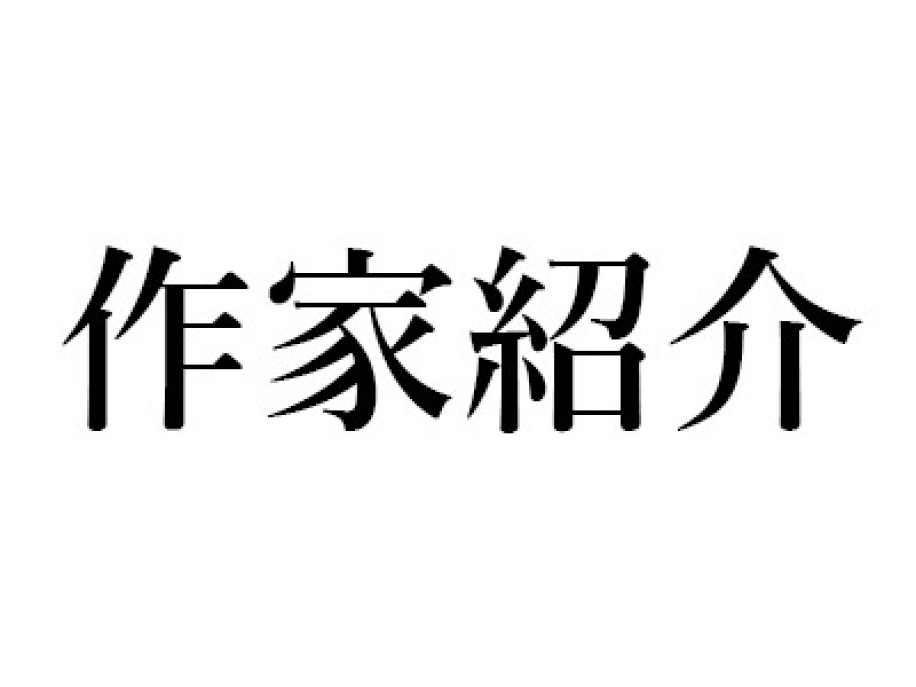解説
『或る女』(中央公論社)
このように見てくると、この『或る女』の世界は、明治の終りから大正のはじめにかけて、有島武郎という稀有のモダンな作家によって形成された空中楼閣のような世界を見せているとも言えるのである。それが空中楼閣であるのは、当時の社会が深く因習に支配された半封建の裡に眠っていたからだ。この作品が空中楼閣としてでなく読まれるためには、その後の長い辛い期間、十五年戦争と呼ばれているファシズムの年月を経て、日本の敗戦以後の時代まで待たなければならなかった。それにしても『或る女』という楼閣を構築し得たのは、有島武郎の独特の才能と同時に、彼が上流社会に属していたことによって、ある程度においてではあったが例外的に自由を持ち、外国を知ることができた等々の条件があったことが指摘できるだろう。
その彼が、「婦人公論」記者波多野秋子と死を共にしたことが、どれほど当時の社会を震撼させたかは、事件を報道した新聞雑誌の反応に明らかである。彼女に夫があったことからの、道徳家、教育者の渋面、内心共感しながらも俗世間を恐れての口籠り、良識を振りかざして鞭を振う言説などが見られた。
その烈しさは、文壇の長老の一人であった生田長江が「有島氏事件の批判に対する批判」(「婦人公論」)のなかで、
「文壇の人々が『恋愛神聖』とか『恋愛の極致』とかをふり廻して『姦通及び情死』を大に讃美しているというような事実、或は大に讃美するであろうと思われるような事実はそもそも何処にあるのであるか。
かの諸名士と称する官吏の古手、教師の古手、記者の古手なぞは、毎度の事ながら事実を虚構して、私共文壇人を誣(し)えているのである」
と、文壇全体を世俗の魔女狩りから護りながら、結論としては、
「私共の理解している氏はたしかにそうした立派な感情の持主であった」
と結ぶ苦心の筆を振わなければならなかった程であった。そうしたなかで主幹の嶋中雄作が世俗の反応など全く意に介さぬ態度で、
「波多野秋子氏の霊に捧げて一切を明かにす」という長文の所信表明を行っていることは、ジャーナリズムの本来の在り方を鮮明に示した事柄であった。当時は背骨のしっかりした言論人がいたのである。このことは、正宗白鳥についても言える。彼は、
「―世にも羨ましいことのように(有島の心中を)空想したりした。こういう情死こそ後日になって幾多の美しい詩の題目になるであろう」
と、平然と述べ、
「氏は温良の美質に富んでいたため、すべての人に好感を抱かれていた人らしく―」
と、有島について観察し、また、妻を奪われた夫波多野春房の心情を慮り、『アンナ・カレーニナ』の夫、『ボヴァリー夫人』の夫、『パウロとフランチスカ』の夫の場合を想起している。世俗の騒ぎに動ずることなく白鳥流を通している態度は、彼が新聞記者であったことを考えると、ジャーナリストにも例外があることを証しているように思われる。
こうした世俗の反応と例外の存在は『或る女』の中で、早月葉子を巡る世間、というかたちで極めて適確に描写されていて、有島武郎自身、死後までを見透していたような錯覚を読者に与えるのである。
この『或る女』について有島武郎自身が語っている言葉は、彼がいかに主人公早月葉子に自らの主体を移していったかを証明しており、そのことは直ちにフローベルの「マダムボヴァリーとは私だ」という言葉を想起させるのである。同じように「マルテの手記」を書いたリルケの言葉も、作品『或る女』と有島武郎の関係を考える上で大きな示唆を与えると思われる。リルケはルー・アンドレーアス・サロメ宛にドゥイノから書いている。
「―ある意味で私の危険から生れたマルテは、私の破滅を引受けるために破滅したともいえるだろうか―」
そして、
「君は、私があの本を書き終ったあとで生きのこった者のような気持がし、途方にくれ、手持ぶさたで、仕事が手につかないのを理解できるだろうか」
と。
そうして、有島武郎はどうだったのか。
「痛い痛い痛い……痛い」
と、「前後を忘れ我れを忘れて、魂を搾り出すようにこう呻く悲しげな叫び声」と共に早月葉子の旅の終りを書き終った大正八年五月二十三日に有島武郎がじっと見ていたのは、女性の姿を纏った自らの行末であったのだろうか。彼はそれから四年後の同じ初夏に自らの生命を絶ったのである。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする