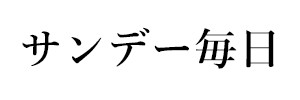書評
『骨風』(文藝春秋)
この本はいい。私はすごくススメたい。
私は、いまこの本を友人たちにススメまくっている。私は著者と友人で、私の友人達もまたクマさんと友人だっていうのに。この本には、クマさんその人がいる。この本を読んでいて感じるのはクマさんその人であって、私が、クマさんはいいなあ、と思っているそのクマさんがそのままいるのだ。
はじまって9行目に、一人称が出てきた。
オレはギャラのすべてがスクラップ鉄の購入代に消えたとしても惜しくはないと思っていた。
クマさんの一人称は「オレ」じゃなけりゃいけない。「私」が惜しくないと思う話は、クマさんの話じゃない。一事が万事に、そのようにこの本はまるごとクマさんなのだ。
今年七十三歳になったクマさんのまわりで、人が死ぬ。
猫が死んで、ワカマツ監督が死んで、お父さんが死ぬ。鹿が目の前で死んで、ホッタさんが死んでいて、深沢さんが死んだのはだいぶ前だったな。
クマさんも蜂に刺されて危うく死ぬところだった。お母さんが亡くなって、弟さんも亡くなった。
死んだ人たちの思い出をクマさんが書いているのを読んで、読者はクマさんの話に耳を傾けながら、クマさんのココロに近づいて、何事かを感じるはずだ。
これは、この本に書かれていることじゃなくてクマさんに直接聞いた話なんだけど、美大の学生だったころの話だろうか、お金持ちのドラ息子に誘われた、グループでのドライブ旅行から帰ってくる。ドラ息子の住んでる高級アパートに、ドヤドヤと入っていくと……。
部屋に豪華な小鳥のカゴがあって、中で旅行中放っておかれた小鳥が死んでいた。その小鳥を、そのボンボンが、部屋のダストシュート(昔、そんな風なゴミ捨て装置があった。フタをあけてそこにゴミをほうりこむと、そのままゴミ捨て場に直行する)に、ポイと捨てた。
「ポイって、捨てるんだよぉ〜」と、言いつけるように言ったクマさんが、一瞬、小学生の男の子のように見えた。
バーのカウンターで、なれない注文をして、試飲でもするみたいにビールを飲んでいると、革ジャンにGパンのガタイのいいスキンヘッド男が、ドカリと私の隣の席に座った。
そんな風にして、はじめて出会って、まだ、日の浅い頃の話だ。
あの時に感じたような、クマさんの命に対するまっとうさが私の中で地続きになっている。
私がつたえたいのはこんな事だ。クマさんの話はオモシロイ。話のだんどりがいいし、声色がいいし、表情がいい。笑いがあるし、驚きがある、話し上手だ。
そしてこの本も、そのクマさんのおもしろい話のように引き込まれる。しかし、話のおもしろいのも、笑いがあり、驚きがあるのも、それはそれだけで、おもしろいのでも驚くのでもなく、クマさんのまるごとを感じるからの、おもしろさであって、驚きだったということ。
そのことにいまさらのように気がついて、私は大切な友人を大切な人に紹介するように、この本をいますごくススメたい。
ALL REVIEWSをフォローする