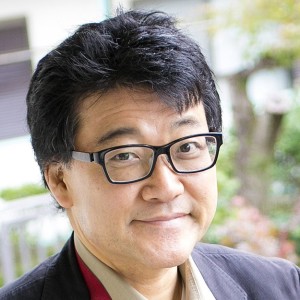書評
『城』(白水社)
フランツ・カフカ(Franz Kafka 1883-1924)
チェコの作家。カフカが生まれたプラハは当時オーストリア・ハンガリー帝国に属し、彼はドイツ語を母国語として育った。生前に発表したのは『変身』(1915)、『流刑地にて』(1919)などわずかにすぎない。死を前にしたカフカは、友人マックス・ブロートにすべての草稿を焼きすてるように依頼する。しかしブロートは「誠実な裏切り」によって、カフカの作品を世に送りだした。代表作に『審判』(1925)、『城』(1926)などがある。introduction
カフカは「変身」をまず読んだが、さほどおもしろいと思わなかった。「流刑地にて」も最初はピンとこなかった(あとで読みかえしてみて傑作だと思ったが)。「なるほど!」と膝を叩いたのは、『城』を読んだときだ。カフカが描いているのは、架空の世界などではなく、ぼくの目のまえにあるこの現実だとわかったのだ。カフカについては、いろいろな研究者が、官僚主義的社会への批判だの、ユダヤ民族の問題を扱っているだの、宗教的アレゴリーだの、不合理なものの象徴だの、御託をひねくりまわしているが、それらはすべてカフカ作品の矮小化にすぎない。よしオレがカフカをちゃんと読んでやろうと意気ごんで《決定版カフカ全集》を揃えた。でも、けっきょく読んだのは小説ばかりで、『手紙』や『日記』はつまみぐいしただけ。軟弱だなあ。▼ ▼ ▼
世界を自分の掌のうえに乗せたい。あるいは、世界のなかに入りこんでひとつになりたい。これは人間のいちばん根元的な欲望だ。いや、というよりも、それが人間であるということなのだ。ボルヘスが精緻な世界模型をつくりあげるのも、パスが世界と言葉の問題を解こうとするのも、そこにかかっている。しかし、その欲望は、けっして成就されはしない。フランツ・カフカは、そのことを言いあててしまった。カフカの作品を読むのは、いっけん現実と隔絶するようだが、じつはふかく現実の底へと滑りこんでいくことだ。
未完の長篇『城』は、次の文章ではじまる。
Kが到着したのは、夜もおそくなってからであった。村は、深い雪のなかに横たわっていた。城山(しろやま)は、なにひとつ見えず、霧と夜暗(やあん)につつまれていた。大きな城のありかをしめすかすかな灯りさえなかった。Kは、長いあいだ、国道から村に通じる木の橋のうえに立って、さだかならぬ虚空を見あげていた。
いまKの目の前にある村は、ひとつの世界である。
彼は測量士としてこの村に招かれたが、顧客である〈城〉は彼を受けいれない。だいいち、Kを雇ったのが〈城〉のどの部署なのかすら判然としない。やがてクラム長官がKの身分を保証してくれるということがわかったが、クラムに面会しようというKの試みはすべて失敗する。おまけに、彼が直接の上司であるはずの村長は、クラムが彼に宛てた手紙を見て「これは正式の任命ではない。この手紙ではなんの効力もない」と一蹴する。だからといって、Kの招聘はまったくの間違いでもないらしい。突如として二人の助手があてがわれるし、クラムからは「よく仕事をしてくれているようで嬉しい」との手紙がくる。もっとも、助手はまったくの厄介者だし、クラムがいうような仕事はなにひとつしていないのだが。
Kに対する村人たちの態度もかたくなだ。村の決まりを知らない男が、傍若無人に歩きまわっていると白い目で見る。だが、その村の決まりがどういうものなのかは明らかにされない。ほんとうにそんな決まりがあるのだろうか。Kが発する問いに対しては、〈城〉の権威と煩雑な法的手つづきが返ってくるばかりなのだ。
『城』は、しばしば不条理小説だと言われる。Kは村の中心である城にたどりつこうと努力を重ねるが、どうやっても辿りつけない。城は永遠に理解不能で不可視だ。――そんなふうに内容紹介されたりする。
しかし、じっさいに作品を読んでみると、どうもようすがちがう。Kは城のことを気にはしているものの、万難を排してそこに行こうというほどの意志はない。村でのすれちがいも、不条理というほどの強度はなく、どちらかといえば日常茶飯のトンチンカンな煩わしさだ。ぼくが最初に『城』を読んだときは、人々の評判を鵜呑みにして、主人公が必死でおこなうありとあらゆる努力が得体のしれぬ障碍に阻まれてむなしく水泡に帰す――という意地悪な物語を期待していたので、すっかり拍子抜けしてしまった(余談だが、そういう小説を探しているなら、カリンティ・フェレンツの『エペペ』がお薦めだ)。
深読みするからまちがえるのだ。〈城〉に特別な意味があるのだとか、これはなにかの象徴だとか、逆に「空虚たる中心」だとか、うがった解釈などは必要ないのに。城は城でしかなく、辿りつけないのはただそれだけのことだ。すこしも難解なところはない。
世界には意味などないし、世界を統べる秩序もない。そこになにかあるとしたら、おびただしい規則だけだろう。そのなかにいる者は暗黙のうちに受容しているが、外から来たものにとっては曖昧で煩雑な規則の束。Kの行為が頓挫するたびに、その一部分がわかるのだが、別な部分がわからないかぎりそれだけでは用をなさない。規則の束の全体をいっぺんに把握しなければ、部分部分の意味は理解できない。しかし、全体を把握するためには部分部分の理解を重ねる以外の方法はない。
これはパラドックスだ。だが、パラドックスそのものはたいして重要ではない。なにより切実なのは、こうした世界のありようが、ほかならぬ自分(この作品ではK)ひとりのものだということだ。『城』を読むうえでの補助線になるのが、カフカの初期短篇「掟の門前」である。ごく短い物語で、のちに長篇『審判』に組みいれられた。こんな話だ。
田舎からやってきた男が“掟の門前”のなかに入ろうとするが、守衛にいまは入れるわけにはいかないと拒まれる。しかし、門は開いているので、その気になれば入れないこともない。だが、彼は待つことにする。男は守衛に入れてくれるよういろいろと頼むが、けっきょく挫折してしまう。その生涯を門前で待つことで費やした彼に死がおとずれる。守衛はいまわの際の男に、この門はただ彼のためにあったのだと告げて、門を閉ざす。
ここで示されている構図は『城』のそれと相似形だ。カフカのこうした作品は、彼が民族、宗教、国籍、言語のあらゆる点で確固たる拠りどころがなく、また社会的地位や家庭関係においても親しい居場所を見出しえなかったという境遇に由来するのかもしれない。しかし、なにもカフカが特別というわけではなかろう。
ぼくらが空気のように享受している世界――それは日常でも物語でもちがいがない――は、本来なんの根拠ももたない、たかだか恣意的な規則の束によって支えられているものだ。『城』という小説は、それをあっさりと暴いてしまう。しかも、だからといって、世界を無視することもそこから逃れることもできない。むしろ、その欺瞞性を知ることで、さらに世界に焦がれてしまう。もっと親密に世界とふれたいとねがう。村のなかを経めぐるKの足どりは、ぼくやあなたが生きることとおなじだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする