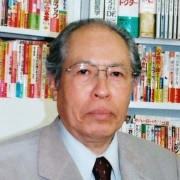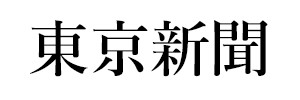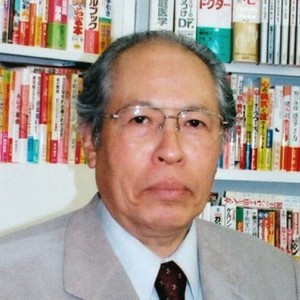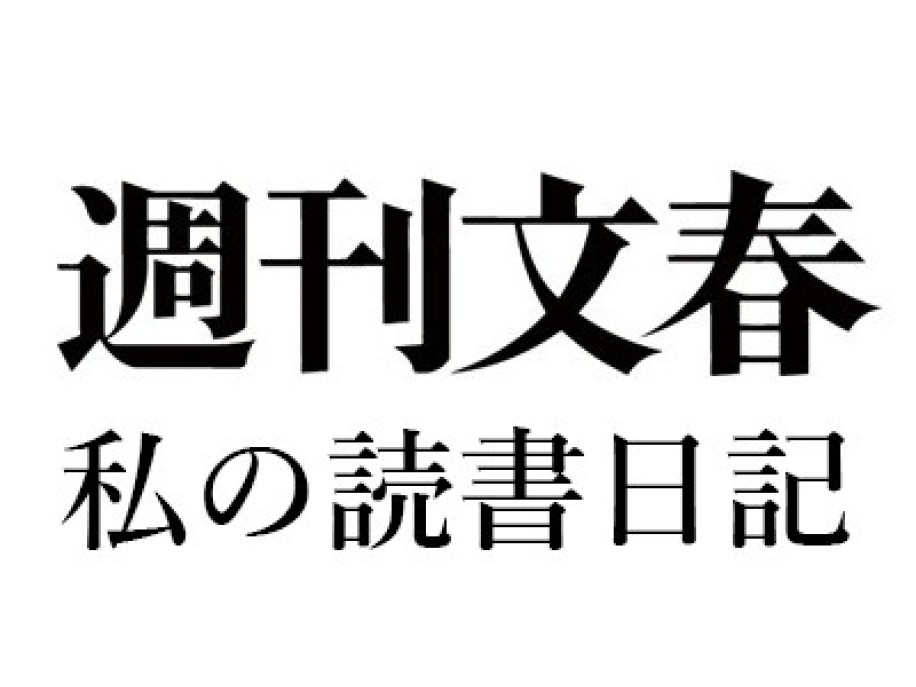書評
『“読書国民”の誕生―明治30年代の活字メディアと読書文化』(日本エディタースクール出版部)
〈読書国民〉の誕生
戦前の雑誌やロ絵などには、読書する人々の姿が頻繁に登場し、「緑陰読書号」などと銘打たれていたものだが、そのもとは明治三十年代、急激な近代化を背景に、日本人の多くが強い向上欲をいだき、その知的源泉を読書に求め、内田魯庵(ろあん)のことばにある「読書国民」の性格を帯びるようになった時期まで遡(さかのぼ)ることができる。本書はこの興味深いプロセスを、豊富な資料を用いて跡づけたもの。かつて「日本人は読書好きな国民」ということが定説となっていたが、その内容をくわしく分析したものは例がない。「世界の一等国民」をめざした明治中期の日本人は、有識層や学生たちは争うように活字媒体を求めた。大手出版社が活動を開始し、各地に新聞縦覧所や図書館が生まれた。それは官民をあげての運動であり地域の小図書館が続々とと誕生し、予算も現在の物価に直せばよほど潤沢なほどであった。著者はそのような読書大国への歩みを目くばりをきかせながら、同時にこの時代はまだ図書館の利用者層が庶民にまではおよばず、とくに女性が自由に図書館を利用できるような社会的条件が整っていなかったことも指摘している。
一方、鉄道をはじめ交通機関の発展によって、車中や駅待合室での読書が盛んになり、列車図書室や旅客専門の貸本会社まで現れた。永続はしなかったようだが、イギリスなどでもほとんど同時代に車中読書をねらった出版市場が成立しはじめた。著者はこれを「無聊(ぶりょう)読書の産業化」とよんでいるが、二十世紀の読書の一面をいいあてている。
昭和初期以降の出版の隆盛も、このような明治期の「国民読書」の基礎の上に準備されたものといえよう。ひるがえって平成の状況はどうだろうか。かつてに比すれば活字には勢いが欠け、学生の読書離れはとどまるところを知らず、図書館の予算も削減の一方だ。車中でも"無聊ケータイ"の図ばかり目につくような気がするのは、私一人だろうか。
ALL REVIEWSをフォローする