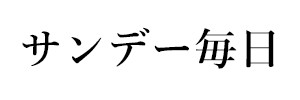書評
『出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記』(フォレスト出版)
裏切りと開き直りが人を切り捨てていく
出版社勤務も含め、もう15年間ほど出版業界にいるが、この業界には、信じられないほど「口約束」が残っている。口約束が実際の約束になっているならばまだいい。「ぜひ、お願いしますよ!」を本当のお願いだと受け止めていたら、とりあえず言ってみただけだった、という揉め事が方々に転がっている。私は、編集者=発注側からライター=受注側に転じたのだが、痛感するのは、そういうつもりじゃなかった、という編集者の開き直りが直接的に生活に影響するという当たり前の事実だ。
著訳書が60冊もあり、10年近くは休みなく忙しく働いてきた翻訳家が、8年前に業界から足を洗った。度重なる編集者からの裏切り、上層部の開き直りによって、1人の人間が繰り返し切り捨てられてきた。
とにかく、無数の言い訳や一方的な通達がぶつけられる。
「今回のこの本は弊社の社長の訳者名で出ることになります」「だって私、英語読めないもん」「印税は6%と言っていましたけど、4%しか払えなくなったんですよ」「誤訳や誤植があった場合は重版の際に訳者が実費で訂正料を払う」「宗教色が強い内容だった(ので出せない)」
ひどい。それを訳者に伝える時、なぜか皆、さほど悪びれる様子がない。まぁ、こういうことになっちゃいましたんで、との態度。そのくせ、訳者として大ヒットが出ると、態度が180度変わる。態度の変化がバレていないと思っているところにも編集者の非道さが透けてしまう。裁判にまで持ち込まれた具体例はあまりに無残だ。
編集者からライターに転じた自分が読んでも、こんなことって本当にあるのかな、と驚く事例ばかり。でも、あるのだ。それくらい、閉鎖的に行われてきた(&いる)ってことなのだ。
ALL REVIEWSをフォローする