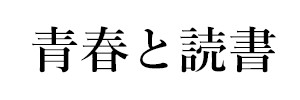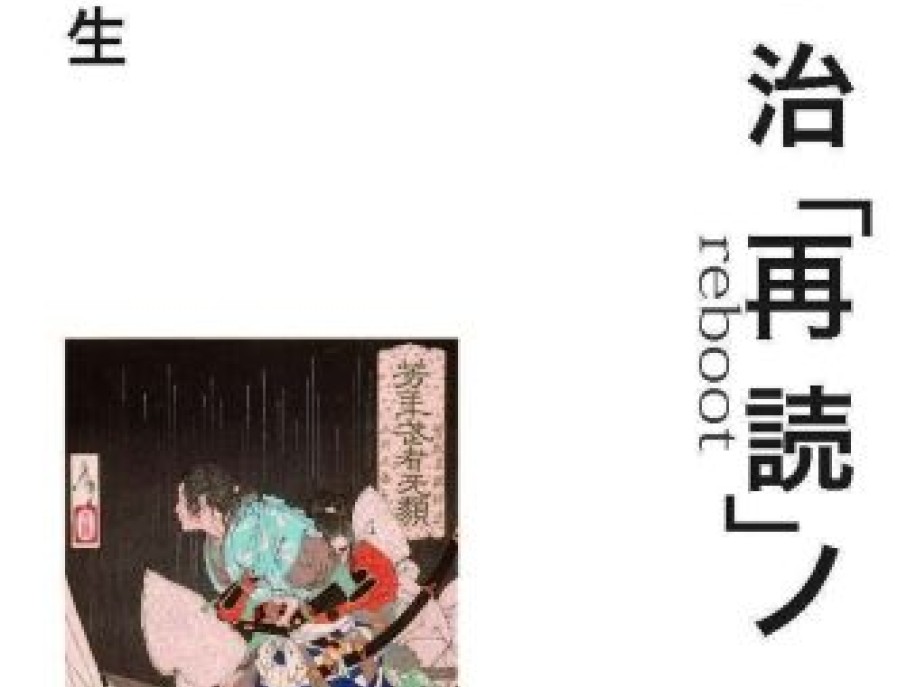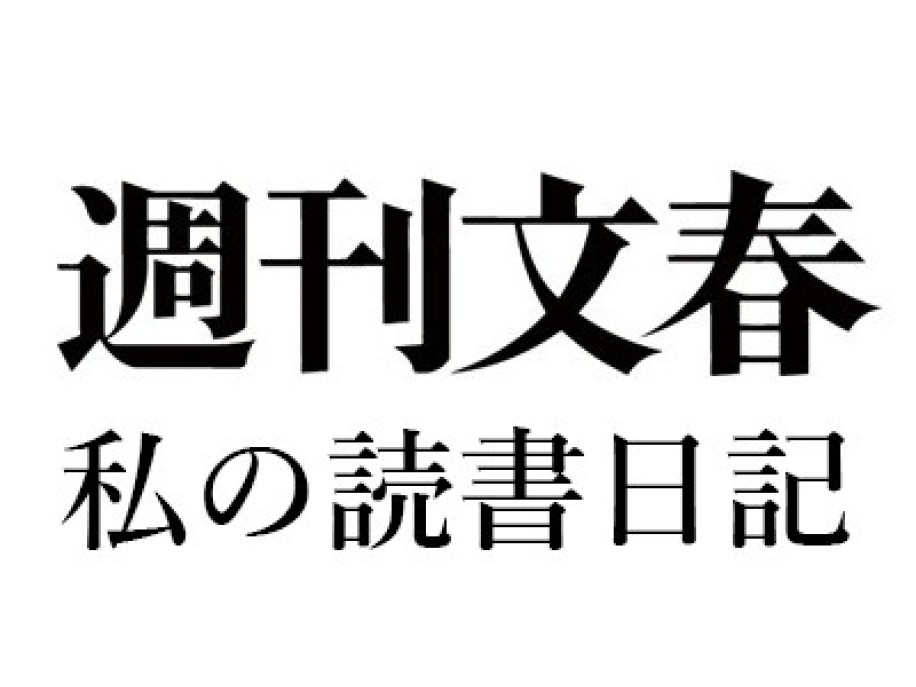書評
『乱世を生きる 市場原理は嘘かもしれない』(集英社)
イヤな言葉がはやる。近頃(たぶんこの二、三年・ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年)私が最も嫌っている言葉は「勝ち組・負け組」というやつだ。一種のシャレなんだろうが「勝ち犬・負け犬」という言葉もいやらしい。誰もが平気で、人によっては嬉々としてこういう言葉を口にし、筆にする。私はわけのわからない不快感に襲われ、頭の中で怒鳴り出す。
「どうでもいいじゃないか、そんなこと!」
少し頭を冷やして考えてみる。私はいったい何に対して怒っているのだろう。どこがどう不快なんだろう。
一番に考えられるのは、「勝ち組・負け組」的二分法というのが、あくまでも世間的な価値基準がもとになっているからだろう。多くの人にとっての「サクセス」のイメージは私だって知っているし、それ自体は間違いでも何でもないが、一人一人の人生はまた別の話じゃないか。人それぞれにもっと微妙で、多彩で、ヘンであってもいいものじゃないか。「勝ち組・負け組」なんて、人間をみるものさしとしてはロクなもんじゃない。あまりにも粗雑で幼稚で殺伐としたものじゃないか。ミもブタも無い。たとえ冗談だとしても、たいして面白いものじゃあない。要するに私はそういう二分法の「世間臭」を嫌悪しているのだろう……。
とまあ、そんなことしか考えられなかったのだけれど、橋本治さんの新刊『乱世を生きる 市場原理は嘘かもしれない』(集英社新書)を読んで、驚いた。
橋本さんもまた「勝ち組・負け組」的二分法への違和感から話を進めているのだけれど、私のように「どうでもいいじゃないか、そんなこと!」で一蹴したりはしない。「知性のあり方」の危機として問題視しているのだ。
私はこのこと自体がうれしい。こういうハヤリ言葉の根本を疑って、知性の問題として考えてくれる「言論人」なんて、実はめったにいないのだ。根本を疑わずに、「勝ち馬に乗れ」とばかり便乗する人が多いのだ。
橋本さんは、今は知性にとっての「乱世」だと言う。バブル壊滅後、いや、二十一世紀という時代は「従うべき理論が存在しなくなって、どう生きて行けばいいのかが分からない」、いわば知的な乱世で、そのために「勝ったか負けたか」という結果で判断するしかなくなった、と言うのだ。で、そういう中で違和感を抱く人間に活路はあるのか……?
まず「乱世」戦国時代を例にとって語られて行く。「勝ち組」戦国大名でも「負け組」守護大名でもないところに、私たちの活路を見出すとしたら、それは「戦火に踏み躙(にじ)られる農民」ではなく「朝廷」なのだ――という発想がいかにも橋本さんらしく、ハッとさせられる。
「勝ち組」小泉自民党に触れた章の「「便利』が加速すれば、破綻は近づく」という言葉にも。そして最終章の「『我慢』とは、現状に抗する力である」という言葉にも。
橋本さんの論理展開は相変わらず周到というか絢燗というか。論理的な足腰の弱い私は時どきヨロヨロしたが、「勝ち組・負け組なんて言い方、ビンボーくさい。そう感じてOKなのね」と、自分の感受性に力強い根拠を与えられたように思った。バレンタインデーにまつわる小話もいい。「経済」の意味を私はほとんど初めて好ましいものとして理解した。
【この書評が収録されている書籍】
「どうでもいいじゃないか、そんなこと!」
少し頭を冷やして考えてみる。私はいったい何に対して怒っているのだろう。どこがどう不快なんだろう。
一番に考えられるのは、「勝ち組・負け組」的二分法というのが、あくまでも世間的な価値基準がもとになっているからだろう。多くの人にとっての「サクセス」のイメージは私だって知っているし、それ自体は間違いでも何でもないが、一人一人の人生はまた別の話じゃないか。人それぞれにもっと微妙で、多彩で、ヘンであってもいいものじゃないか。「勝ち組・負け組」なんて、人間をみるものさしとしてはロクなもんじゃない。あまりにも粗雑で幼稚で殺伐としたものじゃないか。ミもブタも無い。たとえ冗談だとしても、たいして面白いものじゃあない。要するに私はそういう二分法の「世間臭」を嫌悪しているのだろう……。
とまあ、そんなことしか考えられなかったのだけれど、橋本治さんの新刊『乱世を生きる 市場原理は嘘かもしれない』(集英社新書)を読んで、驚いた。
橋本さんもまた「勝ち組・負け組」的二分法への違和感から話を進めているのだけれど、私のように「どうでもいいじゃないか、そんなこと!」で一蹴したりはしない。「知性のあり方」の危機として問題視しているのだ。
私はこのこと自体がうれしい。こういうハヤリ言葉の根本を疑って、知性の問題として考えてくれる「言論人」なんて、実はめったにいないのだ。根本を疑わずに、「勝ち馬に乗れ」とばかり便乗する人が多いのだ。
橋本さんは、今は知性にとっての「乱世」だと言う。バブル壊滅後、いや、二十一世紀という時代は「従うべき理論が存在しなくなって、どう生きて行けばいいのかが分からない」、いわば知的な乱世で、そのために「勝ったか負けたか」という結果で判断するしかなくなった、と言うのだ。で、そういう中で違和感を抱く人間に活路はあるのか……?
まず「乱世」戦国時代を例にとって語られて行く。「勝ち組」戦国大名でも「負け組」守護大名でもないところに、私たちの活路を見出すとしたら、それは「戦火に踏み躙(にじ)られる農民」ではなく「朝廷」なのだ――という発想がいかにも橋本さんらしく、ハッとさせられる。
「勝ち組」小泉自民党に触れた章の「「便利』が加速すれば、破綻は近づく」という言葉にも。そして最終章の「『我慢』とは、現状に抗する力である」という言葉にも。
橋本さんの論理展開は相変わらず周到というか絢燗というか。論理的な足腰の弱い私は時どきヨロヨロしたが、「勝ち組・負け組なんて言い方、ビンボーくさい。そう感じてOKなのね」と、自分の感受性に力強い根拠を与えられたように思った。バレンタインデーにまつわる小話もいい。「経済」の意味を私はほとんど初めて好ましいものとして理解した。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする