書評
『ある明治人の記録 改版 - 会津人柴五郎の遺書』(中央公論新社)
この連載では、できるだけ小説作品に限定して書くつもりでいたのだが……このニカ月あまりは奇怪な宗教集団のことで頭がいっぱいになってしまって、なかなか小説=フィクションものを読む気分になれなかった。現実に起こっていることのほうが濃いんだもの。(ALL REVIEWS 事務局注:本書評執筆年は1995年)
小説は読めなかったけれど、その代わり、幕末維新期にかんするノンフィクションものは何冊か読んだ。おもに中公新書で、『ある明治人の記録 会津人柴五郎の遺書』石光真人編著、『敗者の維新史 会津藩士荒川勝茂の日記』星亮一著、『戊辰戦争 敗者の明治維新』佐々木克編などである。
幕末維新期のことに興味を持つなんて、ほんとうにほんとうに自分でも意外で驚いてしまう。何しろ私は国民的大作家の司馬遼太郎さんの本を一冊も読んだことがない。NHKの大河ドラマ(維新の志士たちがよく登場するようではないか?)を今までに二、三回しか見たことがないという人間なのだった。
それがにわかに、この時代に興味を持つようになったのには、若干の理由がある。
以前、『ムテッポー文学館』(文藝春秋)の岡本綺堂の回に、私はこんなことを書いた。
岡本綺堂をはじめとして、私が好きな作家はたいてい旧幕臣の子どもだというのが偶然とばかり思えず、まったくいいかげんなカンだけでそんなことを書いたのだったが……その後、友人から「学者の山口昌男さんがおんなじようなことを考えているみたいだよ。戊辰戦争の延長線上で文学史をとらえ直して、『「敗者」の精神史』(岩波書店)というのを書いているよ」と教えられ、非常にビックリした。
やっぱり明治維新で負けた人たちの、独特の血の流れというのはあったらしいのだ。
あんまり私的な話になるのが厭で、そのときには書かなかったのだが、私が無意識のうちに旧幕臣系の、つまり敗者の側の文学に惹かれてしまうのは、どうやら私の家自体がその昔は幕臣で、新時代に乗れずに苦労した――というのがあるようだ。長い間、私は自分の家の過去について知らなかったが(父も祖父も、べつに何も言わなかった)、つい二年ほど前にひいおばあさん(安政六年生まれだ)の回顧録というのを読んで、うーん……(ちょっと大げさだが)自分の心の奥底に生まれて以来ずうっと巣くっている、ある苦々しさというもののルーツも、ある系列の作家に惹かれる理由も、だいぶわかったような気がしてしまったのだ。
ひいおばあさんの回顧録は簡単なものだが(原稿用紙十五枚程度)、それでも子孫の私には幕末の動乱がすぐそこに見えてくるような、生々しさで迫ってきた。それで、ひいおばあさんのことをもっと知りたくて、幕末維新期の敗者の記録を読み始めるようになったのだ。
前置きがついつい長くなってしまった。一連の記録の中で、私が最も心を揺さぶられたのは『ある明治人の記録 会津人柴五郎の遺書』である。
御存知のように、会津藩は明治維新に際し一方的に「朝敵」の汚名を着せられ、最も多くの犠牲を強いられた藩である。柴五郎は、その会津藩士の子どもで、会津落城のときにはまだ十歳(私のひいおばあさんと同じ安政六年生まれだ)。私は知らなかったが、その後、「脱走、下僕、流浪の生活を経て軍界に入り、藩閥の外にありながら、陸軍大将、軍事参議官の栄誉を得た逸材であり、中国問題の権威として軍界に重きをなした人」だそうで、昭和二十年に亡くなっている。この『ある明治人の記録……』は、柴五郎が亡くなる三年前に書きあげた少年時代の回顧録を、縁浅からぬ石光真人が編集整理したものである。
ショッキングな回顧録だ。
まず第一に、会津落城のとき、あえて家に居残った女たち(祖母、母、姉妹)が家に火を放ち、自刃したというのが凄い。
「(女たちは)この日までひそかに相語らいて、男子は一人なりと生きながらえ、柴家を相続せしめ、藩の汚名を天下に雪(そそ)ぐべきなりとし、戦闘に役立たぬ婦女子はいたずらに兵糧を浪費すべからずと籠城を拒み、敵侵入とともに自害して辱しめを受けざることを約しありしなり。わずか七歳の幼き妹まで懐剣を持ちて自害の時を待ちおりしとは、いかに余が幼かりしとはいえ不敏にして知らず。まことに慙愧(ざんき)にたえず、想いおこして苦しきことかぎりなし」――と、八十過ぎの老人になっていた柴五郎は、身悶えるようにして書いているのである。
第二のエピソード。会津藩士たちは、下北の辺地に移封され、寒さと飢えに苦しみ、犬の死体まで解体して食べるようなことになるのだが、そのとき柴五郎の父親は「武士の子たることを忘れしか。戦場にありて兵糧なければ、犬猫たりともこれを喰らいて戦うものぞ。ことに今回は賊軍に追われて辺地にきたれるなり。会津の武士ども餓死して果てたるよと、薩長の下郎どもに笑わるるは、のちの世までの恥辱なり。ここは戦場なるぞ。会津の国辱雪(そそ)ぐまでは戦場なるぞ」と激しく叱責した――というのには、まったく圧倒されてしまう。
ひとことで言えば、「武士道」――このモラルの徹底性に私は圧倒されてしまう。それも平時の空威張りなんぞではない、土壇場で発揮される「武士道」の強さに圧倒されてしまうのだ。「かなわないな」と思う。
精神の優位性を生き抜いてみせる――というのが、なんと厭味に、美しくまぶしいことだろう。「武士道」というのは、ちっぽけで限りのある時間しか生きられない「肉体」にたいする、「精神」の復讐行為のように思う。
例の宗教集団の首領は、警視庁の廊下で、「サムライは言いわけしない」と眩いたという。困った冗談を言う人である。私は快楽主義者で「武士道」のようなストイックな世界とは対極にいるが、そのこわさはわかるつもりである。その美しさはいつも気になってしまう者である。私の心の奥にある、何か苦いカタマリのようなもの――それは、もしかして、「私は武士道を生きられない」というところからも来ているのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
小説は読めなかったけれど、その代わり、幕末維新期にかんするノンフィクションものは何冊か読んだ。おもに中公新書で、『ある明治人の記録 会津人柴五郎の遺書』石光真人編著、『敗者の維新史 会津藩士荒川勝茂の日記』星亮一著、『戊辰戦争 敗者の明治維新』佐々木克編などである。
幕末維新期のことに興味を持つなんて、ほんとうにほんとうに自分でも意外で驚いてしまう。何しろ私は国民的大作家の司馬遼太郎さんの本を一冊も読んだことがない。NHKの大河ドラマ(維新の志士たちがよく登場するようではないか?)を今までに二、三回しか見たことがないという人間なのだった。
それがにわかに、この時代に興味を持つようになったのには、若干の理由がある。
以前、『ムテッポー文学館』(文藝春秋)の岡本綺堂の回に、私はこんなことを書いた。
もしかして、明治以降の日本文学史には、官軍側と幕府側の二つの血の流れが文学的体質の違いにつながっていて、えんえんと、そして隠然と戊辰戦争が続いていたりするんじゃないだろうか。そんなことはないか。しかし、私が岡本綺堂に惹かれるのは、何よりも『江戸直系』という感じがするところだ。どうも私は負けた側の気質のほうに共感してしまう――ということだけは確かだ。
岡本綺堂をはじめとして、私が好きな作家はたいてい旧幕臣の子どもだというのが偶然とばかり思えず、まったくいいかげんなカンだけでそんなことを書いたのだったが……その後、友人から「学者の山口昌男さんがおんなじようなことを考えているみたいだよ。戊辰戦争の延長線上で文学史をとらえ直して、『「敗者」の精神史』(岩波書店)というのを書いているよ」と教えられ、非常にビックリした。
やっぱり明治維新で負けた人たちの、独特の血の流れというのはあったらしいのだ。
あんまり私的な話になるのが厭で、そのときには書かなかったのだが、私が無意識のうちに旧幕臣系の、つまり敗者の側の文学に惹かれてしまうのは、どうやら私の家自体がその昔は幕臣で、新時代に乗れずに苦労した――というのがあるようだ。長い間、私は自分の家の過去について知らなかったが(父も祖父も、べつに何も言わなかった)、つい二年ほど前にひいおばあさん(安政六年生まれだ)の回顧録というのを読んで、うーん……(ちょっと大げさだが)自分の心の奥底に生まれて以来ずうっと巣くっている、ある苦々しさというもののルーツも、ある系列の作家に惹かれる理由も、だいぶわかったような気がしてしまったのだ。
ひいおばあさんの回顧録は簡単なものだが(原稿用紙十五枚程度)、それでも子孫の私には幕末の動乱がすぐそこに見えてくるような、生々しさで迫ってきた。それで、ひいおばあさんのことをもっと知りたくて、幕末維新期の敗者の記録を読み始めるようになったのだ。
前置きがついつい長くなってしまった。一連の記録の中で、私が最も心を揺さぶられたのは『ある明治人の記録 会津人柴五郎の遺書』である。
御存知のように、会津藩は明治維新に際し一方的に「朝敵」の汚名を着せられ、最も多くの犠牲を強いられた藩である。柴五郎は、その会津藩士の子どもで、会津落城のときにはまだ十歳(私のひいおばあさんと同じ安政六年生まれだ)。私は知らなかったが、その後、「脱走、下僕、流浪の生活を経て軍界に入り、藩閥の外にありながら、陸軍大将、軍事参議官の栄誉を得た逸材であり、中国問題の権威として軍界に重きをなした人」だそうで、昭和二十年に亡くなっている。この『ある明治人の記録……』は、柴五郎が亡くなる三年前に書きあげた少年時代の回顧録を、縁浅からぬ石光真人が編集整理したものである。
ショッキングな回顧録だ。
まず第一に、会津落城のとき、あえて家に居残った女たち(祖母、母、姉妹)が家に火を放ち、自刃したというのが凄い。
「(女たちは)この日までひそかに相語らいて、男子は一人なりと生きながらえ、柴家を相続せしめ、藩の汚名を天下に雪(そそ)ぐべきなりとし、戦闘に役立たぬ婦女子はいたずらに兵糧を浪費すべからずと籠城を拒み、敵侵入とともに自害して辱しめを受けざることを約しありしなり。わずか七歳の幼き妹まで懐剣を持ちて自害の時を待ちおりしとは、いかに余が幼かりしとはいえ不敏にして知らず。まことに慙愧(ざんき)にたえず、想いおこして苦しきことかぎりなし」――と、八十過ぎの老人になっていた柴五郎は、身悶えるようにして書いているのである。
第二のエピソード。会津藩士たちは、下北の辺地に移封され、寒さと飢えに苦しみ、犬の死体まで解体して食べるようなことになるのだが、そのとき柴五郎の父親は「武士の子たることを忘れしか。戦場にありて兵糧なければ、犬猫たりともこれを喰らいて戦うものぞ。ことに今回は賊軍に追われて辺地にきたれるなり。会津の武士ども餓死して果てたるよと、薩長の下郎どもに笑わるるは、のちの世までの恥辱なり。ここは戦場なるぞ。会津の国辱雪(そそ)ぐまでは戦場なるぞ」と激しく叱責した――というのには、まったく圧倒されてしまう。
ひとことで言えば、「武士道」――このモラルの徹底性に私は圧倒されてしまう。それも平時の空威張りなんぞではない、土壇場で発揮される「武士道」の強さに圧倒されてしまうのだ。「かなわないな」と思う。
精神の優位性を生き抜いてみせる――というのが、なんと厭味に、美しくまぶしいことだろう。「武士道」というのは、ちっぽけで限りのある時間しか生きられない「肉体」にたいする、「精神」の復讐行為のように思う。
例の宗教集団の首領は、警視庁の廊下で、「サムライは言いわけしない」と眩いたという。困った冗談を言う人である。私は快楽主義者で「武士道」のようなストイックな世界とは対極にいるが、そのこわさはわかるつもりである。その美しさはいつも気になってしまう者である。私の心の奥にある、何か苦いカタマリのようなもの――それは、もしかして、「私は武士道を生きられない」というところからも来ているのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
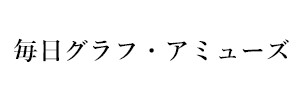
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする











































