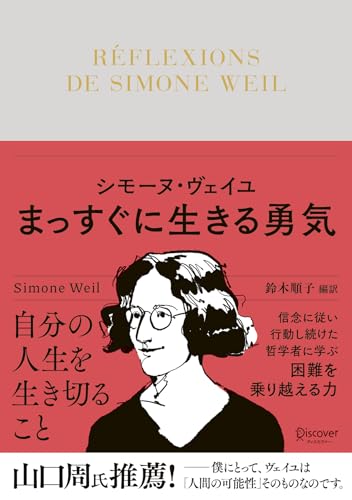書評
『悪魔のような女たち』(筑摩書房)
デカダン派の巨峰が描く魔性の美女
バルベー・ドルーヴィイと言っても、日本の読者にはとんと馴染みのない名前だろう。いや、かなりフランス文学を読み込んでいる人でも、名前だけで実際に作品を読んだことは少ないはずだ。しかし、十九世紀フランス文学の山脈では、その名は、デカダン派の巨峰の一つとして、ヴィリエ・ド・リラダンやユイスマンスなどよりもはるかに高く聳えたっている。ゆえに、今回、その代表作の中短編集が素晴らしい名訳で全訳された意義は大きい。
バルベー・ドルーヴィイの小説は、ノルマンディーの大貴族の末裔という小説家本人の家柄を反映してか、主人公が男女を問わず、恐ろしいまでに美しく、しかも驕慢であることを特徴としている。すなわち、男はダンディ、女はファム・ファタールと、まるで判を押したように決まっていて、他人の思惑に対してはあくまで無頓着に、己の欲望に対してはひたすら忠実に振る舞いながら、二人して「地獄の道行き」を敢行する。この意味で、バルベーはスタンダールとマンディアルグを結ぶ線上に位置するといえる。
具体的に語ろう。
まず『深紅のカーテン』。語り手は乗合馬車の中で、ブラッサール子爵という老ダンディと同乗する。とある宿屋の前に馬車が泊まったとき、ブラッサール子爵は深紅のカーテンで二重に閉ざされた窓から謎めいた光が漏れるのを見ると驚愕の表情を浮かべ、「なんと奇妙なことだ。いまでもおなじカーテンが掛かっているようだ」とつぶやいてから、三十五年前にカーテンの向こうで体験したまがまがしい恋の物語を語り始める。
新米少尉のブラッサール子爵は、部隊が駐屯していた田舎町の宿屋に下宿する。家主夫妻は想像しうるかぎりもっともブルジョワらしい人たちだったが、ある日、寄宿学校から戻ってきた一人娘を見て子爵は驚愕する。両親とは似ても似つかぬばかりか、ほかの人間とも隔絶した絶世の美女だったからだ。しかも、その態度たるや!
「ベラスケスの『スパニエル犬を連れたスペイン王女』という絵をご存じでしたら、この雰囲気を想像することができるかもしれません。高慢でも、軽蔑的でも、挑戦的でもない。違うのですよ! ただ単に無感動。高慢とか、軽蔑的とか、挑戦的な態度というのは、わざわざ蔑んだり、逆らったりすることで、相手の存在を認めているのですが、この女性の発散する雰囲気は、ただ静かに、こう言うだけです、『私にとって、あなたは存在しない』と」
ようするに、デカダン派が愛好する「つれなき美女」の典型として、アルベルト(アルベルティーヌ)は物語の中に登場してくるわけだが、この人物紹介(ポルトレ)の部分こそがバルベーの真骨頂で、小説好きとしては思わず「うまい」とため息をもらしたくなる。極端にいえば、バルベーはどうやって「つれなき美女」のイメージを読者の心に焼き付けるか、それだけに腐心しているように見える。
アルベルトは、ブラッサールなどまったく眼中にないように振る舞うが、ある夜、予期せぬ出来事が起きる。夕食のとき、隣に座ったアルベルトは両親の見えぬところで意外な行動に出たのだ。
テーブルの下で、私の手を、別の手がしっかりと掴んだのです。夢を見ているのかと考え……というより、なにも考えられなかったのです……。大胆な手がナプキンの下まで私の手を探りに来て、その手の信じられない感触だけが、私を捕らえていました! それは、いまだかつてなく、今後もけっしてありえないだろう感覚でした!
驚いたブラッサールが顔を見つめると、アルベルトは何げないしぐさでテーブルのランプのつまみをひねっている。食事が始まると、今度は足がブラッサールに触れてくる。アルベルトは表情一つ崩さずに「怪物のような大胆さでその男に身を任せてしまう」女だったのだ。やがて、アルベルトは両親が寝静まった後、ブラッサールの部屋に忍んでくるようになり、二人は愛の行為に没頭するが、ある夜、アルベルトは激しい痙攣の後で……。
このほか、動物園の黒豹の檻の前に完璧な美貌の男女が現れ、全身黒ずくめの大柄な女が、黒豹の鼻面をぴしりと叩くところから始まる女剣士オートクレールの物語『罪のなかの幸福』、夫のスペイン貴族の名誉を汚すため、あえて娼婦となって梅毒で死ぬシエラ・レオネ公爵夫人の悲劇を激烈に描いた『ある女の復讐』など、バルベー・ドルーヴィイという「デカダンの極北」を知るには恰好の中短編集である。
十九世紀フランス文学はバルザック、フロベール、ゾラだけではないのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする