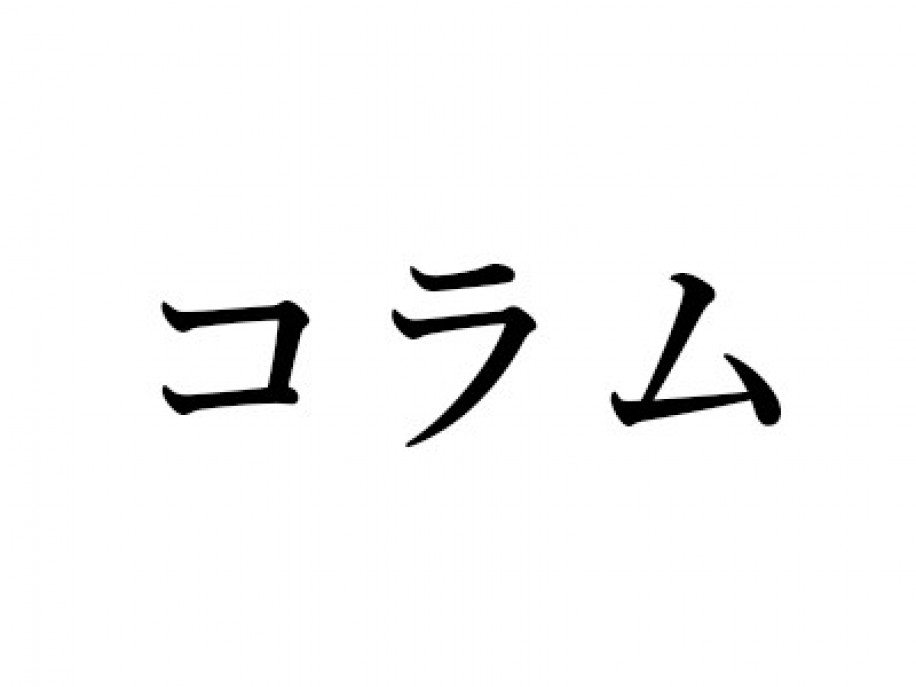書評
『「愛」と「性」の文化史』(KADOKAWA/角川学芸出版)
本稿を書いている最中、面白いニュースが飛び込んできた。アメリカのサンディエゴに在住するナタリア・ダイラン(偽名)という二十二歳の女性が、大学院の授業料を払うために、インターネットで自分の貞操をオークションにかけた。原文はvirginityだから、正確に言うと「処女」のことであろう。入札金がたちまち高騰し、一月十三日現在(二〇〇九年)、最高額の三百七十万ドルに達しているという。奇しくも当人は女性学研究の学位を持っているほどの才媛である。
「貞操」というと、いかにも時代遅れの観念のようだが、今日のアメリカのような性解放の国でもまだ売買できるとは驚きだ。単なる売春の話といえばそれまでだが、どうやら人間の情念というものはその一言で簡単に片づけられるものではない。そんなことを考えながら本書を読み返すと、いっそう興味がわいてきた。
かつて「貞操」という言葉をめぐって、大正期の言論界で一大論争が起きたことがある、近代恋愛の信奉者で、近世文学が嫌いな与謝野晶子は、平塚らいてうをはじめ『青鞘』の新しい女性を相手に文字通りの激論を戦わせた。「貞操」を無条件に礼賛する晶子の見解は、当時「過激」と見なされた「新しい女性」たちの観点よりも社会的な擁護を受けていた。だが、本質的には明治の近代恋愛がもたらした女性の性の抑圧を忠実になぞっている、と著者はその核心を鋭くついた。
俎上に載せられたのは与謝野晶子の「貞操論」だけではない。徳川時代から今日にいたるまで「愛」と「性」に関連する観念が文学作品のなかでどのように表象されてきたかという問題をめぐって、夥(おびただ)しい作品が批評の対象となった。御伽草子、人情本、謡曲、歌舞伎の役者評判記もあれば、森鴎外、谷崎潤一郎や現代の作家たちの作品もある。歴史を「近代」という概念で区分するのではない。江戸期から今日までの文化が一つの連続した時空として扱われている。この点において、歴史家のアンドルー・ゴードンの方法論(本書293ぺージ参照)を想起させるが、時系列に沿った叙述が放棄されたのは、あくまでも「愛」や「性」といった観念の誕生、変容、交差およびその相関性などに注目しているからだ。
一連の論考によって、近代の「恋愛」と江戸以前の「色事」のあいだの上下関係が転覆された、西洋起源の「恋愛」が文明で、近世の「色事」はモラルのない「放縦」とするのは表面的な理解に過ぎない。「恋愛」をめぐる近代以来の言論や文学テクスト群をよく吟味すると、なるほどそれは明治の知識人たちが創出した強迫観念に過ぎないことがわかった。一方、近世の「色事」もただ欲望の充足だけではなく、精神愛の感覚が男女関係にこめられている。その点について、現代の若者の恋愛が限りなく「色事」に近付いているという指摘は興味深い。ただ、著者は近世の価値観を無条件に理想化するのではない、現代人は「色事」から何か学ぶものがあるのではないか、と示唆するにとどまっている。
「愛」や「性」は、観念としてもまた社会的事実としても時代とともに大きく変化する。いつの時代の「愛」と「性」について語っているのか、つねに細心の注意を払わなければならない。 本書においてこの立場は始終一貫している。戦後社会について社会学の調査結果が援用されているのもそのためであろう。
巻末には周到にも高齢者の恋愛について一章が設けられている。小説やノンフィクションに描かれた黄昏の恋についての分析を通して、恋愛は時代とともに新たな展開を見せる実例を示している。心中論とともに興味をそそられる内容である。
【この書評が収録されている書籍】
「貞操」というと、いかにも時代遅れの観念のようだが、今日のアメリカのような性解放の国でもまだ売買できるとは驚きだ。単なる売春の話といえばそれまでだが、どうやら人間の情念というものはその一言で簡単に片づけられるものではない。そんなことを考えながら本書を読み返すと、いっそう興味がわいてきた。
かつて「貞操」という言葉をめぐって、大正期の言論界で一大論争が起きたことがある、近代恋愛の信奉者で、近世文学が嫌いな与謝野晶子は、平塚らいてうをはじめ『青鞘』の新しい女性を相手に文字通りの激論を戦わせた。「貞操」を無条件に礼賛する晶子の見解は、当時「過激」と見なされた「新しい女性」たちの観点よりも社会的な擁護を受けていた。だが、本質的には明治の近代恋愛がもたらした女性の性の抑圧を忠実になぞっている、と著者はその核心を鋭くついた。
俎上に載せられたのは与謝野晶子の「貞操論」だけではない。徳川時代から今日にいたるまで「愛」と「性」に関連する観念が文学作品のなかでどのように表象されてきたかという問題をめぐって、夥(おびただ)しい作品が批評の対象となった。御伽草子、人情本、謡曲、歌舞伎の役者評判記もあれば、森鴎外、谷崎潤一郎や現代の作家たちの作品もある。歴史を「近代」という概念で区分するのではない。江戸期から今日までの文化が一つの連続した時空として扱われている。この点において、歴史家のアンドルー・ゴードンの方法論(本書293ぺージ参照)を想起させるが、時系列に沿った叙述が放棄されたのは、あくまでも「愛」や「性」といった観念の誕生、変容、交差およびその相関性などに注目しているからだ。
一連の論考によって、近代の「恋愛」と江戸以前の「色事」のあいだの上下関係が転覆された、西洋起源の「恋愛」が文明で、近世の「色事」はモラルのない「放縦」とするのは表面的な理解に過ぎない。「恋愛」をめぐる近代以来の言論や文学テクスト群をよく吟味すると、なるほどそれは明治の知識人たちが創出した強迫観念に過ぎないことがわかった。一方、近世の「色事」もただ欲望の充足だけではなく、精神愛の感覚が男女関係にこめられている。その点について、現代の若者の恋愛が限りなく「色事」に近付いているという指摘は興味深い。ただ、著者は近世の価値観を無条件に理想化するのではない、現代人は「色事」から何か学ぶものがあるのではないか、と示唆するにとどまっている。
「愛」や「性」は、観念としてもまた社会的事実としても時代とともに大きく変化する。いつの時代の「愛」と「性」について語っているのか、つねに細心の注意を払わなければならない。 本書においてこの立場は始終一貫している。戦後社会について社会学の調査結果が援用されているのもそのためであろう。
巻末には周到にも高齢者の恋愛について一章が設けられている。小説やノンフィクションに描かれた黄昏の恋についての分析を通して、恋愛は時代とともに新たな展開を見せる実例を示している。心中論とともに興味をそそられる内容である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする