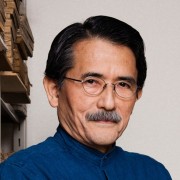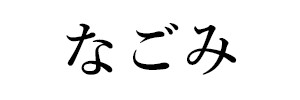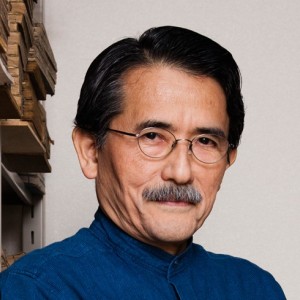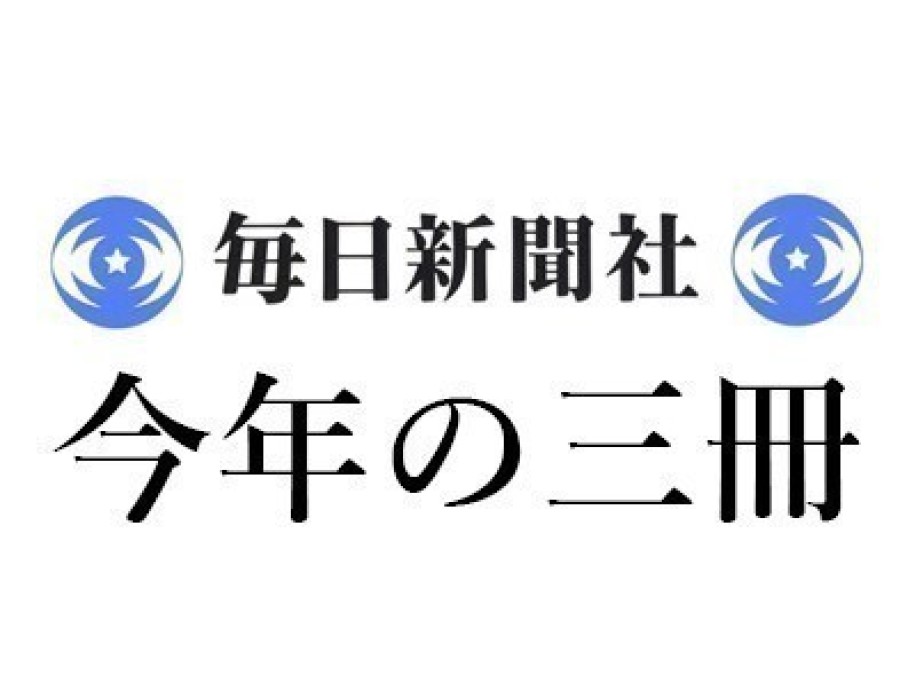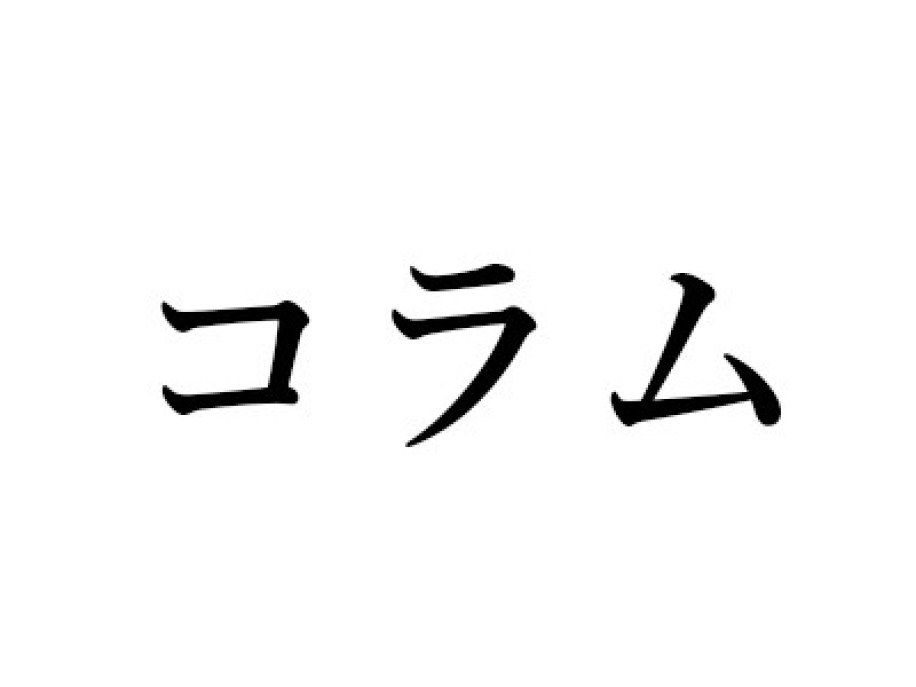書評
『蕪村全句集』(おうふう)
心を澄ます工夫
壁隣ものごとつかす夜寒哉
蕪村の句である。秋も深くなり、夜長の感慨ひとしおのころであろうか。いねがてに、その夜長を起きていると、貧しい長屋なのであろう、壁一枚隔てた隣戸に、この夜更け、なにやら、ゴトンゴトン、ガタリゴトリと物を動かしている音がする。そんな音は聞きたくもないけれど、こうあたりが寝静まってしまうと、いやでも耳に入ってきてしまうのだろう。たいした調度もない暮らしぶり、所詮一升桝は一升桝ながら、なけなしのタンスやら火鉢やらを、えんやらえんやら動かすと見える。そのことを、句の作者は、ただ音だけで想像している。あるいは、ようやく寝た夜更けに、なにをするやら、隣戸から聞こえる音に目が覚めてしまったということかもしれぬ。ちょっと不機嫌の趣をにおわせながら、しかし、句の面には怒りも不満の声もなく、ただ「ものごとつかす」という突き放したような言い方で、かるい舌打ちでもしているらしい気配をにおわせる。この程度だからいいのである。そうして最後に「夜寒哉」と止め、一人この秋の夜更けに起きていると、あるいは目覚めてみると、我が身の寒さが、いっそう沁みてくる、と呟く感じである。たぶん隣の家は夫婦者で、二人でせっせと大物を動かしているのかもしれない。それにくらべて、壁のこちらは寂しい一人寝と読んだら、いっそうもののあわれが色濃い。
私は蕪村の句を愛する。芭蕉よりも一茶よりも、やっぱり蕪村が良い。蕪村の句には、独特の色がある。どんな色か、と言われても、にわかには説明できぬ。説明の代わりに、この本を座右に備えられることをお勧めするのである。難しい句は、蕪村にはあまりない。それでもちょっと取っ付きにくい向きもあるだろう。しかしこの本には、簡略にして要を得た注釈やら、正確な出典やらがきちんと備わっている。句は季節ごとに季題ごとに類題されているから、その折々に当季の景物を探って、あれこれと句を眺めているのは、頗るの妙境である。
ひとり来て一人を訪ふや秋のくれ
こんな句もある。一人寂しく暮している亭主を、これも独り身の客が訪うた。おそらく、連れ合いに先立たれてのやもめ隠居か、風流の隠士かもしれぬ。石川丈山と下河辺長流でも想定しておけばよかろうか。ともあれ、一見ごく寂寞たる句柄のようでいてそうでない。そこには、一期一会とでも言いたいような、ほわっとした温かい気分が僅かに見える。客と主人との清らかな交わりと、邪気の無い笑顔が、この17文字の小天地に封じ込められ、なお「秋のくれ」と止めたことによって、豊かな色彩が与えられているように読める。見事な句である。
こんなふうに、髄時、好きなところを眺めては、その句の奥の景色を眺めやる。これが心の安息であり、心猿をてなづける工夫でもある。
いかにもいかにも、蕪村は、善い。
ALL REVIEWSをフォローする