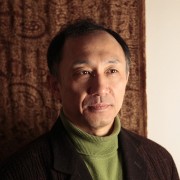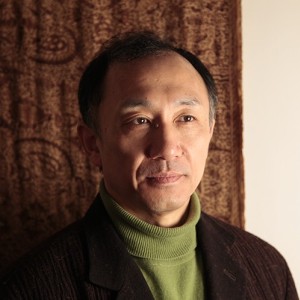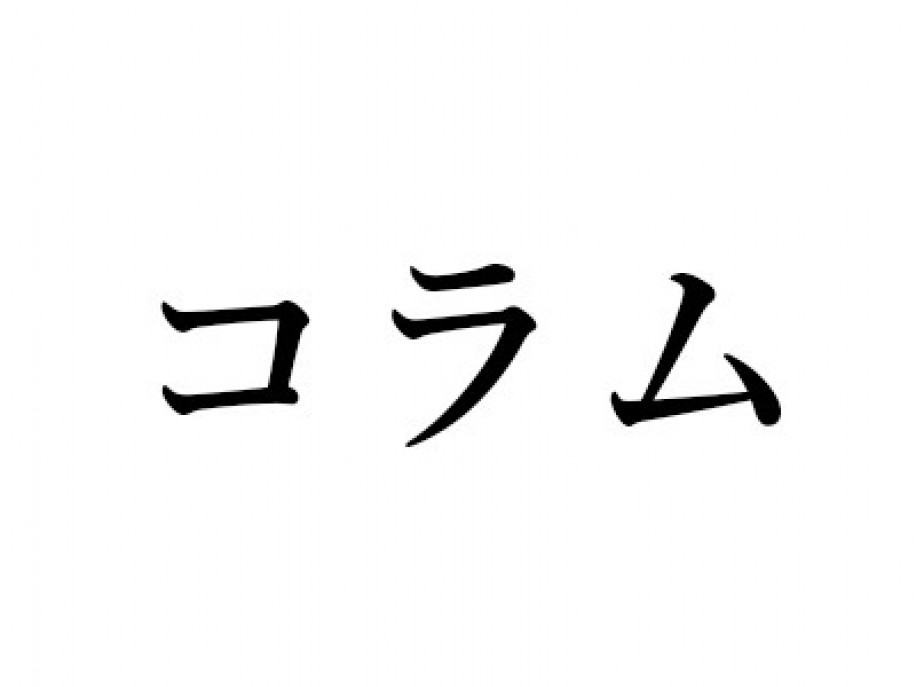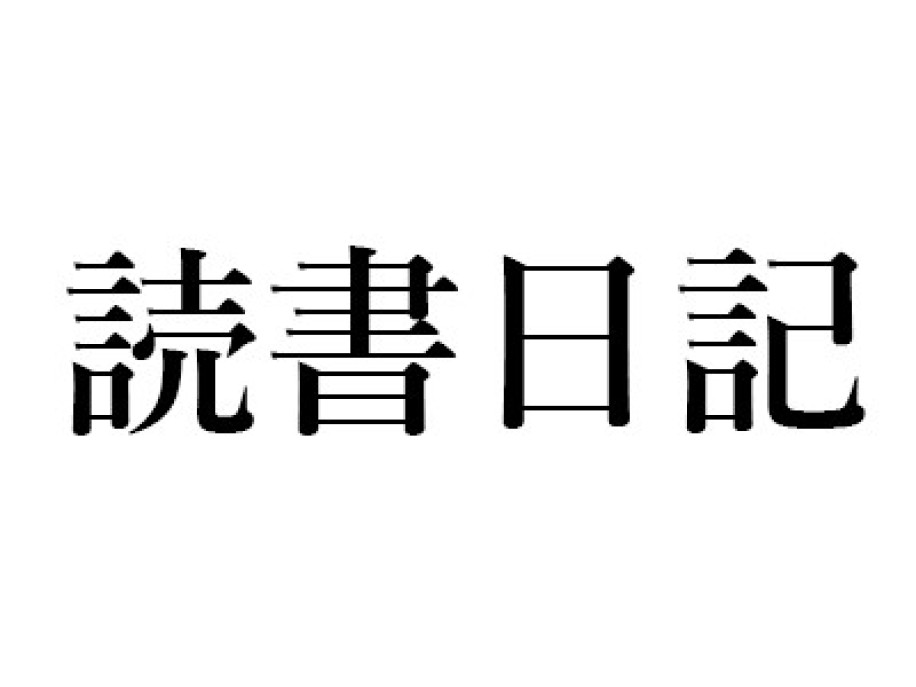書評
『ジョブ・クリエイション』(日本経済新聞社)
90年代以降、雇用の驚くべき現実描く
官民の様々な機関が景気の回復を報じている。けれども多くの国民は、「実感がない」と言っている。研究者と生活人の間にそうした視線の差をもたらす一因が、雇用問題だ。九○年代から続く「失われた十年」の原因につき、研究者たちは不良債権や金融緩和不足を挙げ、侃々諤々(かんかんがくがく)の空中戦を繰り広げた。だが当たり前のように論じられた理屈にも、生活人にとって最大の問題である「雇用」から言えば意味不明のものが多い。あれだけ議論された不良債権にしても、せいぜい十万人の失業しか生んでいないらしい。力の入れどころがおかしいのではないか。
そう感じる人にとって、これは待望の書だ。研究者の間で曖昧(あいまい)に前提されてきた言葉や仮説の意味をとらえ返し、膨大なデータをいくつもの角度から執拗(しつよう)に検討して、依然として深刻な足下の雇用問題を、ありのままの姿で描き出そうとする。研究書ゆえに厳密な論証やデータが掲載されてはいるが、一般読者は飛ばして読めばよい。結論は分かりやすくまとめられており、九〇年代以降の雇用問題の驚くべき現実が浮かび上がってくる。
列挙しよう。仕事を失ったのは、被雇用者というより自営業者だった。中高年のリストラが注目されてきたが、むしろ若年の就業が危機に瀕(ひん)している。人材育成には費用がかかるから中小の優良企業は放棄したかというとさにあらず、人材育成に力を注ぐ企業ほど成績を上げ、雇用も創(つく)り出している。雇われる人材の特徴としてしばしば年齢や技能が挙げられるが、「営業力」こそが求められ、それは詰まるところ「やる気」と「人柄」である、等々。
転職には賃金や履歴などうわべの情報を交換するだけでは不十分で、過去の取引先やボランティアで知り合った人との交わりなど私的ネットワークから得た深い情報こそ重要だ。年齢や技能だけではない、「心のミスマッチ」こそが深刻なのだから、と著者は言う。それを埋める人的ネットワークの構築が急務だと説き、雇用において「希望」のありかを描こうとする最終章は、感動的だ。
朝日新聞 2004年5月2日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする