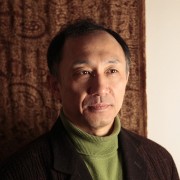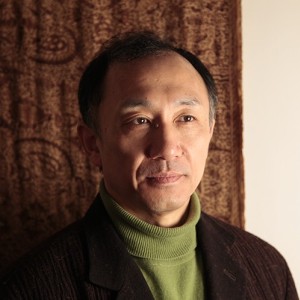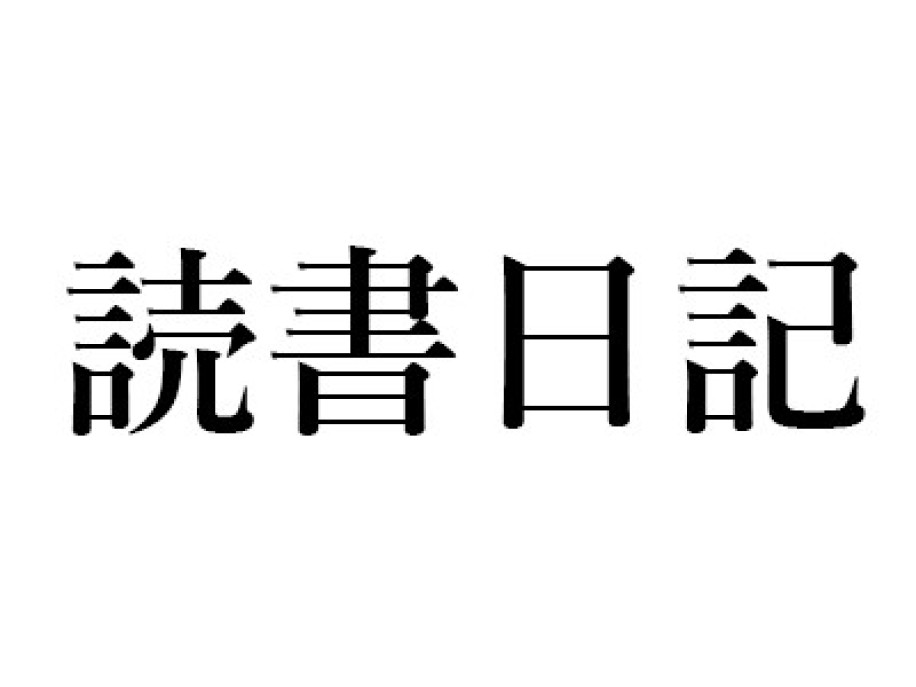書評
『倫理としてのナショナリズム―グローバリズムの虚無を超えて』(NTT出版)
新たな経済状況に即し公共心の再興を
経済のグローバル化が進み、日本のメーカーが中国に工場を移転させるといった現象はありふれたものとなった。情報技術(IT)を用いた株取引によってライブドアがフジ・ニッポン放送という既存メディアを脅かしている(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年)。何百億円を数年で儲(もう)ける青年実業家と最低賃金ももらえないフリーターという具合に、所得格差も拡大している。こうした時代には、政策はどんなものになるべきか。ここ十年来、二つの基本方針が挙げられてきた。国家主導のケインズ主義や福祉主義が赤字財政を招いたということで、小泉政権はグローバル化に対応すべく、リバタリアニズム(自由至上主義)を「構造改革」の名で導入した。これに反対する側も、国家には頼れないことから、NPOや地域経済、セーフティーネットに期待をかける「第三の道」型のリベラリズムを模索してきた。それに対しナショナリズムや倫理を持ち出すのは、いかにもアナクロに見えるだろう。
だが著者の思索は、見かけの何歩も先を踏破するものだ。リバタリアニズムといいリベラリズムといい、ともに高度成長期を経て形成された「中間層」やそこに内包される公共心を前提しており、グローバル化・IT化の下でそれらが融解したのだから、無効となったというのだ。なるほど高給を得ながら外国で税を払い、放送網を取得しようとしながら利用目的を説明しない現代のエリートたちは、公共心を失っている。
多くの著作の集大成として打ち出す結論は、グローバル市場と地域経済を媒介させるような公共心を国家レベルで再興させることである。それが経済の新たな現実に即した「市民的(シビック)ナショナリズム」であり、旧時代の排他的・均質的な国家主義とは異なる。
ただし本書には、ITといえば没意味的で不道徳なコミュニケーションしかもたらさないという見方が色濃いようだ。それは半面の事実ではあるが、新しい市民倫理の醸成にはパーソナルメディアがかかわらざるをえないだろう。マスコミは市民相互の「承認」や「称賛」に向かなくなっているからだ。
朝日新聞 2005年2月27日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする