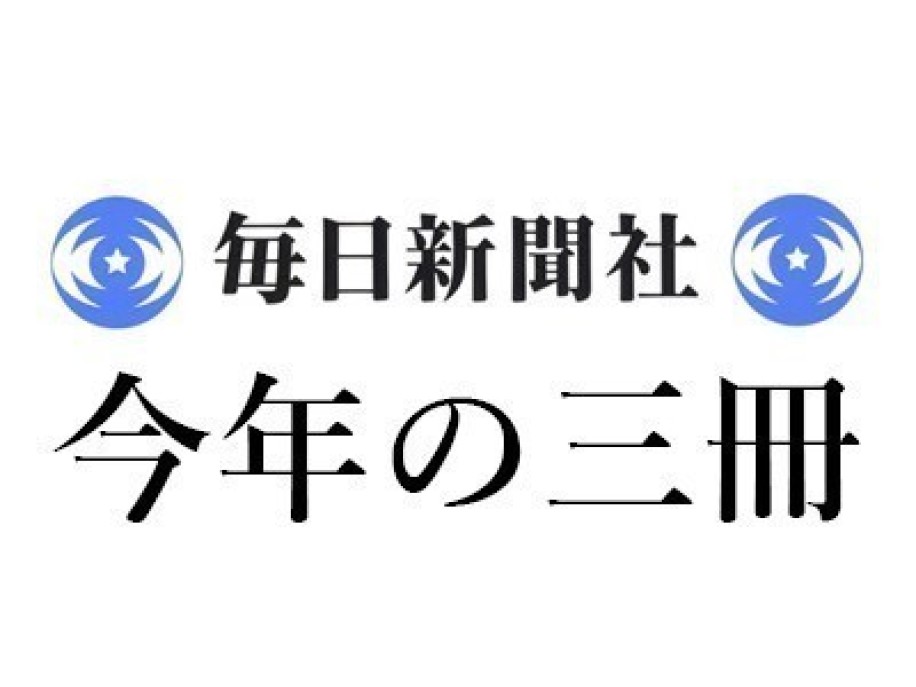書評
『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生』(柏書房)
衰弱する社会関係資本
豊かさが庶民に及んではいなかった時代の日本では、都会で職を失った人々は、一時的に帰郷し、実家や親戚に身をよせ待機した。近隣同士は落語にでてくる長屋の住人のように、相身互いと助けあった。濃密な人間関係の息苦しさを代償にしてではあったが、悲惨をのりきるインフォーマルな互助制度が強く作動していた。本書は、米国をベースにして、このような人々の間の互酬性(贈与の交換)の量と質の変動とその帰結を、全米各地の文書館などから収集した膨大なデータをもとに分析している。クリントン大統領の一般教書演説にも影響をあたえた話題の書である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2006年5月)。
著者は、この互酬性の規範を社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)と呼ぶ。人々が返礼をくりかえすことで、社会的ネットワークが更新・持続される。かくて人脈関係が市民的インフラ(資本)となるからである。悩みをかかえたとき相談する人がいるかいないかで個人の不幸度はかわる。地域社会に絆(きずな)があれば、安全性も高まる。しかし、本書は社会関係資本が一貫して減少してきた式の単純なノスタルジー史観を展開しているわけではない。地域社会の活動への参加率や参加形態などの時系列データの徹底的な解読によって、20世紀初期3分の2時代は社会関係資本の上げ潮で、70年代から衰弱してきたとする。テレビや郊外化、世代変化などを社会関係資本の減少原因とする70年代犯人説は日本でも検証してみる価値が十分ある。格差社会是正の手立ては所得再分配などの経済問題だけにとどまらない。社会関係資本(信頼にもとづく互酬性)を豊かにすることがセイフティネットになることが示唆されている。
題名は、米国でリーグボウリング(地域でのチーム対抗試合)が減ってきたことから、社会関係資本衰弱の象徴現象としてつけられている。軽妙洒脱(しゃだつ)ないいまわしをはさんで、600頁(ページ)の読書マラソンを完走させる筆力がすごい。柴内康文訳。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする