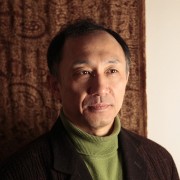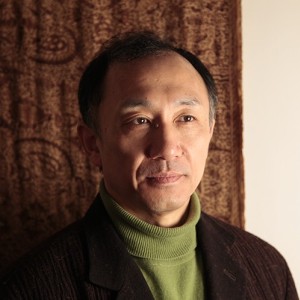書評
『途上国ニッポンの歩み―江戸から平成までの経済発展』(有斐閣)
ビッグバンより漸進主義で「和魂洋才」
日本経済の通史に関心のある読者は多い。それでいて、一般読者の知的好奇心に応えうる書物は少ない。なぜだろうか。さまざまな史実につき、学界では無数の解釈が示され、論争が繰り広げられているのだが。一因として、おのおのの解釈を列挙しても「点」が並ぶにすぎず、歴史という「線」にならないことがある。「線」をかたどるには一定のビジョンが必要になるが、マルクス主義の革命史観には往時ほど共感が寄せられていない。
留学生向けの講義録だというが、ビジョンを提示するために著者が行った工夫は秀逸だ。ひとつには、開発のアドバイザーという立場を利用して、極東の農業国から最先端の工業国へとたどった日本を途上国に見立て、個々の経験を評価している。幕末期に多くの藩がすでに経済発展していたのに、江戸期の長者231人のうち維新を経た半世紀後には20人しか地位が維持できなかったという、豪商が明治産業化の担い手ではなかったことを示す記述などは、近代史がすでに疎遠なものとなった日本の読者にも、新鮮な驚きをもたらすだろう。
いまひとつの工夫が、途上国は外国から与えられたインパクトをそのままで受け止めず、従来のシステムと、主体的に統合してやることで発展できるという「翻訳的適応」の考え方である。明治維新では、産業化や民主化といった洋才をいかに天皇制や日常心理という和魂につなげるかが問題となった。
だが適応には時を要する。近代化に悩んだ漱石の講演が引用され、時が熟するのを待つ「漸進主義」が、一気の適応をめざす「ビッグバン」よりも好意的に紹介されている。いまだ封建的な民衆に合わせて立憲君主制を唱えた大久保と、人心の刷新を説いた福沢の相違は、この点にあるという。
IMFの勧告通りに財政緊縮を導入すべきだと結ぶように、ここ10年の改革に関しては「漸進主義」は支持されないが、会計ビッグバンに端を発したIT長者のメディア買収への世論の反発なども、同じ図式から考えてみたくなる。
朝日新聞 2005年4月24日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする