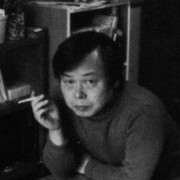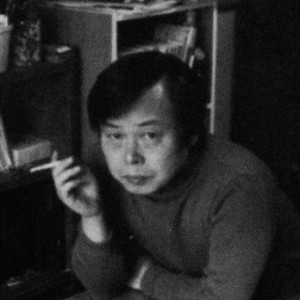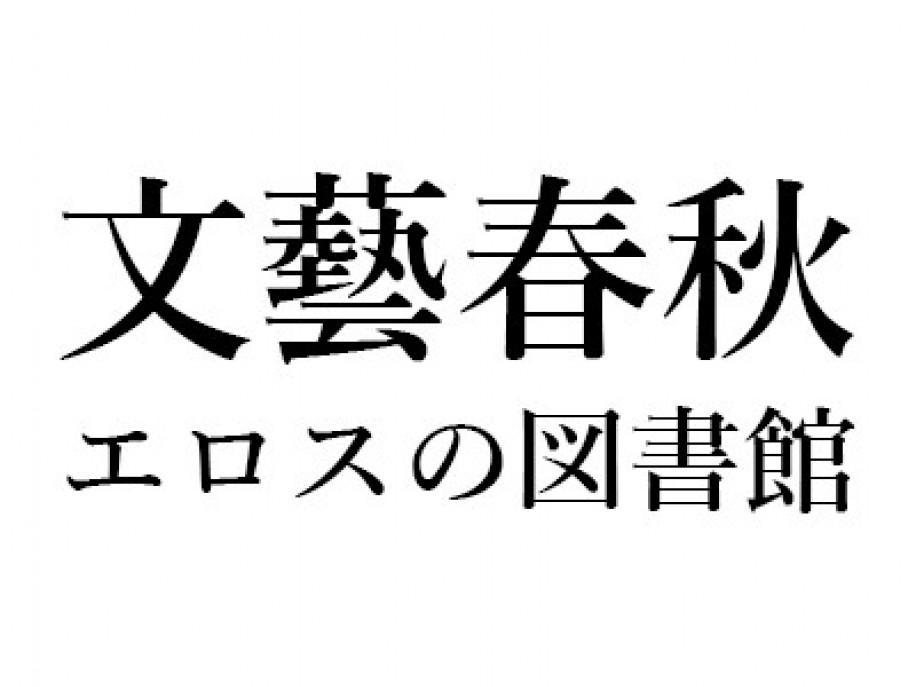書評
『絵本未満』(大和書房)
ふきんがこわい
ふきんと書いてあるふきんがあったそうだ。それをロシア、ヨーロッパから帰ったばかりの映画監督が見て、これが日本のやさしさだといった。ふきんとふきんでないものの差異が、いちいち断るまでもなく論理的に露出している精神風土から帰ってきて、ふきんはふきんであるというトートロジーが綿のようにぬくぬくくるみこんでくる日常が、パッと見えた。さて、どうするか。映画監督とそれをそばで見ていた甥(おい)の少年が考えこんだ。映画監督のほうは先ごろ物故した浦山桐郎氏、居合わせた甥がこの本の著者だった。そうかと思うと、1枚の絵にひと月かけて、「気の遠くなるような時の流れを絵本の中に閉じ込める」坊主頭の絵本作家が登場してくる。「海底深く沈んでいった鳥たちの屍(しかばね)の山がやがて水面に届き、遠くをめざす若鳥が羽根を休める小さな島になるという」やさしい話を描く人だという。
つまりは、やさしい本である。しかしこのやさしさには、ふきんと書いてあるふきんに外側から気がついてしまった人間の、残酷さもふくまれている。だから後半になると、ふきんからふきんがはがれて、それが出刃包丁を持ちだして人を殺しにさまよい出る、コワイ話がぬっとあらわれたりもする。著者は生まれてまもなくヒ素粉ミルクで死にかけたのだそうだ。あらためて表紙絵を見ると、哺乳(ほにゅう)瓶を手にして涙をぽろぽろこぼしている自画像である。哺乳瓶のなかは、やさしいミルクなのか、殺す毒なのか。シャツの胸には骸骨(がいこつ)とばら、首には十字架のペンダント。生と死、絶望と希望がどこまでもぶっちがいになって、ひょっとするとこの哺乳瓶は、十字架上のキリストを刺す槍(やり)なのかもしれない。
そういうこわくてやさしいふきん、哺乳瓶や、こわくてやさしいふきん、哺乳瓶みたいな人たちが、ナイーヴにひらかれた本のなかにつぎつぎに立ち現れる。著者のいう「多声構造」だ。それで、いくつもの声がいつまでも発声して終わらないから、「絵本未満」。ときどき1つの声だけが暴走したりもする。それを見て、対話者の1人スズキ・コージがいった。「でも、気ながにやるしかないって思うんだけどね」
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1990年5月20日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする