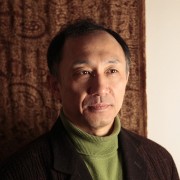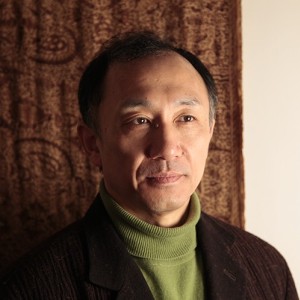書評
『マオ―誰も知らなかった毛沢東 上』(講談社)
抗日戦の神話も嘘? 議論呼ぶ新説が続々
毛沢東が1949年の建国の後に、60年前後の「大躍進」でとてつもない飢饉をもたらし、60年代の「文化大革命」で粛清を行い数千万の人民を死に追いやったことは、これまでも紹介されてきた。李志綏(リーチーソイ)『毛沢東の私生活』のように、身近な見聞から食欲や性欲にだらしない男として描いた暴露本も何冊かある。中国共産党にしてからが、文革の「誤り」は公式に認め、建国以前の輝かしい「功績」がそれを超えているのだというレトリックを用いている。学界でも、毛は闘争の論理や「農村による都会の包囲」の戦略を駆使して建国にこぎつけたものの、都市生活者による経済発展は実現できなかったとされている。それだけに、文革期の一家庭が翻弄される様を哀切込めて描きベストセラーとなった『ワイルド・スワン』の著者が十年の歳月をかけ送り出した毛沢東伝とはいえ、なお破壊できる偶像なぞあるものかとまず思ったのだが、そんな先入観は、上巻で吹き飛んだ。建国以前の「功績」をすべて爆破し去ろうとするかのように、挑戦的な新説が、ページを繰るごとに現れるのだ。英雄的な長征の果てにたどり着いた延安を拠点に、愛する農民とともに抗日戦争を闘ったという神話は、真っ赤な嘘だというのである。
毛は自己愛に取り憑かれたサディストで、共産主義にさして共感せず党の創立時のメンバーでもなく、長征はたんなる敗走、蒋介石打倒の目標に向けては日ソと結んで中国の分割をも模索し、自軍である紅軍も野心の生け贄として、党員や支配地の農民は残虐な拷問と略奪・処刑によって恐怖で縛り上げた、と言うのだ。スターリンは毛の野心と残虐性に共感し、対日戦争回避のために利用したのだという。毛と張学良、スターリン、介石蒋のやりとりが本当なら、20世紀の国際関係史は根本的に見直しを迫られる。共産主義にも最終的な判決が下されるだろう。問題作であることは間違いない。
日本関係では、張作霖爆殺はスターリンの策謀だと示唆しており、遠藤誉『チャーズ』で知られた八路軍の長春包囲作戦による33万人の餓死事件は、毛沢東が直接に指揮したものと指摘する。中国公式発表の南京大虐殺犠牲者数を上回る数字である。もっとも、「大躍進」3800万の犠牲者も毛は軍事大国化の代償と認識していたらしく、数字が空しく思えてくる。
本書の生命線は、数百人におよぶ関係者へのインタビューと中国・旧ソ連の初出アーカイブ文書。とはいえ、どれほど多くの一次データを掘り起こしても、解釈は他にも可能である。すでに内外の学界で批判が出ているが、父の仇か全責任を毛に負わせて人民を免責する決め打ち風の新説には疑問も多い。百倍もの戦力を有する国民党に勝利した理由を、人民が理想に燃えたからと見るのなら理解できるが、恐怖と偶然だけでは説明として納得しかねる。「人民の敵」を処罰する得意げな紅衛兵の写真を見ると、毛は人民に潜在する破壊衝動を引き出す天才だったのでは、という気がする。
朝日新聞 2006年1月15日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする