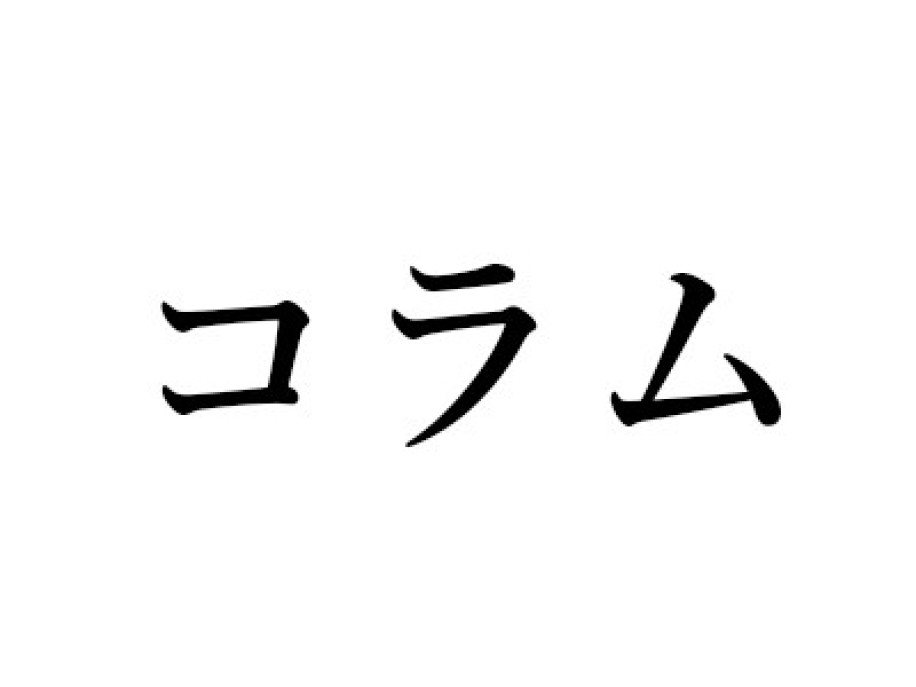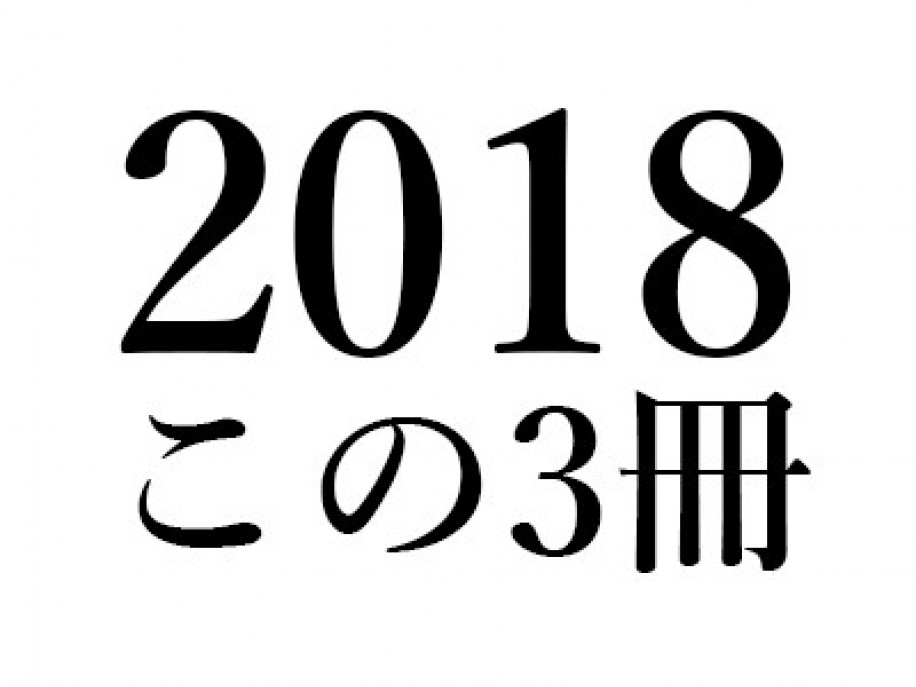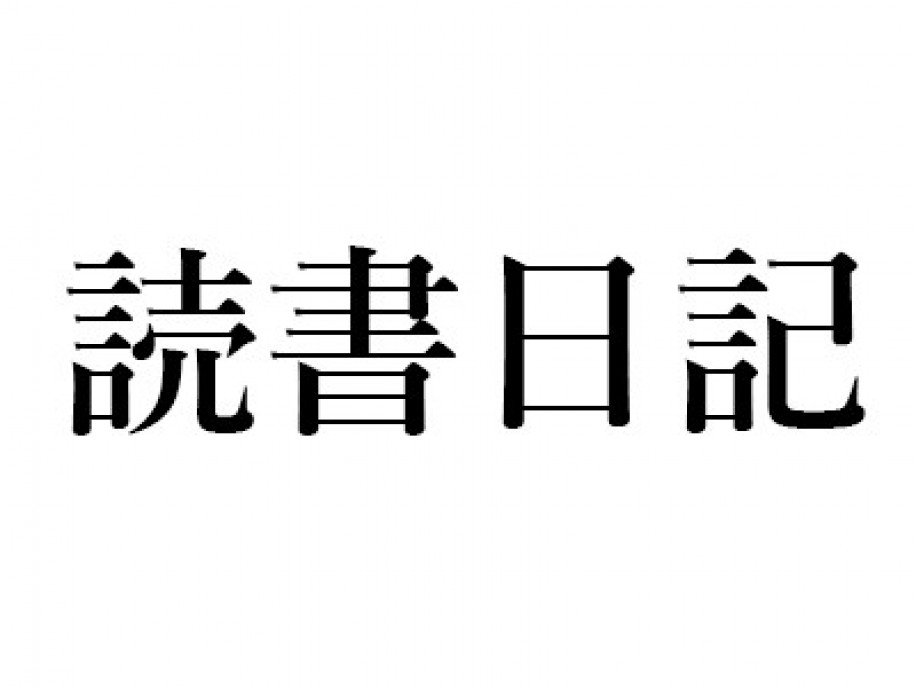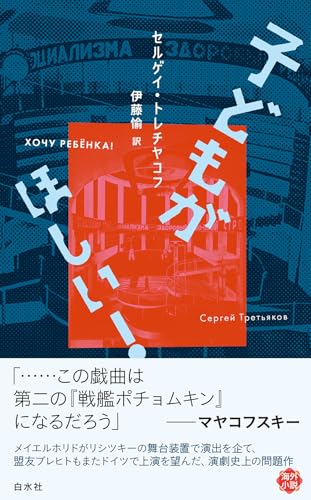書評
『1945年に生まれて──池澤夏樹 語る自伝』(岩波書店)
理系の素養まで併せ「何ものにも自由」
池澤夏樹という名前を初めて見た時、鬱蒼(うっそう)とした森を爽やかな風が吹きぬけてきたような気がした。それから四十年、この世界文学の健脚の旅人は、日本文学の自足的な「私」の淀(よど)みを世界に向けて開く若々しい力であり続けてきたが、いつの間にかこの夏に満八十歳を迎えた。池澤氏は一九四五年の夏生まれなので、文字通り戦後八十年の日本とともに歩んできた。本書はこの節目に、文芸評論家、尾崎真理子が聞き手となって、作家に自らの生涯を語ってもらった「自伝」である。語りは帯広と東京で過ごした幼少期から始まる。父は高名な作家、福永武彦、母は詩人、原條(はらじょう)あき子。しかし両親はやがて離婚。福永は「愛と孤独と死」を描くロマンで一世を風靡(ふうび)したが、池澤氏は「福永の文学をどこかで認められない」と率直に語る。一方、女性に囲まれて育ったため、十分に活躍する機会を与えられなかった母や叔母の「恨みを預かって、ぼくは今でも戦闘的フェミニスト」だと自認する。実際、後の池澤氏の小説には矜持(きょうじ)が強く、恋愛より自分の仕事を優先するカッコいい女性がしばしば登場し、新しい女性像の先駆けとなった。
理科系の学問を志しながら大学での勉強に途中で見切りをつけた池澤氏は、「入社試験のない」自由な生き方を選び、日本を飛び出してミクロネシアなど南洋の島々に足しげく通い、さらにギリシャに移住。カヴァフィスの詩やアンゲロプロスの映画に出会う。その後も、経済成長ばかりを追求する日本から距離を置いて、沖縄、フランス、北海道と次々に住処(すみか)を変え、自由と移動を基調とした生き方を貫いた。こうして南洋の島を舞台にしたマジックリアリズム的長編『マシアス・ギリの失脚』や、沖縄の米軍基地とベトナム戦争を背景にした『カデナ』、原爆開発を扱った『アトミック・ボックス』、さらに北海道開拓史とアイヌ問題を取り上げた歴史小説『静かな大地』などの傑作が次々と生み出された。
池澤氏は社会や政治を論じる作家が減ってきた現代日本では、稀(まれ)に見る社会派だが、決して文学を政治に従属させているわけではない。若い頃から皆と一緒にデモに参加するような集団行動は嫌いだったが、内心「最後まで左翼なのは俺だぞ」という自負を保ち持った。「池澤さんは最初から一貫して、主人公からも宗教からも十分、距離を保って」きたと言う尾崎氏に対して、池澤氏は「何ものにもとらわれたくなくて、自由でいたいんでしょう。どんな意味でも小説をプロパガンダにしたくない。ぼくにとって、文学が神様ですから」と鮮やかに応えている。
池澤夏樹は理科系の素養と繊細な詩情を溶け合わせた明晰(めいせき)な文体を創出し、百科全書的な博識に拠(よ)って文明批評の論陣を張り、「社会と世界の動きを見渡して」「コンビニから難民まで」を視野に入れた小説を書き、個人編集『世界文学全集』『日本文学全集』によって文学の新しい羅針盤を示した。その営為を尾崎氏は、「この四十年、時代の指標」だったと呼ぶ。池澤さん、長いこと本当にお疲れさまでした。でもまだ「総括の時期」なんて言うのは早いですよ。世界がますますおかしな方向に向かいつつある今、私たちはもっと池澤夏樹の声を必要としているのですから。
ALL REVIEWSをフォローする