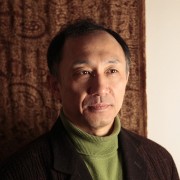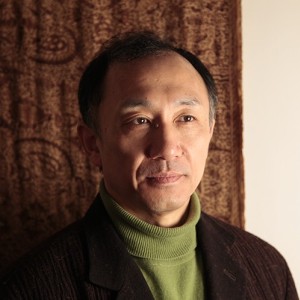書評
『貨幣という謎 金(きん)と日銀券とビットコイン』(NHK出版)
「観念の自己表現」としての貨幣論の先へ
1990年代初頭に資産バブルが崩壊してからというもの、日本経済は「失われた二〇年」の長期不況をさまよい、安倍政権はインフレを意図的に起こそうと金融緩和を試みている。一方、世界経済は金融商品の規制緩和や機関業務の自由化、統合通貨ユーロの誕生を経て、リーマンショックや欧州ソブリンショックに見舞われた。つまりこの四半世紀というもの、デフレや金融危機、バブルや通貨統合と、経済は貨幣的な現象をめぐって揺れ動いてきた。それゆえ経済政策は、もっぱら有効な貨幣の供給の方法を中心に激しく議論が交わされてきた。しかし政策という応用技術の背後で経済学が「貨幣」をどう理解したかとなると、深い洞察は加えられなかったと言わざるをえない。経済学の教科書では、すべての分野で同時に需給が均衡する「一般均衡」が、理想であるとともに現実でもあるとみなされている。すべての財につき物々交換が行われうるということであり、そこで貨幣は添え物にすぎない。
著者はそうした市場観を「一極集中的」と呼ぶ。それが現実とかけ離れているのは、「お金で物を買う」という誰もが日々体験する現象が、重視されていないからだ。売り買いや取引は、同時かつ集中的には行われない。コンビニや魚河岸や銀行決済での取引は、別々の所と時でバラバラに、しかしゆるやかな繋(つな)がりをもって実行される。市場とはそうした行為のネットワークであって、ハイエクが言うように「分散的」でしかありえないのだ。
著者は前半でこう述べ、「貨幣とは何か」を抽象的に論じつつも、リアルな経済の大海に漕(こ)ぎ出す。「貨幣の哲学」を論じながら、「円天」詐欺事件やビットコイン取扱企業の破綻といった生の事件をも俎上(そじょう)に載せている。
貨幣は金銀といった「もの」(素材)から離れカードのデータのような「こと」(情報)と化しつつある。それはまた預金が決済にも使われるという意味では、「信用貨幣化」でもある。そのように貨幣が様々な形をとりうるのは、他の人が受け取ってくれると信じて自分も受け取り、実際に他人がそれを受領してくれるという「観念の自己実現」が成り立つからだと著者はいう。
貨幣とはみながそれを貨幣だと思うから貨幣なのだという貨幣論は、岩井克人氏が先鞭(せんべん)をつけたものである。王様は、子どもが「王様は裸だ」と叫ぶまでは裸ではないことになっていた。著者の工夫は、それを疑いを差し挟む可能性のある「予想の自己実現」と、今日の世界は明日も続くと信じる「慣習の自己実現」に分解したところにある。慣習と疑いの大小により、貨幣は求められたり捨てられたりする。これはちょうどケインズが『一般理論』で株式投機にかんして論じてみせたことでもある。
ではバブルの生成や崩壊といった不安定性を制御するには、どうすればよいのか。著者はハイエクの「貨幣の脱国営化論」すなわち民間銀行の競争的な貨幣発行により、貨幣の質を高めることに注目する。この見方からすれば、日銀がインフレを目指すというのは円の質を劣化させることだから、一時的には好景気を招き寄せても長期的には経済を不安定化させるだろう。
本書はケインズとハイエクの貨幣論を継承するものである。とすれば、危機には政府が対応すべしとした前者と政府の対応そのものを拒否した後者の対立が気にかかる。本書はコンパクトながら、読者をさらに大きなテーマへと誘ってくれる。
ALL REVIEWSをフォローする