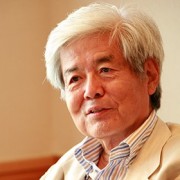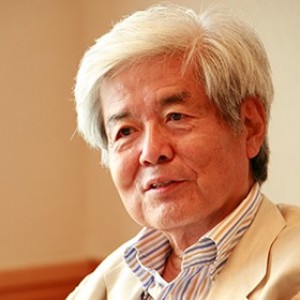書評
『脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?』(河出書房新社)
知識携え正面から向き合う
八十歳を過ぎて、アルツハイマー病の本なんか、読みたくない。でもあるものは仕方がないし、いずれは我が身かもしれないしなあ。自分が認知症になるのがイヤなのではない。そんなことは言ってもしょうがない。でも周囲が困るだろうなあと思う。そう思っても手の打ちようがない。死ぬのもそうだが、私が死んだところで私自身の知ったことではない。あんがい気づかない人が多いと思うが、病気も同じである。本人は痛い、つらいと大騒動、他を考える余裕がない。でも家族は大変である。その意味では、死も病いも、かならずしも本人のものではない。
表題の通り、ごく素直な本である。脳科学を研究している娘が、母親が認知症になったらどうするか。どう考えればいいのか。とりあえず治療法はない。専門家だから、それはすぐ調べられるし、わかっている。
まず最初は否認である。そんなはずはない、母親がどこか少し変だけれど、一時の不具合だろう。でも病は意地悪く進行する。ついには病気と認めざるを得なくなって、病院に連れて行き、正式にアルツハイマー型の認知症だと診断される。
そこから受容が始まる。はかばかしい治療法はない。それはわかった。でも、本人のためにも、自分のためにも、なにかできることがあるだろう。これを重苦しく書けば悪戦苦闘だし、軽く書けばウソになる。
脳科学を学んだことを、著者は生かそうとする。認知症の母親がわからないことを言う、行う。娘はとりあえず驚き、怒り、嘆く。でも母親の立場で考えたらどうだろうか。
連れ合いである父は母と散歩することにする。母本人は気持ちがいいらしい。喜んで行くし、父に腹を立てていても、やがて忘れて一緒に散歩に出る。
母にはなにができなくなったのだろうか。娘はそれを追求する。一緒に台所に立つ。もちろんあれこれモメるのだが、それによって、母にできることと、できないことがあることがわかってくる。それがわかってくると、怒ったり嘆いたりする代わりに、ああしたらどうか、こうしたらどうかという具体的な方法が見えてくる。
誤解されることが多いが、認知症では感情ははっきり残っている。自尊心を傷つけられれば怒る。なぜ自分が怒ったか、それを忘れてしまっても、怒りだけが残ったりする。精神科医には患者さんに殴られる人と、殴られない人がある。そう先輩に教わったことがある。殴られる人は患者さんの感情が見えない人なのであろう。
脳の中では感情の方が、いわゆる理性より安定していて、病気でも壊れにくい。感情は一時的だと思うから、不安定だと錯覚する。でもじつは人は感情の動物であり、感情がなければ、生きるための力が欠ける。私は子どもの頃からクモが嫌いで、いまでも嫌いですからね。
「母と一緒で嫌なこともあるけれど、嬉(うれ)しいこと、学べることがたくさんある」と著者は書く。「理解力が衰えて、なお残っているものが、母が人生の中で大事にしてきたものなのではなかろうか」
人生には負の面がかならずあって、それを想像すると極端になりやすい。その治療はじつは簡単で、正面から向き合えばいいのである。著者は脳科学を武器として母親の認知症に向き合った。健気(けなげ)な戦いだと思う。この戦いには勝ち負けはない。ただ一つ、そこで得られるものがある。それは自分が成熟することである。その意味で人生は一つの作品である。著者という作品が完成に近づくことを期待する。
ALL REVIEWSをフォローする