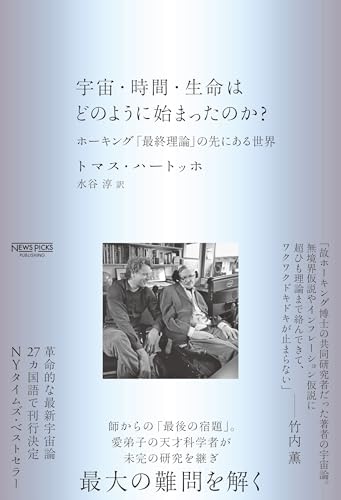書評
『天然知能』(講談社)
外部を招き入れて理解を実現
著者の名前を見ただけで難しかろうと敬遠するのが無難とわかっていながら今回はあえて取り上げる。「天然知能」という言葉で、私が生きものの感覚として大事にしていることを論理的に考えてくれているのではないかと感じたからである(間違いでないことを願いながら)。近年話題の人工知能の対義語としては自然知能を考えるのが通常だが、著者はそこに天然を持ち込む。世界に対する対処の仕方を身近な生きものへの向き合い方によって人工・自然・天然の三つの知能に分けるのだ。人工知能は、自分にとっての用途、評価を明確に規定し、その上で対処する。自然知能を著者は「自然科学が規定する知能」とする。私は生きものである人間として考える時にはたらくのが自然知能と考えてきた。しかし、自然科学的思考が一般化している現代社会では、機械論を背景にした知識の蓄積が知能とされているための悩みがある。そこで、自然知能を自然科学的思考ときめてしまうことにはやや抵抗を感じながらも一応その意味は理解しようと思う。そして天然知能は、「ただ世界を、受け容(い)れるだけ」とある。少しわかりにくいが、「子供の頃、ドブ川でナマズを捕っていた私は、天然知能でした」という文で、私もそうだったし、今もあまり変わらないと思うのである。自然知能は問題や謎として知覚されたものだけに興奮し、人工知能は知覚できたデータだけを問題にするのに対し、「見えないものに興奮するのは、天然知能だけの特権」なのだ。
各章は、サボテン、イワシ、カブトムシ、シジミ、ライオンなどの生きもので語られる。たとえばイワシの章には、「太平洋を泳ぐイワシ」が登場する。直接それを見ることはまずないが、本や映像での知識から推定して誰もが太平洋のイワシの存在を信じる。そう考えるのが普通だろうが著者はそうではないと言い切る。大事なのは、イワシという問題と大海を泳ぐイワシという解決の間には大きなギャップがあり、そこに外部を招喚することが重要であって、これができるのは天然知能だけだと言うのだ。天然知能が解決を求める時には、決してこれで終わりにはならず、常に「もっと何かあるだろう」になるのである。そこに発見があり、理解があるのだ。「外部に踏み込み、その外部を招き入れることで、物事の理解を実現する」。こんなあたりまえのことをなぜ今まで誰も教えてくれなかったのだろう。
これは「生物として生まれてから、『わたし』という主体が生まれてくる過程」にも適用される。主体として意見をもつようになる、つまり「おのずから」から「みずから」へと変化する過程は、三人称から一人称への視点の変化と言える。しかし、一人称といえども「食べたい」は外部から「食べたいと思わされている」のでもあり、能動か受動か明確には決まらない。これを著者は一・五人称と呼び、われわれは常に「おのずから」と「みずから」の間を揺れ動いており、これが天然知能がはたらいている状況だとする。これもなるほどである。
イワシだけで紙幅が尽きてきたが、基本はここにあると思うのでお許しいただきたい。結局、問題と解答、原因と結果、意図と実現がすっきりつながる「かっこいい」に対して、それが一致しない「かっこワルイ」が天然知能なのだ。しかも一方的に外部が関与する「ダサい」もある。そこで天然知能は「ダサカッコワルイ」になる。でも私はこれが好きだ。読み終わっての思いである。「ボーッと読んでるんじゃねえよ」と叱られる読み方かもしれないけれど。
ALL REVIEWSをフォローする