書評
『秘伝 大学受験の国語力』(新潮社)
個性尊重教育と入試問題
『秘伝 大学受験の国語力』を読む
あるとき、評論家、小林秀雄(一九〇二~八三)の娘が国語の試験問題をみせて、「なんだかちっともわからない文章」と質問した。小林も読んで、なるほど悪文とおもい、「こんなもの、わかりませんと書いておけばいい」というと、娘は笑い出した。「だって、この問題は、お父さんの本からとったんだって、先生がおっしゃった」。いまだったら、小林秀雄のお嬢さんにはぜひ、本書(石原千秋『秘伝 大学受験の国語力』新潮選書、二〇〇七年)をすすめたい。目から鱗のはず。
問題文は複雑に入り組み、迷わせようと仕組まれた事件なのだ。だから場数を踏んだ名探偵の推理力を傾聴するにしくはない。
本書は、大学入試センター、私立大、国立大にわたる事件(問題文)にわけいって、解決法を具体的に示している。「二項対立整理能力」や「翻訳能力」などの迷宮を解きほぐす推理の方程式がくりだされる。
名探偵は入試問題攻略法だけを説いているわけではない。おりおりにはさまれた歯に衣着せぬ教育論が光っている。
本当に「個性尊重」教育をもとめているのなら、「本文の言葉を適当に用いて説明する」などの問題はやめて、つぎのような問題にするべきだという。「本文の言葉を出来るだけ使わずに説明しなさい」。人と違うことに価値があるのだという思想を教えるには、「お題目ではなく、こういう具体的で切実な方法が何よりも有効」という(四四~四五頁)。なるほど、入試問題は絶大な教育力をもっている。
昔の入試国語も紹介され、解説されているが、一九五五年の立教大学経済学部の問題はすごい。
漱石や谷崎潤一郎など十の小説の冒頭部分を書き出し、作者と作品名を答えさせるもの。
文学的教養をためす試験ともいえるが、本当のところは出題者が労を省いた出題だったはず。こんな出題者の手抜きが許された時代がわかっておかしい。だから受験生や国語教師、出題者はもとより、受験生の親も年配者も存分に楽しめる。
ALL REVIEWSをフォローする









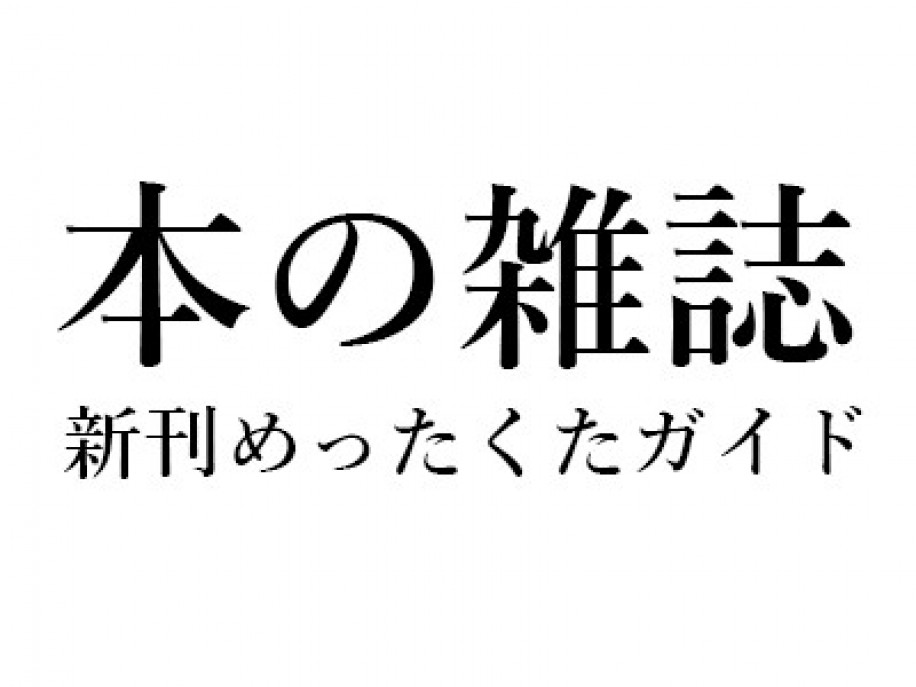

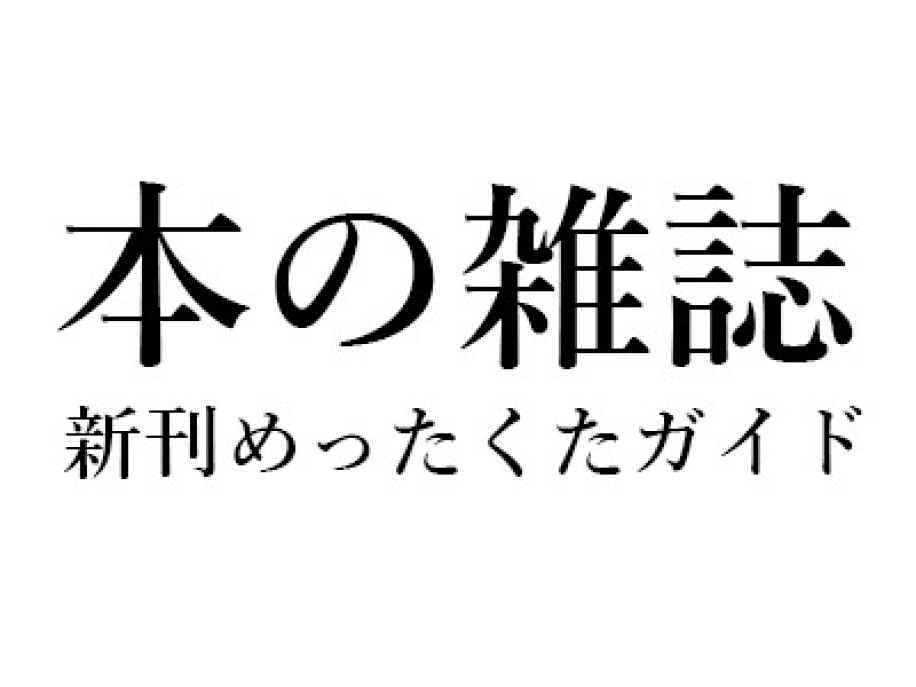




![正解がない時代の親たちへ 名門校の先生たちからのアドバイス[エッセンシャル版]](https://m.media-amazon.com/images/I/411xtqUxpxL._SL500_.jpg)























