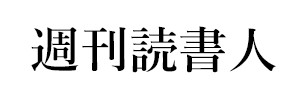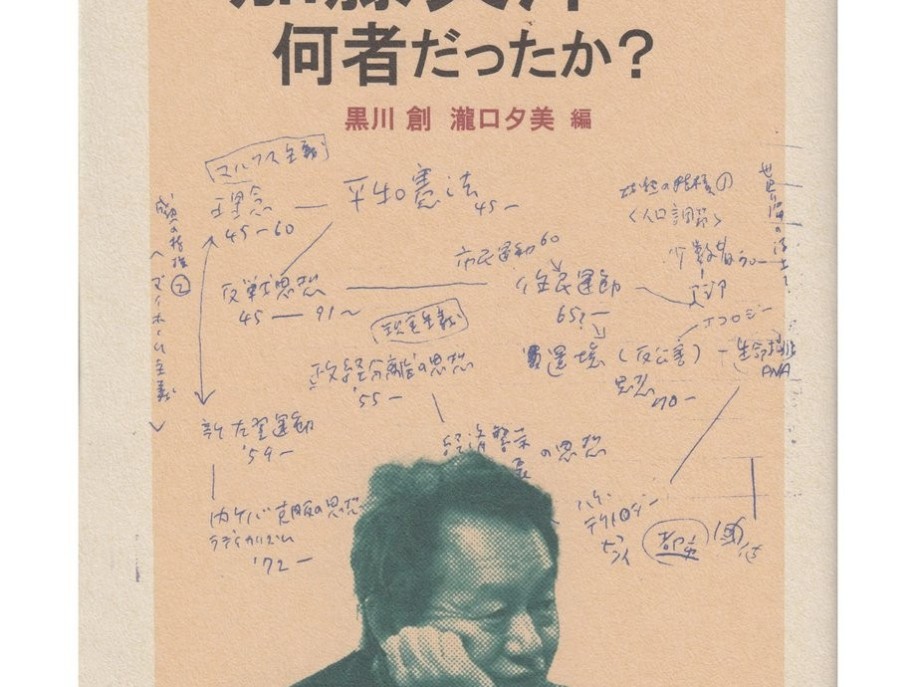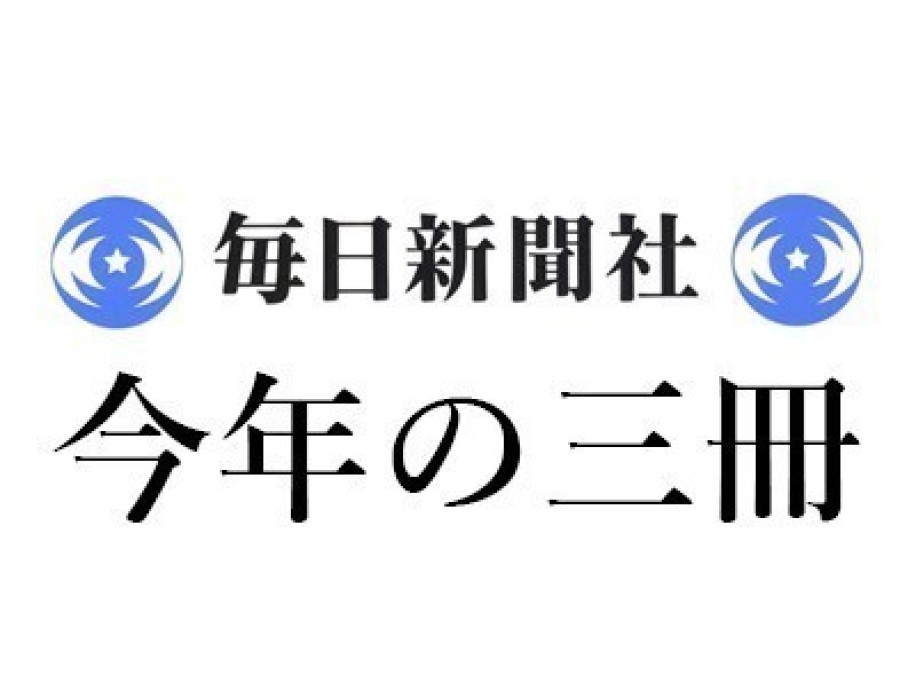書評
『ゼロ戦 沖縄・パリ・幻の愛』(集英社)
ゼロを追い求める者
三十八歳のフランス人女性作家とゼロ戦に、いったいどんなつながりがあるのか。彼の地でいまだに根強く流布しているハラキリやカミカゼの変奏を聞かされるのか、それともまったくあたらしい趣向が仕組まれているのか。一九九六年度のゴンクール賞受賞作という評価がなければ、またこの作者が、現在のフランスでは貴重な短篇擁護をもくろむ叢書から一冊の作品集を世に問うていることを知っていなければ、いささかきな臭い書名を堂々と掲げた本書を手に取ることはなかったかもしれない。語り手は一九四四年、ニューヨークでアメリカ軍人とフランス人女性とのあいだに生まれたローラ・カールソン。父親は翌年、沖縄で戦死し、母親は二歳の娘を連れてパリの実家に戻るのだが、精神に異常をきたしてアメリカ時代の記憶を失い、部屋に閉じこもるようになる。ローラの幼年期は、母の放縦を許さない祖父母と永遠に不在の父、そしてほぼ存在しないに等しい母親の沈黙に閉じこめられてしまう。彼女の殻が破れるのは、友人の導きで、ながらく家庭ではタブーであった父親の死の状況を理解し、特攻隊員の手記を読んでからのことである。
多くの評者が指摘するとおり、ゼロ戦のzéroのなかに著者の名であるRoseが埋め込まれているとすれば、「ゼロを追い求める人」とも解しうる原題の戦闘機は、そのまま自己認識の、さらには自己追放の装置となるだろう。じじつ、彼女の心に住み着いたのは幻の父親その人ではなくて、彼を死に追いやったカミカゼの方なのだ。中耳炎にはじまるローラの幻聴が戦闘機の爆音を呼び寄せ、日本兵の姿を身近に現出させるのは、自爆を選んだ異国の若者の行動が、受け身の世界観からははずれた、しかし同時に限りなく閉塞的で、限りなく前向きの方途と映ったからである。
モーリス・パンゲ『自死の日本史』(筑摩書房)の、それも特攻隊員たちの「無と同じほどに透明であるがゆえに人の眼には見えない、水晶のごとき自己放棄の精神」を解き明した章を繰り返し読み、深い影響を受けたという作者が主人公に託したものは、死と引き替えに輝かせるべき象徴的存在を引き抜いた、自分自身のための通過儀礼だった。恋人に作曲家の卵をあてがい、幻聴に満たされた存在の核をわざわざ芸術に譲り渡すことで骨抜きにしてしまったりーー軍服に身を固め丸刈りになることで、この作曲家は幻想のなかの日本兵と交錯し、さらに深くローラの内部に侵入するーー、カミカゼと一体化して自動車で自殺に向かわせる際、六〇年代の熱狂とかけはなれたうそ寒さを彼女の周囲に漂わせるあたり、ただ勢いに任せて書いたのではない、沈着な推敲があるように思う。意表をつく設定と、ひと息に読ませる簡潔な文体。『めす豚ものがたり』のダリュセックもそうだが、ここにはほのかな古典文学の香りがあって、それが作品の破綻を防いでいる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする