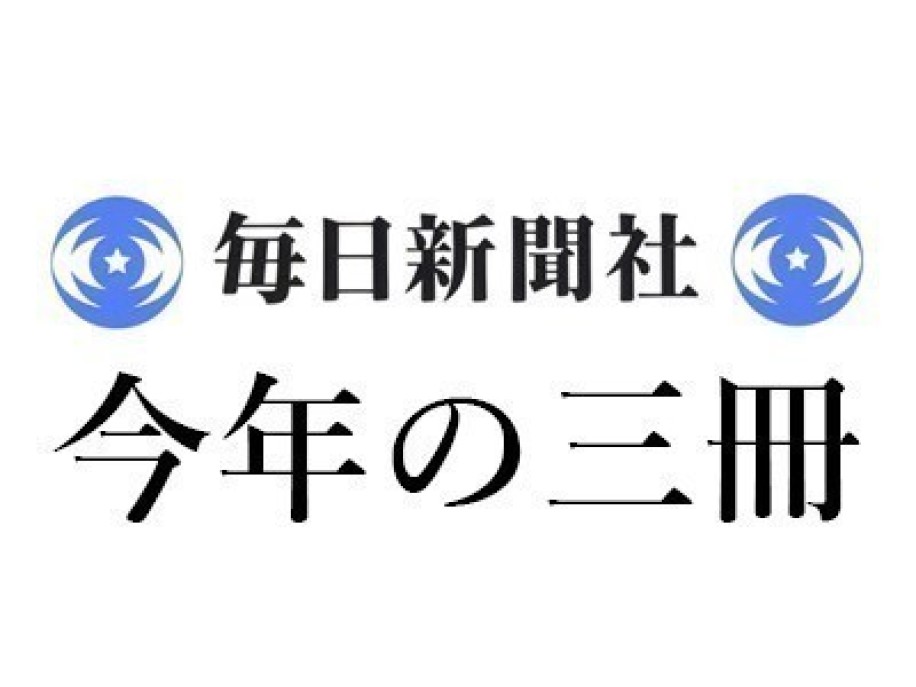書評
『蔭の棲みか』(文藝春秋)
自然体が生む目線の確かさ
芥川賞を受賞した表題作を巻頭に据えて、前候補作と「文學界」の同人雑誌優秀作に選ばれた初期の作品が遡行(そこう)的に収められている、新鋭の第一短篇集。書き手の足取りと変化がおのずと明らかになる、読者には親切な構成だ。しかしそれをあえて逆からたどってみよう。「舞台役者の孤独」は、集中もっとも熱気にあふれた作品である。「更生した」元不良少年の主人公とかつての子分たち、そしてそれを統括する差配の男たちの体臭が、濃くにおい立つ。幼かった義弟の死にとらわれている主人公の迷いを、「かれ」という三人称単数のごつごつした繰り返しが、巧みに表現している。
真ん中に収められた「おっぱい」の言葉は、題名どおり大変に柔らかい。子どものない共働き夫婦の家に、妻の恩師で生活に窮した老人と、目の不自由なその娘が、乳飲み子を連れて、いわば無言のおねだりにやってくる。母親となった彼女の豊満な乳房が、夫婦の関係に、一瞬、瑞々しい変化を及ぼす。このあたりの展開が良い意味で技巧的な、転換期の作品だ。
表題作は二作の長所、つまり登場人物に対する親近感と冷静な「引き」をほどよく調和させている。狭い路地が縦横に走るバラック集落に七十年近く住み着いている、右腕のない主人公ソバン老人の、したたかでどこかいいかげんな、愛すべき弱さがいい。
いま私は、収録作の登場人物がみな「在日」の血と歴史を抱えているという事実を、あえて省いてみた。作品にそなわっている物語の骨格と軽快なリズムは、出自を見据えつつ、それだけに頼らない力をあかしているからだ。
日本軍として戦った韓国人兵士への補償問題に対するソバン老人の反応は、たしかに本書の核であり、「在日」への新しい光ともなるだろう。だがこの自然体を生んだのは、書き手の目線の確かさなのだ。それを忘れてはならない。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
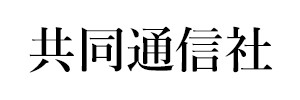
共同通信社 2000年3月
ALL REVIEWSをフォローする