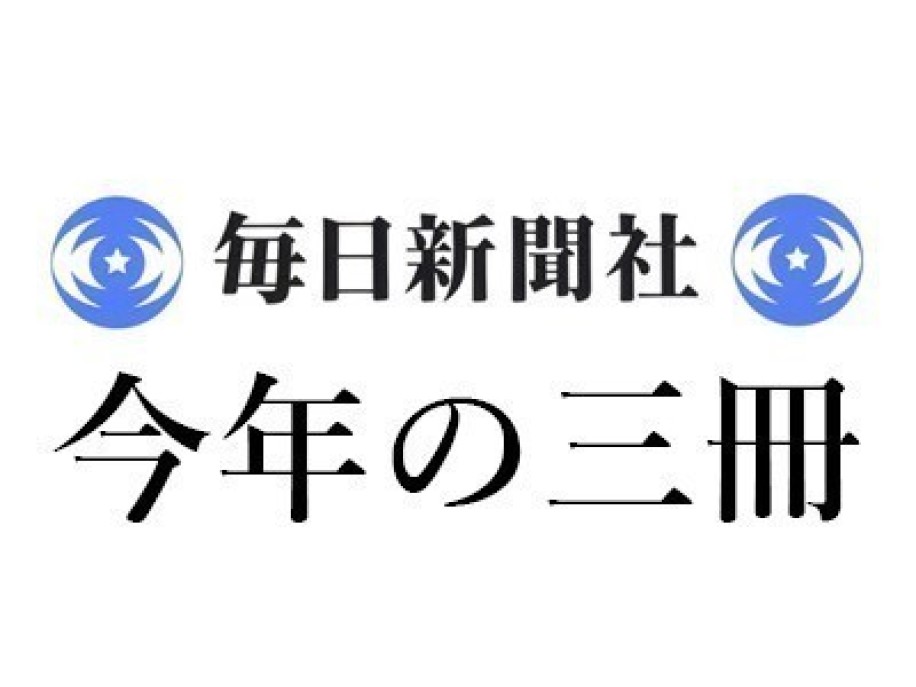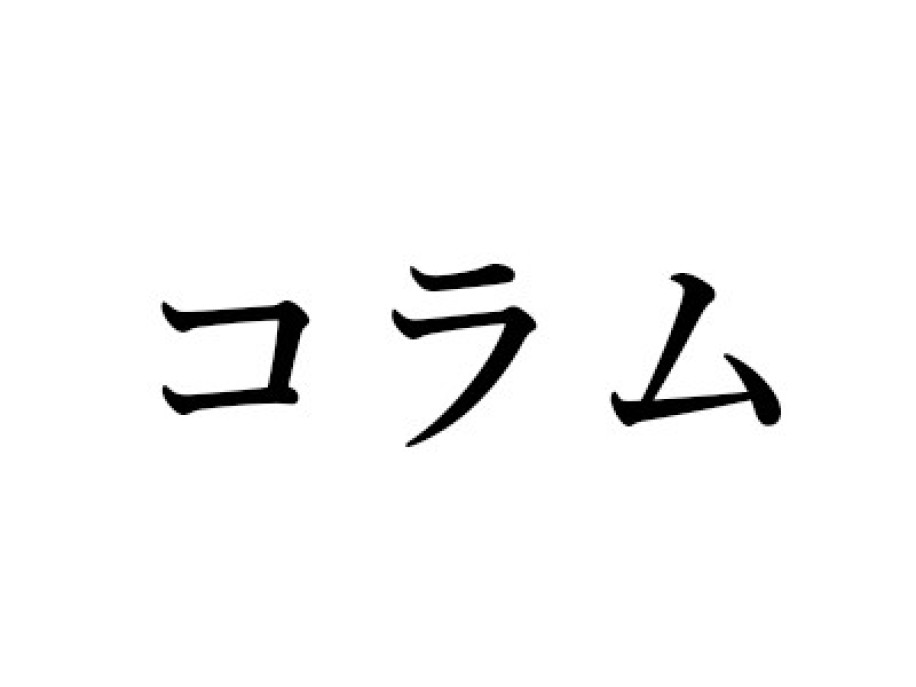書評
『巴』(新書館)
一文字の魔力
一九九六年から二〇〇〇年十月まで、計二十四回におよぶ雑誌連載を全面改稿した長篇小説である。隅田川一帯を舞台とする本作は、東京周辺部を描く薄暮、および薄明の、時間と場所の境界線を扱った過去の諸作とさまざまな部分で響きあっている。だが本書ともっとも深いかかわりがあるのは、おそらく左右対称の一文字をタイトルに掲げて、めくるめく官能と、いわばうらぶれた形而上学を提示した『幽』(講談社)だろう。一枚の鏡を、ガラスを介して人が向き合う不思議なこの文字に魅了された著者が、おなじくたった一文字の魔力にひかれていくのは、当然の事態かもしれない。
語り手の大槻は、東大を中退した三十代半ばのインテリ崩れで、寛子という人妻のヒモのようなかっこうで食いつないでいる。一九九四年の夏の夕べ、大槻はかつて「東洋経済研究所」なる職場で同僚だった男と再会し、とある書の大家が翻訳者を探しているから手伝えと誘われる。
釈然としないまま、差し出された報酬につられて出かけていったその篝山(こうやま)と名乗る老人の家で、彼はポルノと昆虫の記録映画がモンタージュされたような、奇怪な十六ミリ映画を見せられる。そのなかでいかつい男に抱かれ、あられもない声をあげていた少女が、朋絵だった。大槻は篝山から、翻訳ではなく、この少女を使った映画撮影の一部を担当してくれと頼まれる。ここから、朋絵=巴(ともえ)をめぐるミステリーがはじまる。
巴とはなにか。完全には閉じていない、左回りの方向性を示す渦である。この物語が円環を、それも逆向きの円環を志しながら、最後の最後まで破綻へのあこがれを失わずにいるのは、円になりえない「巴」一文字の、わずかな亀裂のせいなのだ。
いくつもの「今」が渦巻いてつくりあげる時間を、いかに食い破り、外へと逃れ出るか。本書はこの、左回りの渦を右回りに変えようとする不可能への、果敢な挑戦なのである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
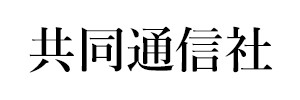
共同通信社 2001年7月1日
ALL REVIEWSをフォローする