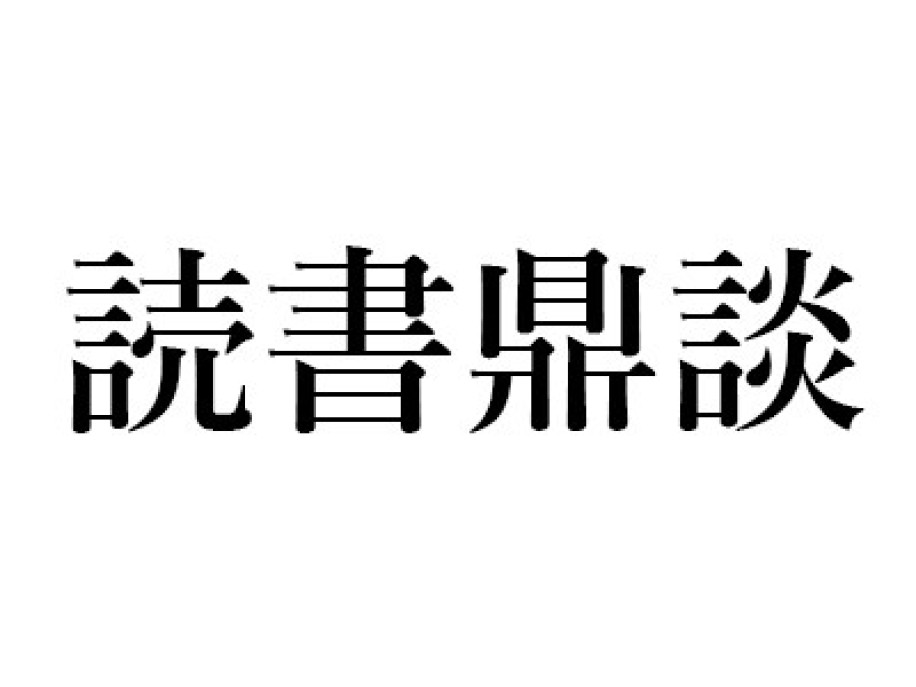書評
『上海―都市と建築 1842‐1949年』(PARCO出版局)
光と闇の衝突する魔都形成の基本書
パリもロンドンもいいが、薬物にも似た魅力という点ではやはり上海がいい。昭和はじめに村松梢風あたりが言い始めたらしい“魔都”の魅力は今も消えていない。もちろん、父と娘の分乗した二台の人力車が夕暮れの雑踏を走っていて角を曲がった時、後ろの娘の車が横道に消え、それっきり行方不明になった、というような魔都ぶりは今はないが、また別の光と闇の交差が街をひたしている。たとえば、郊外の旧ロシア正教会に行くと、高天井の堂内には数家族が小屋がけして暮らしていて、コンロの夕餉(ゆうげ)の煙が大ドームの中を立ち昇ってゆく。あるいはバンド(河岸のビル街)の旧ジャーデン・マゼソン商会の華麗な石造ビルの一階の積み石の上には青菜が干され、上階にはオシメが風に揺れている、といったふうに、外国人居留地百年の富の蓄積が生んだ純ヨーロッパ式の都市が物体としてありながら、そこでの人の暮らしぶりは純中国式である。この、物体の方も人の方も絶対に相手に譲るまいと決意したかのようなギャップと、そこから生まれる奇妙な活気こそ今の上海が旅行者を引きつける魔性の魅力だろう。ともかく、街に入ったとたん、視覚が騒然とするのである。
昔の魔都と今の騒然都市の魅力は多くの物書きを引きつけ、これまで“上海”と題したたくさんの本や研究書が日本でも世界でも生まれてきた。それらのほとんどは上海の人と事件と社会をテーマとしている。もちろん都市で一番面白いのは人と事件だからそれでいいのだが、しかし、実際に上海の街角に立った時、目の前に壁のように続く石や赤煉瓦の西洋館について知らないとなんだか損したような気持ちになる。
世界で最も個性的な都市の一つにちがいない上海の都市形成と建物についての基本書を世界の誰が最初に書き上げるかは隣国の者としてはおおいに気になってきた。英国かアメリカか中国か日本か。さいわい、このたび日本の村松伸がそれをなしとげてくれた。上海の資料は、地元中国とイギリスをはじめとする欧米諸国とそして日本の図書館や文書館に眠っているのだが、これらを利用するには中国、日本、英語の三ヵ国語が欠かせない。この条件を満たせる者はそうはいない。日本の研究者が一番近道に立っているわけで、そうした和漢洋に通じている日本の利点を生かした成果だった。
とはいっても、和漢洋の三つの活性度には差があって、やはり根が中国建築史研究者だけあって漢の知識を働かせたところが一番発見的、内発的で面白い。和と洋はやや“学習的知識”のきらいがある。
たとえば、外国人居留地の上海で一番地価が高かったところが西洋館の並ぶバンドではなく、その背後に“不法”に形成された中国人街の一区域であることを発見し、その理由を古地図などから探るところは他の追随を許さない。一区域というのは“悪所”で、日本の地上げ屋も顔負けの欧米人のディベロッパーが現地人居住禁止の原則を犯して居留地内で中国人向けの長屋経営を大規模に行い、それに乗じて中国人は、西洋館の背後に、悪所もあれば市場もあり金満商人もいれば乞食もいるし青幇(チンパン)の手先も徘徊する自分たちの街を作ってしまう。百五十年前の誕生の時から、上海は、光と闇、アジアとヨーロッパが衝突する魔都であった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする