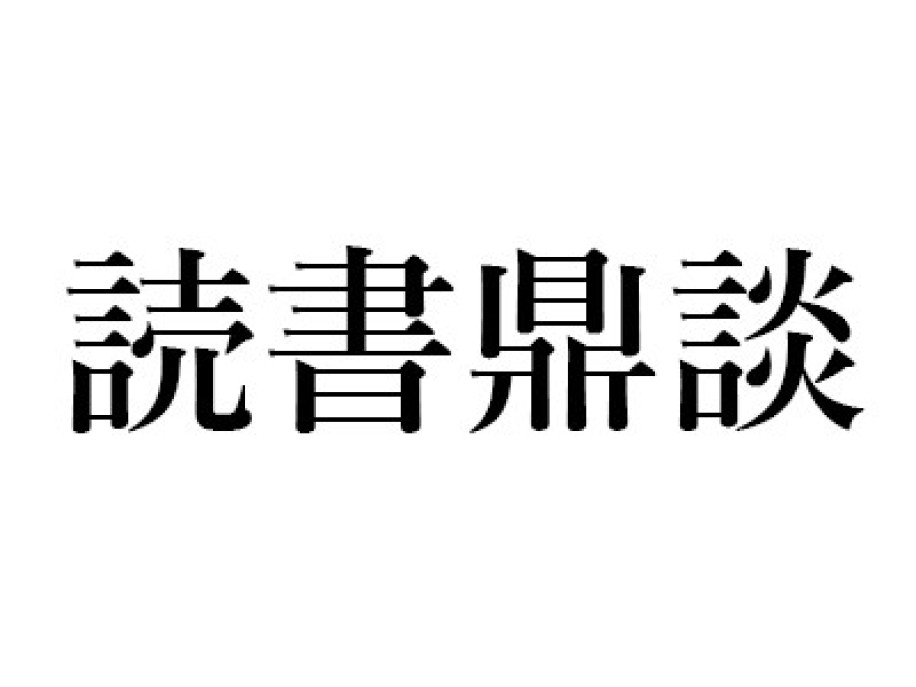『森の掟―現代彫刻の世界』(小沢書店)
視覚の奴隷化した触覚の解放を訴える
同じ建設業ではあるが、土木と建築には大きな差がある。土木は何百億もの闇献金を生み出すが、建築にそういうパワーはない。たとえがまことに悪いけれど、絵画と彫刻の差は、土木と建築の差に似ていなくもない。絵画は、闇献金のお札がわりにもなり、また美術評論家や美術史家に原稿料をもたらすが、彫刻にそういう現実的特典はとても期待できない。疑う人は、本屋に行って美術関係の棚を見るか、銀行の地下の貴重品保管庫を見せてもらえばいいが、幅を利かせているのは絵(屛風もあるらしい)だけで、彫刻はほとんど相手にされていない。
そうした中で、彫刻の味わい方について絵同様に知りたい、とか、芸術だかゴミだか分からない現代彫刻の存在意義に興味を覚えた人は、本屋の美術書の棚に目を凝らしてこの本『森の掟』(小沢書店)を探してほしい。著者は、かの神奈川県立近代美術館の館長だから、絵も扱っているにちがいないが、彫刻についての語りは群を抜いている。
近現代の日本と世界の彫刻と彫刻家を一作一作、一人一人とりあげて語る本だから、石彫から木彫、金属までいろいろあるし、亡くなった高名作家から若手まで含まれるが、力こぶが入っているのは木彫、とくに日本の木彫について。
現代芸術は形にばかりこだわり、さらに記号化しはじめた結果、生命力を喪ってしまった、という基本的見方に立ち、著者は、彫刻の重要さを訴える。絵は視覚の産物だが、彫刻は触覚の産物であり、その触覚は、子供の成長過程を見れば分かるように「あらゆる感覚機能のなかで、いわばその土台であり証人となるべきもの」にもかかわらず、文明社会の中では、「日常の意識が、たえず触覚を別の感覚で代用してしまうため」力をなくしてしまった。ここに現代芸術の病根があり、再び生命力を回復するには、今や「視覚の奴隷となっている触覚を本然の姿に解放する」必要がある。
その主役となるのは彫刻、とりわけ日本の木彫というわけだが、なぜかというと、日本の木彫は、円空仏に見られるように、昔から「木のもっている一種のアニミズム的な生命感を巧みにみつけだしている」からだ。
円空仏的伝統はヨーロッパ化して石と金属に目覚めた現代の日本の彫刻界に生きているかしらん、と疑う読者のため、著者は、四年前に急逝した砂澤ビッキの仕事を提示して語る。
素材の木のあつかいが、わたしのこれまで接してきた彫刻家のそれとちがって、きわめて木の素性に親しんでいる……人間のもつ感覚を総動員して、まさに木を自己の肉体の一部と化する彼の手続きが、当の自分にさえもよくは知らぬ不思議な力に満ちて、何か霊気のようなものを発散している。
著者の願うように、視覚の奴隷となり果てた触覚の解放がはたして起こるのか、それとも、触覚はおろか絵画的視覚すら動物的なものとして捨て去って、記号化、電子映像化へと進んでいくのか、文明の未来の知覚の形式はいまだ霧の中だけれども、私としては、四分六くらいで著者に賭けたい気持ちがこのごろ切にしている。
まったく余計なことだが、著者の由緒ありげな姓名はたまたまそうなっただけで、北海道の森の中に生まれたそうだ。
【このが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする