書評
『福田恆存全集〈第1巻〉』(文藝春秋)
『福田恆存全集』
半年ほど前、ついに決意して『福田恆存全集』(文藝春秋)を入手した(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は1992年)。気になる表題のものから少しずつ読んでいる。せっかちな私にしては珍しく、何編かの評論を読んでは、何日間か間を置いてまた読み進んでゆくというやり方である。なぜなら、福田恆存という人は私にとってちょっと特別の人だからだ。大学の社会主義研究サークルの合宿の席で「今、気になっているのは福田恆存」と切り出したら、一笑に付され、そこであくまで自分の関心に執着してゆける人間だったら私ももう少したいした人物になっていただろうが、「保守反動イデオローグ」というレッテルにおそれをなして、さっさと引っ込めてしまった。福田恆存という人にたいして私はそんな恥ずかしい記憶を持っている。
それなのに、この数年、(大げさなようだが)いろいろな物事が私を福田恆存のほうへと突き動かしているように思えることがたびたびあった。誰かに耳もとで「まだ問に合う。早く読め」とせき立てられているように思われることがたびたびあった。それで決意して読み始めたわけだが、かつてヒョイと無視した思想に、時代が変わったとはいえ、またヒョイと乗っかるわけにはいかない。それで、できるだけ意地を張って、あやしみながら読もうとしているわけだ。
それでも、次のような一節に出会うと、「私のこの二十年三十年はいったい何だったんだろう」とガッカリしてしまう。
大衆の無知を軽蔑することはない。が、無知なものは無知だと言つたはうがよい。それを怒り、それを教へたはうがよい。事実、無知なのに、何もかも心得た大衆の智慧を仮想することはあるまい。さうしておだてたり媚びたりせずにはゐられないのは、要するに彼等が無知といふことを軽蔑してゐるからではないか。
私は大衆を自分にとつて好都合な価値として信じないが、たとへ自分にとつて不利な存在でも力としてなら信じる。
大学生のころから、私にとっての大きな謎は「大衆」というものだったような気がする。雑誌といってもアカデミズムや論壇とはまったく関係のない女の子雑誌の世界を右往左往して暮らして来たが、そういう中で私がボンヤリと学んだことはやっぱりこういうことだったのだ。二十年以上もかかって、ようやっとこの一節にたどりついただけとは。
全集の第五巻には一九六〇年代初めに集中的に書かれた、「言論の自由」にかんする評論が何編かおさめられている。
『言論の自由』とは何か。元来、それは『政府干渉からの』自由を意味した。したがつて、それはあくまで消極的なものである。
法律用語としての『自由』も『幸福』も、それが法律用語である限り、積極的な意味をもちうるものではなく、あくまで消極防衛の限界内に留らねばならない。
が、それ(=私事を秘めるということ)は飽くまで人間の生き方に関する道徳問題であつて、権利義務の法律問題ではない。大げさに言へば、今日の文化の荒廃現象は、前者によつて解決すべきことを常に後者によつて解決しようと計ることから生じたものである。
――というような、非常にまっとうな一節を読むのはすごい快感だ。ずうずうしいようだが、二年ほど前の“セクシュアル・ハラスメント”論争のころ、私も同じようなことを書いていなかったか。私が言いたかったのは、こういうことだったのだ。
今大騒ぎしている『フライデー』襲撃事件にしても、“有害コミック”問題にしても、えんえんと続く“芸術とわいせつ”問題にしても、こういう視点があればもう少しすっきりした議論ができるのではないか。今の時代の不幸はこういう大人の(と言うのは、人間性や人間の将来にかんして予定調和的な夢想を持たない人ということである)言論人がいないことだ……。
と、意地を張っているわりには、私はたやすく福田恆存の論陣にはまり込んでいるようだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
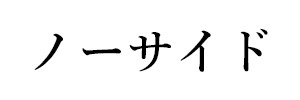
ノーサイド(終刊) 1992年10月号
ALL REVIEWSをフォローする











































